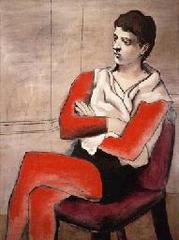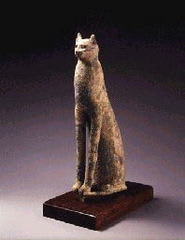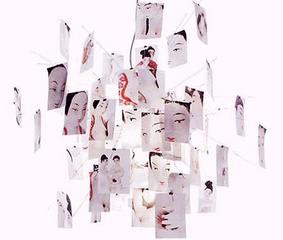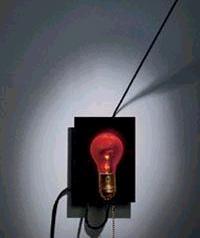新年を迎えて2日目、数年ぶりに東京都写真美術館に出かけた。
この日はなんと3つの展覧会の入場料が無料だった。全ての展覧会を見ると1,700円かかるところが無料とは太っ腹すぎる。無料なので非常に混むかと思ったが、適度な混み具合で作品を鑑賞するのに困ることはなかった。
最初に観覧したのは「映像をめぐる冒険vol.3 3Dヴィジョンズ –新たな表現を求めて– 」(http://syabi.com/contents/exhibition/index-334.html)。
3D映画などで使われている視覚原理「立体視」がテーマ。といっても3D映画やアトラクションのようなスペクタクルを追求するのではなく、歴史を紐解きながら立体視という表現手法に何が可能なのかを検証するというもの。19世紀中頃から20世紀初頭までの立体写真や立体視装置、立体視を利用した現代の作品が展示されていた。
20世紀初頭までの立体写真は、現代の作品に比べて素朴なものだが特別なメガネをかけてみると立体となって浮き出てくるのは単純に面白かった。現代の作品では作者が言わんとすることがよく分からないものがあったが、浮き上がる立体に動きがあってより面白くなった。
次は「収蔵作品展 [かがやきの瞬間] スナップショットの魅力 」(http://syabi.com/contents/exhibition/index-348.html)。
ウォーカー・エヴァンズやアンリ・カルティエ=ブレッソンなど写真史に残る写真家の作品から今回が初出となる新作まで様々な作品が展示されていた。
印象に残ったのはポール・フスコの「RFK Funeral Train」。この作品は、1968年に暗殺されたロバート・ケネディの国葬を行うため、NYからワシントンDCに電車で遺体を移動させる際に、電車の窓から哀悼するアメリカ国民の姿を捉えたもの。
撮影場所は駅のホームや、郊外の住宅地や田舎、都会の古ぼけたアパートの裏の線路沿いなどいろいろ。被写体となった人々は列車を静かに見守る人や列車に向かって手を振ったり、国旗やメッセージを書いた紙を掲げる人など様々だった。作品からその場の空気が伝わり、作品の中の人たちと時を共有している気分になった。
写真についてあまり知らないので作品についてどうこう言うことはできなかったが、数十年以上前の作品では街並みや人々の服装等その当時の様子がわかって興味深かった。
最後は、「日本の新進作家展vol.9 [かがやきの瞬間] ニュー・スナップショット」(http://syabi.com/contents/exhibition/index-342.html)。
2番目の展覧会と同様、スナップショットの展示だが、こちらは6人の新進作家に焦点を当てたもの。
印象に残ったのは2つ。まずは中村 ハルコ「光の音」。イタリア、トスカーナ地方に住む夫婦と彼らの生活、美しい風景を撮影した作品。色彩が鮮やかで美しく、物語の世界のようだった。
もう一つは、結城臣雄の東京の街をテーマにした作品。彼はソニー・ウォークマンのCMの「瞑想するサル」を生んだCM演出家で、2000年頃から東京の街を撮影を開始し、作品数は7万点にも及ぶ。作品は散歩中にさりげなく街を撮影したというような雰囲気のもの。視点が散歩をしている人目線で、自分も東京の街中を散歩しているような気分になる作品だった。
話はそれるがが、2つのスナップショットの展覧会のパンフレットがなかなか凝っていた。パンフレットには複数の作品の画像が載っているが、作品と作品の間にミシン目が入っていて切り離して飾ることができる。現代美術に関心がある人に渡したら好評だった。
久々写真や映像の展覧会を観覧したが、なかなか面白く刺激になった。散歩もよいがたまには芸術鑑賞もよいもの。来年の正月もぜひ入場無料を行ってほしいなあ。
この日はなんと3つの展覧会の入場料が無料だった。全ての展覧会を見ると1,700円かかるところが無料とは太っ腹すぎる。無料なので非常に混むかと思ったが、適度な混み具合で作品を鑑賞するのに困ることはなかった。
最初に観覧したのは「映像をめぐる冒険vol.3 3Dヴィジョンズ –新たな表現を求めて– 」(http://syabi.com/contents/exhibition/index-334.html)。
3D映画などで使われている視覚原理「立体視」がテーマ。といっても3D映画やアトラクションのようなスペクタクルを追求するのではなく、歴史を紐解きながら立体視という表現手法に何が可能なのかを検証するというもの。19世紀中頃から20世紀初頭までの立体写真や立体視装置、立体視を利用した現代の作品が展示されていた。
20世紀初頭までの立体写真は、現代の作品に比べて素朴なものだが特別なメガネをかけてみると立体となって浮き出てくるのは単純に面白かった。現代の作品では作者が言わんとすることがよく分からないものがあったが、浮き上がる立体に動きがあってより面白くなった。
次は「収蔵作品展 [かがやきの瞬間] スナップショットの魅力 」(http://syabi.com/contents/exhibition/index-348.html)。
ウォーカー・エヴァンズやアンリ・カルティエ=ブレッソンなど写真史に残る写真家の作品から今回が初出となる新作まで様々な作品が展示されていた。
印象に残ったのはポール・フスコの「RFK Funeral Train」。この作品は、1968年に暗殺されたロバート・ケネディの国葬を行うため、NYからワシントンDCに電車で遺体を移動させる際に、電車の窓から哀悼するアメリカ国民の姿を捉えたもの。
撮影場所は駅のホームや、郊外の住宅地や田舎、都会の古ぼけたアパートの裏の線路沿いなどいろいろ。被写体となった人々は列車を静かに見守る人や列車に向かって手を振ったり、国旗やメッセージを書いた紙を掲げる人など様々だった。作品からその場の空気が伝わり、作品の中の人たちと時を共有している気分になった。
写真についてあまり知らないので作品についてどうこう言うことはできなかったが、数十年以上前の作品では街並みや人々の服装等その当時の様子がわかって興味深かった。
最後は、「日本の新進作家展vol.9 [かがやきの瞬間] ニュー・スナップショット」(http://syabi.com/contents/exhibition/index-342.html)。
2番目の展覧会と同様、スナップショットの展示だが、こちらは6人の新進作家に焦点を当てたもの。
印象に残ったのは2つ。まずは中村 ハルコ「光の音」。イタリア、トスカーナ地方に住む夫婦と彼らの生活、美しい風景を撮影した作品。色彩が鮮やかで美しく、物語の世界のようだった。
もう一つは、結城臣雄の東京の街をテーマにした作品。彼はソニー・ウォークマンのCMの「瞑想するサル」を生んだCM演出家で、2000年頃から東京の街を撮影を開始し、作品数は7万点にも及ぶ。作品は散歩中にさりげなく街を撮影したというような雰囲気のもの。視点が散歩をしている人目線で、自分も東京の街中を散歩しているような気分になる作品だった。
話はそれるがが、2つのスナップショットの展覧会のパンフレットがなかなか凝っていた。パンフレットには複数の作品の画像が載っているが、作品と作品の間にミシン目が入っていて切り離して飾ることができる。現代美術に関心がある人に渡したら好評だった。
久々写真や映像の展覧会を観覧したが、なかなか面白く刺激になった。散歩もよいがたまには芸術鑑賞もよいもの。来年の正月もぜひ入場無料を行ってほしいなあ。