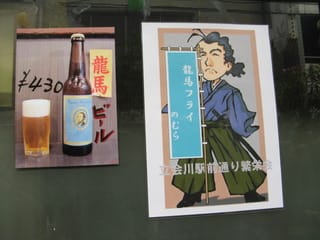(その1はこちら)
■大谷石
宇都宮市大谷町付近に分布する緑色凝灰岩。今から約2,400万年前に海底火山の噴出物によって海底で生成されたとされており、大谷町付近に厚さ約300mにわたって堆積。やわらかく加工が容易なため、古くは古墳の石室の材料として、近世以降には屋根や壁などの建築用材として重宝され、全国に「大谷石」の名で知られた。近世から近代にかけては紀行文、絵葉書、絵画、俳句等を通じて自然の奇岩群と松がみごとに調和した景観が紹介され「陸の松島」として全国に知られた。
■越路岩
「陸の松島」を代表する奇岩で、国名勝に指定。

■奇岩群




■大谷資料館
大谷石の採掘の歴史を紹介する資料館で、地下には約2万平米の地下採石場跡が広がる。地下採石場跡の最深部は60m、平均気温は13℃。地下採石場跡は昭和20年(1945)には中島飛行機(現:富士重工)の地下軍需工場として、昭和44年(1969)には政府米の保管庫として利用されたが、昭和54年(1979)に一般公開。現在は幻想的で迫力のある空間を生かし、コンサートや演劇、美術展などの会場としても利用される。

駐車場にあった奇岩。穴のあき方が斬新。

地下採石場跡に向かう階段。

資料館ホームページの地下採石場跡の写真。下見時は雨が降っていて湿度が高かったせいか、思うように写真が取れなかった。地下採石場跡の様子はGoogle画像検索の写真を見るとよく分かる。
■景観公園
大谷寺の背後にある国指定名勝の御止山が一望できる公園。

■大谷寺
弘仁元年(810)弘法大師による開基として伝えられる天台宗の寺院。本堂は洞窟に包み込まれ、独特の景観。本堂には平安時代~鎌倉時代に大谷石の岩壁に彫られた10体の磨崖仏があり、国の特別史跡と重要文化財の二重指定を受けている。本尊の「大谷観音」は平安時代の高さ4mの千手観音で、日本最古の磨崖仏。宝物殿には洞窟から出土した縄文時代の人骨が展示。


本堂。堂内の磨崖仏は写真撮影禁止。洞窟がサルバドール・ダリの絵に出てきそうな形をしている。
■大谷公園
昭和31年(1956)開園の採石場跡を利用した公園で、石像や奇岩、採石場跡がある。



平和観音。自然の岩壁に彫られた高さ27mの観音像で大谷町のシンボル。戦没者の慰霊と世界平和を祈念し昭和23年(1948)より6年をかけ、総手彫りで製作された。平和観音の裏側の展望台からは大谷の町が一望できる。

親子がえる。住民を蝗から救ったとの伝説のあるかえるの親子。

スルス岩。巨大な石臼に似た岩。

天狗の投石。天狗が投げたという伝説の残る岩。
■その他

大久保石材店。

株式会社屏風岩。

紫陽花と大谷石。

岩壁をくりぬいた門。
■大谷石
宇都宮市大谷町付近に分布する緑色凝灰岩。今から約2,400万年前に海底火山の噴出物によって海底で生成されたとされており、大谷町付近に厚さ約300mにわたって堆積。やわらかく加工が容易なため、古くは古墳の石室の材料として、近世以降には屋根や壁などの建築用材として重宝され、全国に「大谷石」の名で知られた。近世から近代にかけては紀行文、絵葉書、絵画、俳句等を通じて自然の奇岩群と松がみごとに調和した景観が紹介され「陸の松島」として全国に知られた。
■越路岩
「陸の松島」を代表する奇岩で、国名勝に指定。

■奇岩群




■大谷資料館
大谷石の採掘の歴史を紹介する資料館で、地下には約2万平米の地下採石場跡が広がる。地下採石場跡の最深部は60m、平均気温は13℃。地下採石場跡は昭和20年(1945)には中島飛行機(現:富士重工)の地下軍需工場として、昭和44年(1969)には政府米の保管庫として利用されたが、昭和54年(1979)に一般公開。現在は幻想的で迫力のある空間を生かし、コンサートや演劇、美術展などの会場としても利用される。

駐車場にあった奇岩。穴のあき方が斬新。

地下採石場跡に向かう階段。

資料館ホームページの地下採石場跡の写真。下見時は雨が降っていて湿度が高かったせいか、思うように写真が取れなかった。地下採石場跡の様子はGoogle画像検索の写真を見るとよく分かる。
■景観公園
大谷寺の背後にある国指定名勝の御止山が一望できる公園。

■大谷寺
弘仁元年(810)弘法大師による開基として伝えられる天台宗の寺院。本堂は洞窟に包み込まれ、独特の景観。本堂には平安時代~鎌倉時代に大谷石の岩壁に彫られた10体の磨崖仏があり、国の特別史跡と重要文化財の二重指定を受けている。本尊の「大谷観音」は平安時代の高さ4mの千手観音で、日本最古の磨崖仏。宝物殿には洞窟から出土した縄文時代の人骨が展示。


本堂。堂内の磨崖仏は写真撮影禁止。洞窟がサルバドール・ダリの絵に出てきそうな形をしている。
■大谷公園
昭和31年(1956)開園の採石場跡を利用した公園で、石像や奇岩、採石場跡がある。



平和観音。自然の岩壁に彫られた高さ27mの観音像で大谷町のシンボル。戦没者の慰霊と世界平和を祈念し昭和23年(1948)より6年をかけ、総手彫りで製作された。平和観音の裏側の展望台からは大谷の町が一望できる。

親子がえる。住民を蝗から救ったとの伝説のあるかえるの親子。

スルス岩。巨大な石臼に似た岩。

天狗の投石。天狗が投げたという伝説の残る岩。
■その他

大久保石材店。

株式会社屏風岩。

紫陽花と大谷石。

岩壁をくりぬいた門。