神様はきっと人には幸せになって欲しいと想っている。
しかし、人間自身は、神様の御心よりも、自分を幸せにしたいと思うエゴで一杯で、幸せを想う神様に近づく事も感じる事も出来やしない。おまけに自分の心の奥に神様がいる事も知らずに、自分の心しか見ていないのだから。
それでも神様は、いつでも人の幸せを想っているよ。生まれた吾が子の幸せを願わぬ親はいないのです。
私は無能です。人を救う力などありません。だけど、人には幸せになって欲しいのです。
私が歩む坐道は私を救いました。だけど、それを人に示しても、強いる事は道で無くなります。人のそれぞれ縁がある以上、自分が良いと思っても、他人にとって善いとは限りません。願わくば、すべての人が自分に合う道を見つけてくれたらそれが一番良いと思います。
八百万の神々の数だけ道があるのです。そして行きつく頂上は同じです。
人を真に幸せにする道を、様々な道を私は応援します。無学無能な私は応援しかできないのです。
今日も応援。明日も応援。明後日も応援。そして、人を愛する神様も応援します。
人の真心の感化は、きっと全ての万象に通じるのです。
「汝の神は汝を愛し給う。」
 にほんブログ村
にほんブログ村

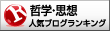
哲学・思想 ブログランキングへ
上記三か所をクリックをお願いします。画面変更後に玄徳道を押しながら順番に押していただけたらありがたいです。
しかし、人間自身は、神様の御心よりも、自分を幸せにしたいと思うエゴで一杯で、幸せを想う神様に近づく事も感じる事も出来やしない。おまけに自分の心の奥に神様がいる事も知らずに、自分の心しか見ていないのだから。
それでも神様は、いつでも人の幸せを想っているよ。生まれた吾が子の幸せを願わぬ親はいないのです。
私は無能です。人を救う力などありません。だけど、人には幸せになって欲しいのです。
私が歩む坐道は私を救いました。だけど、それを人に示しても、強いる事は道で無くなります。人のそれぞれ縁がある以上、自分が良いと思っても、他人にとって善いとは限りません。願わくば、すべての人が自分に合う道を見つけてくれたらそれが一番良いと思います。
八百万の神々の数だけ道があるのです。そして行きつく頂上は同じです。
人を真に幸せにする道を、様々な道を私は応援します。無学無能な私は応援しかできないのです。
今日も応援。明日も応援。明後日も応援。そして、人を愛する神様も応援します。
人の真心の感化は、きっと全ての万象に通じるのです。
「汝の神は汝を愛し給う。」

哲学・思想 ブログランキングへ
上記三か所をクリックをお願いします。画面変更後に玄徳道を押しながら順番に押していただけたらありがたいです。















