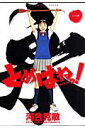


「とめはねっ!」河合克敏 小学館 ~3巻
私立鈴里高校に入学したちょっとガチャピン似の男子高生・大江縁(おおえ ゆかり)は担任の先生に言われ、荷物を教室へ運ぶことになったのだが、そこの教室の中では書道部員が着替えの最中で、縁はノゾキと間違えられてしまう。部員数に悩む書道部は口止め料として縁を書道部への入部を強制させてしまうのだが、縁は帰国子女(男)、筆など持った事はない・・・
そんな時、縁が密かに憧れていた女子柔道の期待の星・望月結希の投げ技に巻き込まれ、腕を骨折してしまうというアクシデントが発生。
責任を感じた結希は縁のいる書道部に期限付きで入部することとなるのだが・・・
柔道、競艇とマイナー競技にスポットを当ててきた河合さんの新作。
実はプロフでも公開していますが、たれぞ~さんは高校時代に書道部に在籍しておりまして、もうツボくすぐられまくりな作品だったりします(笑)
書聖と言われた王義之(おうぎし)などの昔の書の達人の書を真似て書くのを「臨書」というんですが、臨書に関するウンチクもさることながら、河合さんのキャラ設定がしっかりしてて、地味・暗いと言われ続けた文化部の代表「書道部」をこれでもかーと楽しく表現してくれてます。
この3巻ではタイトルにもなっている書道における「とめ」「はね」についても書かれていますが、私が懐かしいなーと感じたのは手本の見方
楷書では区別がつきにくい漢字の書き順ですが、行書、草書となるとこれがとても重要になってきます。
字のバランス、そして筆運びの流れが美しさを現すことにも繋がるので、正しい書き順でその流れを切らないように書くことがとても大切
手本となる字の個性を表現しつつ、この「流れ」を切らさないように書くのが難しいのです・・・
勿論、書き順が違えば流れも変わるので、「美しい字」とはかけ離れてしまうから、先生の見かたも当然厳しい。
そんな臨書の原点を初心者の主人公を通して読者にもわかりやすく、丁寧に教えてくれていますね
そして
「大切なのは自分が興味を持って取り組むこと・・・」
作中で三浦先生の言ったこの言葉が全てにおいての原点のような気がします
「好きこそものの上手なれ」と昔の人は言ったもんだけど、やっぱり好きだと情熱が違うもんね(笑)
キャラクター構成といい、書道を知っている人にも知らない人にも楽しめる作品を作り上げられるのはさすが河合さんの技量ですね。
そして巻末では「篆刻」の話も出てきてましたが、う~んマニアック。
勿論、書道部の私も自前で作りましたともさ。
ここまで漫画でやっちゃうのもやっぱり河合さん(笑)









