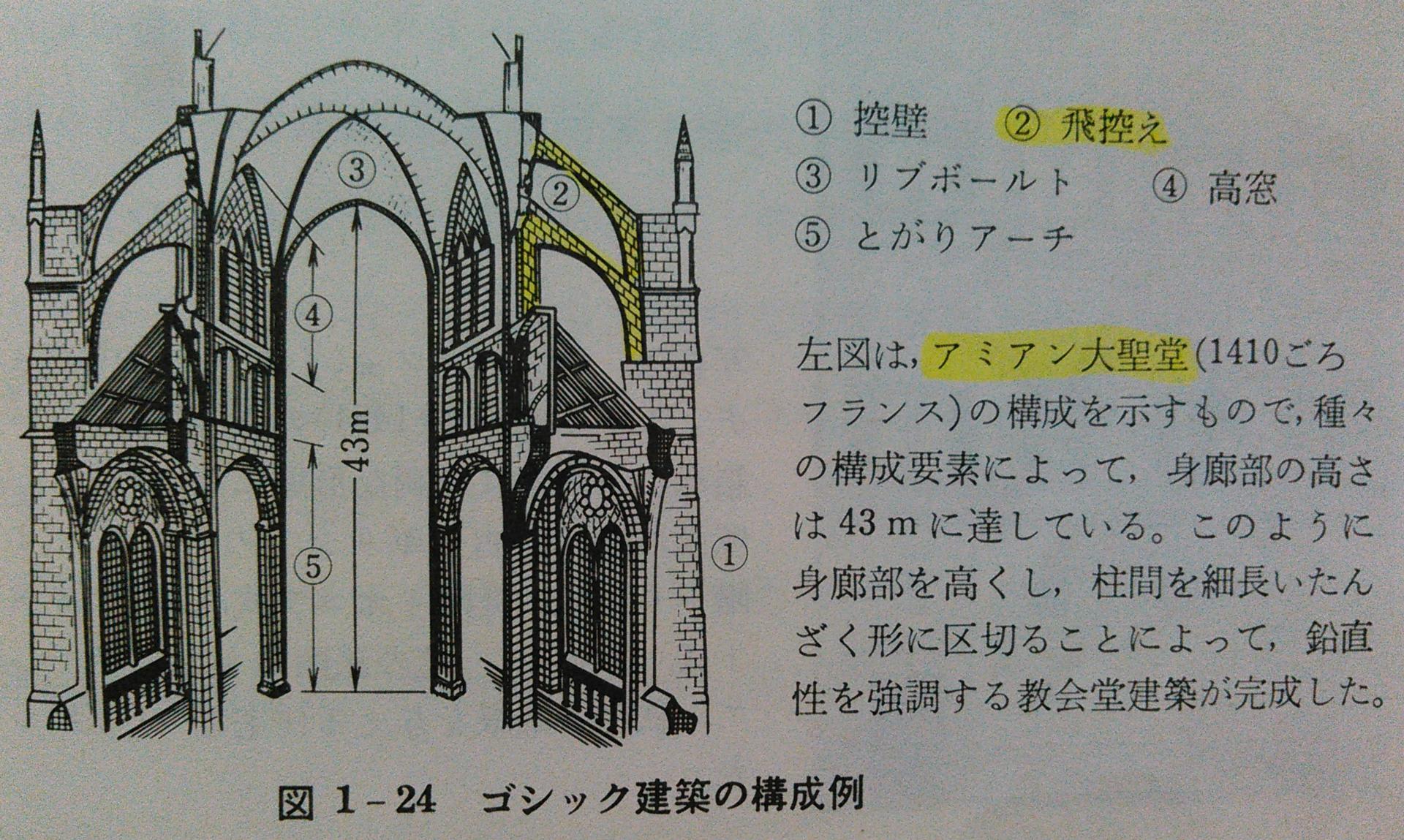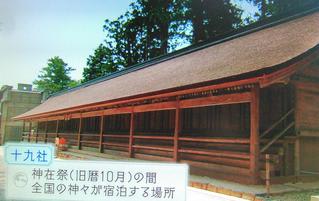これまでの出題とは違った傾向の設問です。今後の主流になるのでしょうか?
二級建築士試験 平成27年「建築計画 建築史」の出題を参考にしてつくりました。
日本の建築物と建築家(設計家)を関連付けてください。
解答
1.聴竹居(1927年) 藤井厚二
2.旧東京中央郵便局(1931年) 吉田鉄郎
3.神奈川県立近代美術館(1951年) 坂倉準三
4.広島平和記念資料館(1952年) 丹下健三
5.東京文化会館(1961年) 前川國男
設問では 村野藤吾氏(目黒総合庁舎)がトラップ。村野建築もチェックしておいて下さいね。
*************************
「京都 聴竹居」 1927年
http://chochikukyo.com/contact/
「藤井厚二」 ~ 竹中工務店のHPより引用させて戴きました。
http://www.takenaka.co.jp/design/architect/01/
藤井厚二は、日本の気候・風土に適応した住宅のあり方を実証するため、大山崎の豊かな緑の中に次々と実験住宅を建てました。
自邸・聴竹居はその集大成であり、和洋の生活様式の統合とともに日本の自然との調和を目指した近代住宅建築の代表作です。
そこには藤井自らが確立した環境工学をもとにした気候・風土と共生するためのさまざまな工夫が施されています。

藤井がデザインした照明器具や椅子とベンチ式のソファーが設えられた応接間で、和と洋が見事に融合したモダンな空間になっています。
正面の床の間は、椅子に座った時の目線にあわせ高く設えてあります。幾何学的な照明は、床側も照らすように工夫が施されています。
居室(居間)の奥には1/4円弧で緩やかに区切られた食事室があります。
また、居室正面壁には、床の間の違い棚のような棚、マッキントッシュ風の時計、壁面に収納された神棚など設えられています。
写真は坂倉順三「旧飯箸邸」「現ドメイヌ・ドゥ・ミクニ」軽井沢

****** 坂倉順三(H26軽井沢の山荘が出題されている) ******
ドメイヌ・ドゥ・ミクニの建物。日本を代表するモダニズム建築として知られる「旧飯箸邸」が東京・世田谷から軽井沢の地に移築されました。昭和16年に建てられ、今も当時のままの姿をとどめる、この木造建築の傑作を設計したのは、20世紀の建築界最大の巨匠ル・コルビジェに師事し、戦後日本の建築界を牽引する役目を果たした坂倉準三氏です。
ドメイヌ・ドゥ・ミクニ
http://www.oui-mikuni.co.jp/group/domain.html
軽井沢ならではの素材でドメイヌ・ドゥ・ミクニの料理コンセプトは地産池消。
軽井沢の近隣には野菜、豚、牛など、美味しい素材が豊富です。ダイレクトに、本来の香りを保ったまま調達できる食材をつかい、追分の美しい風景と調和した、スローなひとときを心から楽しめる料理をお届けしていきます。長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字小田井道下46-13

****** 今日の問題 ******