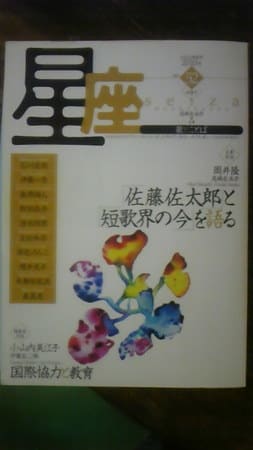「星座かまくら歌会」2016年10月 於)生涯学習センター
この歌会に出詠するようになってどのくらいだろう。参加するたびに学ぶこと、課題解決の暗示。こういうものが得られる。「星座α」の定例歌会も同様だ。「かまくら歌会」には熱心な会員は静岡から参加する。東京の23区以外からも都心を越えて参加する会員もいる。それだけ実りの多い歌会だ。
今日も着眼点がよい作品が多かった。作品のコアになるポエジー(詩情)が明確だ。回を追ってその傾向が強まっている。作者の独自性も出るようになった。
一首に付き参加者が自由に発言する。一通り終わったあとで尾崎左永子主筆が講評する。
論点はいつも同様だ。言い過ぎていないか、言い足らなくはないか、固定観念や固定的な情感に寄りかかっていないか、言葉を飾っていないか、語感は悪くないか、耳から聞いて読者に伝わるか、叙述に傾いていないか、印象は鮮明か、言葉遣いに無理はないか、固有名詞が生きているか。
ここで考えたことが一つあった。社会詠のありかただ。社会詠は社会に対する作者のスタンスが欠かせない。それがなければ「新聞の見出し」になったり、「事実報告」になる。社会と「われ」との関係性が問われる。叙景歌にしても心理詠にしても、素材と作者がどう向き合っているかが重要なファクターだ。
社会に対する個人のスタンスは、社会体制へのスタンスだ。社会の多数派に対する異議申し立てとも言える。そのスタンスはいくつかある。
体制に順応迎合するか、体制にしぶしぶ従うか、体制に異議申し立てをするか。このうち順応迎合は文学足りえない。なぜならそこには葛藤がないからだ。多数派の順応迎合することは葛藤を伴わない。自分の社会的地位が安泰だからだ。
体制にしぶしぶ従う場合、作品に葛藤があったばあいは文学足りえる。広津和郎の『風雨強かるべし』がそうだ。
体制に異議申し立てで人間が描けている場合、文学足りえる。小林多喜二の『蟹工船』がそうだ。あるシンポジウムで「安保法制賛成の立場からの短歌作品もありうる」と一人のパネラーが言った。だがこれはお話にならない。体制への迎合は葛藤を伴わない。
葛藤を伴わない文学はあり得ない。社会体制が変わってもそれは同様だ。社会と個人の葛藤を表現している限り文学足りえる。そう思うのである。