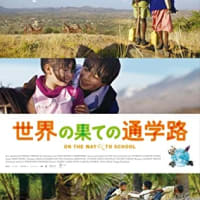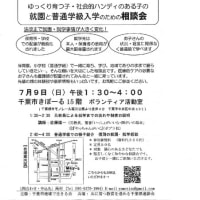先日、ある研修会で薬物依存に関するワークショップに参加しました。
その人は、誰も助けてくれる人がいなかったため、子どものころから20代前半まで様々な苦労をしていました。
もし子どものころに「助けてくれる人」がいたなら、その人はどんなふうに手をさしのべることができたのだろう?
どんなふうに声をかけることができたのだろう?
もし子どものころにそんな人に出会えるとしたら、どんなふうに手をかしてもらいたかったのだろう?
どんなふうに声をかけてほしかったのだろう?
そんなことを考え、感じる時間を過ごしました。
その途中で、「あ、これ、ワニなつ的にそのまま使えるんじゃないか」と思いました。いや、すぐにでもやってみたいと思いました。
先日、Tさんに「ワークショップ……」とタイトル案を書いたメモを渡したら、すぐに会場をとってくれました。
というわけで、はじめてのワークショップをやってみます。
「明日までにチラシをつくって」と言われて作ったチラシを以下に貼り付けます。
◇
《ワークショップ 共に育ち学ぶ世界》
普通学級での13年の暮らしをふり返る
・・・0歳~30歳の流れのなかで・・・
「支援」のために、教室を分けることは必要でしょうか。
「支援」のために、子どもを分けることは必要でしょうか。
インクルーシブな社会とは、共に育ち、共に学び、共に生きる、
すべての人を包み込めるおおらかな社会のことです。
ところが、「特別支援」が進めば進むほど、膨大な数の子どもが分けられ、インクルーシブとは正反対の子ども社会がつくられていきます。
共に生きる社会を目指すなら、子ども同士が共に育つ「いま」を支えあうことが、なにより大切です。
子どもの「いま共に」を支えることなしに、将来の「共に」は生まれません。
特別な支援はいらない。特別な生き方をさせたくはない。
障害のある子どもと共に生きる日々のなかで、私たちが大切にしてきたことはなにか。
普通学級の生活を通して、私たちは子どもたちの未来にどんな贈り物を届けたいのか。
そんなことをいっしょに考えるためのワークショップ開催します。
2015年2月8日(日) 午後1時半~4時半
場所:千葉市
参加費:無料 (※ 保育はありませんが、子ども連れ参加歓迎♪)
司会進行:佐藤陽一
話題提供:仲井眞由美
主催:千葉市地域で生きる会&生活と教育を考える会
後援:共に育つ教育を進める千葉県連絡会
コメント一覧

kawa

yo

kawa
最新の画像もっと見る
最近の「ワニなつ」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- ようこそ就園・就学相談会へ(517)
- 就学相談・いろはカルタ(60)
- 手をかすように知恵をかすこと(29)
- 0点でも高校へ(402)
- 手をかりるように知恵をかりること(60)
- 8才の子ども(162)
- 普通学級の介助の専門性(54)
- 医療的ケアと普通学級(92)
- ホームN通信(103)
- 石川憲彦(36)
- 特別支援教育からの転校・転籍(48)
- 分けられること(68)
- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)
- 膨大な量の観察学習(32)
- ≪通級≫を考えるために(15)
- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)
- この子がさびしくないように(86)
- こだわりの溶ける時間(58)
- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)
- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)
- 感情の流れをともに生きる(15)
- 自分を支える自分(15)
- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)
- 受けとめられ体験について(29)
- 関係の自立(28)
- 星になったhide(25)
- トム・キッドウッド(8)
- Halの冒険(56)
- 金曜日は「ものがたり」♪(15)
- 定員内入学拒否という差別(99)
- Niiといっしょ(23)
- フルインクル(45)
- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)
- ワニペディア(14)
- 新しい能力(28)
- みっけ(6)
- ワニなつ(351)
- 本のノート(59)
バックナンバー
人気記事