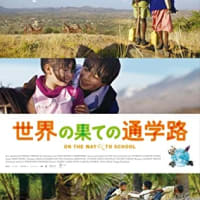「この子がさびしくないように」
それは、「年老いて認知症が深まり、自分のことさえ分からなくなってしまった母親がさびしくないように」と、同じことです。
「この子がさびしくないように」
娘が生まれるまえから、私はその答えを知りたくて、ずっと探していたように思います。
それは、「わたしがさびしくないように」と同じことでした。
「8歳のわたし、がさびしくないように」、その答えが分からないと、わたしは子どもに出会えないと、思っていました。
その答えを私に教えてくれたのは、知ちゃんであり、たっくんであり、朝子であり、康司であり、りさであり、石川先生の会で出会った子どもと親たちでした。
「この子がさびしくないように」
親だけでは、かなえられないこと。
それこそが、「この子がさびしくないように」の答えでした。
どんなにがんばっても、大人に、親に、友だちの代わりはできません。
「この子がさびしくないように」
親にできることは、この子に、たしかな「ここにいるわたし」を感じられるようにしてあげること。
「ここにいるわたし」の居場所を守ること。
「この子がさびしくないように」
「子どもはだれかと一緒のとき、一人になれる」 D・W・ウィニコット
だれかとは、自分をまるごと受けとめてくれる母親のこと。
その母親が見えなくても、いなくても大丈夫なのが、一人なれる「ここにいる私」。
この子が、自分の苦労もさびしさも、自分で受けとめて、自分で助けを求めて、自分で生きていけるように、親以外の人間と環境への信頼を育てること。
そのためには、親がひとりで、「この子がさびしくないように」側にいてはいけないということ。
「この子がさびしくないように」
虐待され、家を追われ、十代半ばで「一人」で生きていくことを迫られた子どもたちが、「さびしくないように」。
私がかなえたい、自立援助ホームの答えもまた同じでした。
だれよりもさびしい子ども時代を過ごしたかもしれない子ども。
「ここにいる私」を感じることができなかったかもしれない子ども。
それでも、「一人」で生きていけという、社会。
わたしにできることは、ただまるごと受けとめるために、自分で自分を受けとめること。
迷う自分、「おろおろする自分に耐えること」(※)、のようです。
※《親はこうした子どもの孤独な闘いをひたすら見守ること、つまり受けとめること。
そのためには親自身が自分を根気よく受けとめ続けることができなくてはならない。
すなわち自己を受けとめる力を強化することが不可欠である。
自己受けとめができないとき、子どもを受けとめることはできない。
具体的に言えば、
おろおろする自分に耐えること。》
「存在論的ひきこもり」論 芹沢俊介 雲母書房より
最新の画像もっと見る
最近の「関係の自立」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- ようこそ就園・就学相談会へ(517)
- 就学相談・いろはカルタ(60)
- 手をかすように知恵をかすこと(29)
- 0点でも高校へ(401)
- 手をかりるように知恵をかりること(60)
- 8才の子ども(162)
- 普通学級の介助の専門性(54)
- 医療的ケアと普通学級(92)
- ホームN通信(103)
- 石川憲彦(36)
- 特別支援教育からの転校・転籍(48)
- 分けられること(68)
- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)
- 膨大な量の観察学習(32)
- ≪通級≫を考えるために(15)
- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)
- この子がさびしくないように(86)
- こだわりの溶ける時間(58)
- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)
- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)
- 感情の流れをともに生きる(15)
- 自分を支える自分(15)
- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)
- 受けとめられ体験について(29)
- 関係の自立(28)
- 星になったhide(25)
- トム・キッドウッド(8)
- Halの冒険(56)
- 金曜日は「ものがたり」♪(15)
- 定員内入学拒否という差別(99)
- Niiといっしょ(23)
- フルインクル(45)
- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)
- ワニペディア(14)
- 新しい能力(28)
- みっけ(6)
- ワニなつ(351)
- 本のノート(59)
バックナンバー
人気記事