令和4年5月10日(火)
ウツギの花 : 空木の花、卯の花

ユキノシタ科の落葉低木、高さ1.5m前後
山野に自生し、生け垣などにも植えられる。



5月頃、白色5弁の小花が密に垂れ下がった様に咲く。

葉は互生し、長卵形で先が尖り縁に浅い鋸歯がある。
ウツギの名は四月に咲くため、また幹が空洞になって
いることから「空木」(ウツキ)という。
「打つ木」という説は、邪悪な土地の精霊を追い出すため
に、この木で地面を打つ風習が古くから在った事に起因す
ると云われている。


卯の花は万葉の昔から和歌に親しく詠まれて「垣根、雪、
月、郭公、神山、白河の関」などに多くの縁語が掲げられ
ている。
陰暦の四月を「卯月」と呼ぶのは、この花からきたという。

五月は二つの季節が行き交う時で、その区切りを示す様な
植物といわれる。
田舎者のようなこの花が新緑の世界に在って、ういういし
く点りだす。まさに「夏は来ぬ」の思いに胸が躍る。

童謡「夏は来ぬ」は、日本最古の和歌集「万葉集」の研究
者として著名な、国文学研究者で歌人の「佐々木信綱」が
明治4年29年(1896年)に詩を作り、小山作之助に
曲を依頼して出来た曲である。
旧仮名遣いで、中々理解出来ぬ詩をそのまま現代まで歌い
継がれている。(初夏の状景を歌う名曲である)
夏は来ぬ
作詞 : 佐々木 信綱、 作曲 : 小山作之助
卯の花の 匂ふ垣根に
時鳥(ほととぎす) 早も来なきて
忍音(しのびね)もらす 夏は来ぬ
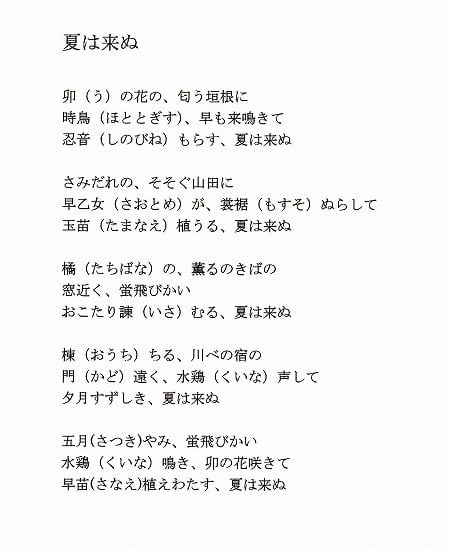
今日の1句(俳人の名句)

卯の花やけふは音なきわらは病み 与謝 蕪村




























































