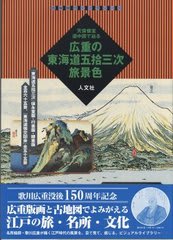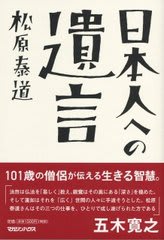先週の6月19日の東海道五十三次の一週間遅れの記事です。
ウオーキング専門ブログに書いた記事をそのまま紹介します。
●19日、朝6時28分の新大阪駅始発の新幹線で静岡へ、ビジネスマンばかりの車内でウオーキング姿は気が引けるのだが・・・静岡で東海道線に乗り換え、前回ゴールの由比駅に着いたのが8時56分。富士山が見えるようであれば、前回、見ることができなかったさった峠に行くことも想定していたが、目の前の太平洋もかすんでいたし、タクシーの運転手さんに聞いても、今日の天気では見えないだろうと言われ諦めたが、それでも、もしかして・・・もしかして、と駅のベンチで9時半まで待った、しかし、状況は変わらず断念してコースに入った。

駅前の通りは、ずばり「桜えび通り」、桜えび2匹の派手なアーチが出迎えてくれたが、そちらには行かないで山手にある車の通行量が激しい396号線をすすむ。

平バス停から元の道に戻り古い家並みの続く道をすすむ。「桜えび」と「しらす」の看板がやたらと目につく、海が近いので潮の香り、魚の匂いがする道が続く。さった峠からの富士山は諦めたが、今日のもう一つの目標、「桜えび」を食べること、しかし、この時間、開いている店などはない。

道を少し横道に入り坂上田村麻呂ゆかりの豊積神社へ寄った。和瀬川を渡るとこのあたりから宿場の名残のある光景が続く。驚いたのは、家々の屋根、その軒下が普通見慣れた住宅とはまったく違うこと。
「せがい造り」といって、軒先を長くして、それを支えるために腕木というものが付け足されている、さらにその軒先を雨から守るため「下り懸漁」というものが作られていて、いかにも重々しい重厚な造りになっているが、明治時代からの工夫らしい。ほとんどの家が同じ構造になっているのにびっくりした。

由比川を渡りしばらくすすむと左側に脇本陣羽根の屋、脇本陣徳田屋跡、つづいて加宿問屋場跡が続く。洋館づくりの清水銀行由比支店は明治の郵便局の跡だそうだが、なかなか美観の建物だ。
続いて長い黒壁と道路と壁との間に池のような水貯めがある由比本陣跡へ、由比本陣は、もともと由比城主が引き継いできたもので現在も八代目が健在しているそうだ。庭園は小堀遠州作といわれ、奥には、明治天皇が小休止された離れ座席の「御幸亭」が復元されている。この旧本陣内が由比本陣公園として整備され、その中心が「広重美術館」になっている。

桜えびの食事ができるまでこの美術館で過ごすことにしてゆっくりと見学をさせてもらった。
ここで広重の「東海道五拾三次旅景色」という大判A3サイズの分厚い写真集を2600円で購入。これは掘り出し物と喜んだが、この写真集にこのあと苦しめられることになろうとは思いもよらなかった。(次の日の日記で記述)
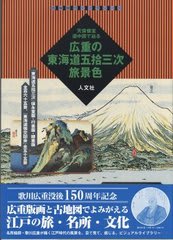


(本陣内の公園、正面が広重美術館)
11時になり、すぐ近くのおもしろ宿場館内のレストランで待望の桜えびの昼食をすることにした。二階のレストランは、正面が太平洋、右にさった峠、左手にこれからすすむ蒲原方面が一望できるすばらしい席を確保(まだ、お客さんは一組しか入っていなかった)。名物の桜えび御膳を注文したが、かきあげがおいしかった。生の桜えびの甘いのにもびっくり、わさび醤油で食べるとさらにおいしかった。この「桜えび」は、この駿河湾でしか捕れない深海のえびだそうで夜になるとプランクトンを食べるために浮上してくるのを捕るらしい。おいしかった◎◎。



(レストランから見えるさった峠と東海道本線)
食事と景色に満足して11時50分に早い午後のスタート、由井正雪の生家といわれる正雪紺屋(染物屋)を通りすぎると

「御七里役所跡」、はて? 初めて聞くことばだが、御七里役所とは、徳川家康の八男頼宣が紀州藩士となってできたもので、幕府の行動を監視するために紀州から江戸まで146里間、七里ごとの宿場に23ケ所つくった施設だという。

ここまで来るだけで、汗が噴き出すほどの蒸し暑さ・・・日陰のない通りは暑い。タオルを首に巻いて暑さしのぎ、水分補給を頻繁にするために汗ふきも忙しい。暑さで集中力がにぶってくるので、いつものことだが、一番怖いのが車!いくら気をつけても安全運転ができない命しらずの凶器が走ってくることを忘れないようにと自分に言い聞かせる。
396号線の石碑だけの由比一里塚をすぎ、由比城跡入り口前を通過、単調な古い街並みを蒲原宿をめざして歩く。神沢川橋を渡り東名高速道路の下を過ぎ、さらにまっすぐに延びた道をすすむ、汗が目に入り痛い!たぶん、30度をかなり超えているだろう、首筋が暑いというより痛い。
休憩したくてJR蒲原駅へ回り道して寄ってみた。向田川を過ぎると道路わきに154という数字だけの標識がたっていたがたぶん、東京からのキロ数だろう。
さらに396号線をどんどん歩いて行く。蒲原西木戸の標識がある角(西木戸・茄子屋の辻)を左折して裏道へ入る。ここから光景が一変して古い家並みが伸びている、蒲原宿のはじまりだ。
格子戸のきれいな増田家、醤油屋跡を整備した国登録の文化財「志田家住宅主屋」では説明役のご婦人からいろいろとこの地区のことも含めて話を聞いた。そこで東から来た人と遭遇した、お互いにエールを送って失礼する。すぐ向かいにやはり国登録の文化財「旧五十嵐歯科医院」古い洋館の建物はとくに目立っていた。


「御殿道」というかわった名前の石碑が目についた!どうやら徳川家康から家忠、家光までの休憩所があったところらしい。
宿場の雰囲気が残る蒲原は飽きない、高札場跡、旅籠跡を過ぎ山居沢川を渡り少し右へ入り込むと広重の「蒲原夜之雪」記念碑が小さな公園の一角にあった。その絵がそのまま碑になっている。「蒲原夜之雪」の絵は、広重の東海道の絵の中でも特に傑作といわれるもの。この碑は、「蒲原・夜之雪」が国際文通週間の記念切手に採用された記念に地元の有志が建立したそうだ。ここで休憩、クリームパンのおやつ。13時48分。

さらにすすむと途中でなにやらのぼりを持った一団が一台の車を従えて歩いてくる・・・・ヒロシマ・ナガサキへの平和行進と書かれている・・・どんな団体なのか見た限りではわからなかったが警官もひとり付いていた・・・そうだ、もうそういう時期だ、ヒロシマ県人にはよくわかる。
ナマコ壁の残る家の前を通り諏訪橋を渡り、「蒲原宿の東木戸」の碑の前を通過、ここが蒲原宿の東の入口、すぐ近くに立派な蒲原一里塚の碑があった。


ゆるやかな坂を上がると小川の向こう側で写真を撮っている男性がいたので声をかけた、東京から歩いてきているそうで、しばらく話がはずんだ。どんな地図を使っているのか見せたもらった、すごい、すべて、現在の地図に旧東海道を置き換えて作った手製のもの、これなら迷うことはないだろう。歩く前にじっくりと資料作りに一カ月、歩いて整理するのに一カ月かけているという。時間のある人はいい、自分のようなバタバタ、前日あわてて、明日歩く!といういい加減さでは表面的なものしか見ることができない・・・反省。とても気持ちのいい出会いだった、お元気で!

ここでコースから離れているが浄瑠璃姫の碑があるというので寄り道して行ってきた。暑い時、車の多い道は余計に暑く感ずる、顔の汗を手でなでたらざらざらしていた、ずっと車と一緒に歩いてきたので砂ホコリなのだろう、それにしてもすごい。
今度は急な坂道を上っていく・・・一番疲れる時間帯、下着を着替えたいのだが、適当な場所がない・・・汗で気持ちが悪い。坂道は、吉野山修行体験で教えてもらった
“さんげ さんげ 六根清浄” これを繰り返しながら歩調と呼吸を整えて歩く。
上りきって左へすすむと東名高速をまたぐ新坂橋へ、渡ると静岡市から富士川町となる。14時40分。周囲は東名をはさんで小高い山。ここから曲がりくねりながら集落へと下りて行く。

途中で道確認のために中年の女性に尋ねたら、間違っていなかったのに、次の曲がり角まで親切に歩いて教えてくれた。お気をつけて!このひとことがなによりうれしい。
これまで、どれだけ多くの人から、このことばをもらったことやら、人の温かさをしみじみと感ずるときだ。
新幹線のガード下を通り、どこまでも続くかだらだら道をもくもくとすすむ、間違いなく歩いているつもりだが、手持ちの地図にチェックポイントがない道が続くと確認のしょうがない、慎重に歩かないと迷ってしまうので、どうしても徐行になる、後半に迷ってしまうと足だけでなく、気分的に疲れとでダメージが大きいので人がいたら確認をすることにしている。

退屈すると大好きなミラー遊び!これも気分転換のお遊び!
通行量の多い道を歩いていたら、黄色い帽子をかぶった男性一人、女性二人の三人が信号横にいたので声をかけた。学校帰りの子供の安全管理をしている人たちだった。気さくな人達で話がはずんだ。こちらの地図を見て、これはわかりにくい!と言っていた。そりゃ無理、地図を逆方向に歩いているのだから・・・愉快なお父さんがこれから行く富士川まで、何度も何度も難しい個所を教えてくれた。でも、そんなに覚えられないよ、うれしかった。

東名高速道路をくぐり道は右に左に、とにかくわかりにくくてゆっくり歩いて確かめる他ない。
岩淵の一里塚から下校の子供たちの間にはさまれるように狭い道を車にひやひやしながらすすみ、やっと富士川に出た。16時4分になっていた。
ここから富士山がきれいに見えると聞いていたがまったく見えなくて、この日、とうとう富士山を見ることはできなかった。近くを歩いているはずなのに・・・。
新幹線の富士川鉄橋からの景色がしっかり頭の中にあるので、そのイメージを浮かべると富士山の位置はわかるのだが。

富士川橋を渡って水神社で休憩。境内には「富士山道」と「富士川渡船場跡」の碑が立っていて、ここが重要な場所であったことがわかる。
かって富士川は東海道一の急流として恐れられていて人々は水神を怒らせないように祈ってこの水神社を建立したと伝えられている。

ここからしばらくポイントのない道を歩き続ける、40分も歩いただろうか、身延線柚の木駅の近くへ来たが、一か所で一筋まちがってしまい元戻り、疲れてくると集中力がなくなってくる。庭先の咲いた黄色のユリがあまりにあざやかできれいだったので掃除をしていたお父さんに断って写真を撮らせてもらったら大変よろこんで話しかけてきた。この人も気をつけてと言って見送ってくれた、同年輩の人、通じるなあ・・・ここで予定時間より1時間以上も遅れてしまった、ゴールまで5キロもある。もう、うろうろとより寄り道しないように歩こうと思うが、きれいな花をみるとついつい撮ってしまう。
2キロほど歩いて新幹線富士駅へ通ずるところへ、さらにポイントの少ない道をすすむ、CASAが目印という大きな道の三叉路へきたがない、ない、たぶんレストランだと思うがない、おかしい、間違っているかもしれないともう一筋左の交差点へ行くがない、聞こうにも人がいない。ここはうろうろしないで人の来るのをじっと待つ、日暮れてきた。こんなとき、なんとなくさびしくなる。ここはお国を離れて何百里?自転車で通りかかった男性に地図をみてもらって現地を確認、親切に丁寧に教えてくれた。CASAはなくなってかっぱ寿司になっていた、これじゃ、いくら探してもみつからないぞ。
ここから吉原の街の中へすすんでいく、吉原は思っていた以上に大きな町だ、今日のゴールは岳南鉄道の「吉原本町駅」と決めている。
中心部の青葉通りを越えて小潤井川のところでおばさんに道を確認、途中にあるお寺の名前で聞いたら右側の道だという、?と、しかし自信をもってこちらで間違いないと言われたので行ってみたがやはり間違い、庭の花に水やりしていたお年寄りに聞いたらお寺違い!修正して、吉原の賑やかな商店街を通り、そのはずれにある岳南鉄道の「吉原本町駅」に18時20分ゴール、予定していた時間を1時間も遅れてしまった。午前中を由比で過ごしたこともあるが、事前準備もせずに出たとこ勝負で歩いたつけは大きかった。まあ、事故もなく歩けたのだからよしとしよう。

35,900歩 25.1キロ。
吉原本町駅から地図を頼りに予約していたホテルをさがして15分。やっとほんとのゴール。あー疲れた! (翌日の日記は近日中に)