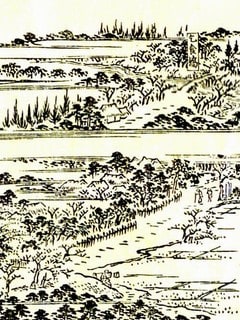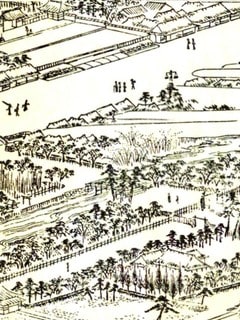下板橋駅を出て右に行く。この辺りにあったという田楽橋は既に姿を消している。一番目の角を右に入る道は区境になっていて少々気にはなるが、今回は予定通り二番目の角を右に入る。谷端川の上に造られた駐輪場に沿って進むと、昭和になって架けられた三の橋に出る。

その先には昭和に架けられた二の橋がある。この辺りから南側は谷戸地形になっていて、その下流域を雲雀谷戸、上流域を下り谷と呼んでいた。明治の地図を見ると谷戸は線路を越えて現・池袋六ツ又付近に達しているようである。この谷戸は江戸時代の池袋村絵図にも描かれているが、絵図によると水源は六ツ又より南にあり、その位置は、現・サンシャインシティ付近だったと思われる。また、この絵図によると、雑司ヶ谷道沿いにも水源があり、その位置は現・池袋の森の近くのようである。この谷戸からの流れは、本来なら谷端川本流に流れ込んでいた筈だが、池袋村絵図によると、西前橋で谷端川本流から分水され東に流れていた分水路に流入していた。この分水路は谷端川本流と平行して、本流の南側を東に流れたあと、明治通りの手前で谷端川本流に合流していたが、昭和4年の地図では、この分水路はすでに無く、谷戸からの流れは谷端川本流に直接流れ込むようになっている。

緑道を進むと一の橋が現れる。ここから先、谷端川は右に曲がり埼京線の板橋駅の下を潜っている。ガードを出て直ぐの角を右に行くのが谷端川の跡で、この道を歩いて行くと、左側に桜並木が見えてくる。桜の季節であれば、ここを左に入り谷端通りに出て桜並木を歩き、南谷端公園の角で右に桜並木を下って谷端川跡の道に戻るのが良いのだが、今回は、ひたすら谷端川跡の道を歩く。道は程なく左に曲がっていくが、ここには地名に由来する谷端橋が架かっていたという。ここを過ぎて先に進むと明治通りに出る。その手前に旧鎌倉街道跡の道が残っているが、ここにあった橋が鎌倉橋で、江戸時代にもここには橋が架かっていた。

明治通りを渡って先に進む。その先の信号の辺りには上之橋があり、山手線の線路近くからの流れと、薬学者の丹羽藤吉郎邸(後に山口邸)にあった瓢箪形の池の水が合わさり音を立てて谷端川に流れ込んでいたという。谷端川の説明板を左に見て先に進み、中之橋があった四つ角と、宮仲橋があった四つ角を過ぎると、北大塚三の交差点に出る。谷端川は交差点の南側を流れていて葮山橋が架かっていたというが、今回はそちらの道をとらず都道436号を進む。先に進むと空蝉橋下交差点に出るが、その手前に左手から巣鴨新田からくる道があり、蛇子橋(真法橋または寂法橋)で谷端川を越えていた。嘉永7年の図(御府内場末往還其外沿革図書)には、この橋の近くで合流する流れも記されているが、大正大学付近を源流とし旧中山道に沿って流れたあと、庚申塚の手前で旧中山道を横切って南流する小川が合流していたようである。さらに進めば大塚駅の北口に出る。王子電車の時代には、鉄橋で谷端川を越えていたが、今は都電が暗渠の上の道路を渡っている。
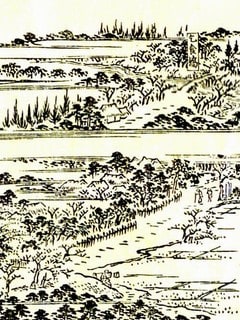
都電の軌道を渡って先にいくと折戸通りで、昔は藤橋(富士橋。乞食橋)で谷端川を渡っていた。現・春日通りから分かれて藤橋を渡り、折戸通りで旧中山道の庚申塚に出る王子道は、江戸時代によく利用されたルートで、上の図は、十羅刹女堂(天祖神社)から乞食橋(藤橋)に向かう道を描いたものである。ところで、享和元年の巣鴨村絵図によると、鎌倉橋と藤橋の間に四カ所の橋が記されている。新編武蔵風土記稿に記載されている橋のうち、上橋は上之橋に、寂法橋は蛇子橋に該当すると思われ、残りの2カ所のうち1カ所は位置的に中之橋のように思えるが、あと1カ所は判然としない。

谷端川には、西側から現・天祖神社付近の湧水池からの流れが、東側から現・天満宮付近の湧水池からの流れが合流しているので、藤橋から先は谷端川の水量が増えていたと思われる。JRのガードを潜り、すぐ左へ下っていく道は大塚三業地の道に相当し、花街らしく入口には紅色の欄干がある姿見橋があり、その先には見返橋があったという。道は程なく右へ曲がって行くが、ここに地名由来の熊野窪橋(熊野橋)があり、その先には左側に入る東福寺参道に東福寺橋があった。この二カ所の橋は巣鴨村絵図に記されている橋である。巣鴨小を過ぎて谷端川跡の道を先に進むと、豊島区と文京区の区境に出る。明治42年の地図には、東福寺橋からここまでの間に橋の記載は無いが、昭和4年の巣鴨町西巣鴨町全図を見ると、区境に架けられた宮原橋のほか、東福寺橋との間に幾つかの橋が記載されている。

宮原橋を過ぎて文京区に入り、猫貍橋を目指して谷端川跡の道を歩く。道は氷川下児童遊園に沿って右に曲がり都道に出るが、都道から左に児童遊園の南東沿いの道に入る。この道を上がって行けば砂利場坂になるが、谷端川は児童遊園を横切り砂利場坂の下を流れていた。新編武蔵風土記稿によると、護国寺造営の際に砂利取り場として使用された谷端川沿いの土地が荒廃したままになっていたのを、享保年間に願い出て開墾し新田としたとあり、小石川(谷端川)に架かる砂利場橋という名の土橋を記している。安永江戸大絵図にも、ここに橋が記されているが、橋は享保年間以前に架けられていたと思われる。一方、砂利場坂の下にあった橋は、一木橋(いちもく橋。上猫貍橋、一本橋)と言う名の木橋であったとも伝えられている。ここからは憶測になるが、砂利場橋という土橋が壊れたあと、丸太の一本橋が架けられ、一木橋と呼ばれるようになったのかも知れない。児童遊園の南東沿いの道に入ってすぐ右に行く細い道が谷端川の跡で、この道を進んでいき、小公園になっている場所を上がると不忍通りに出る。猫貍橋はこの辺りにあったというが、明治の初め頃までは江戸名所図会の挿絵のような農村風景が多少なりとも残っていたと思われる。

不忍通りに出て右手の千石三の交差点を渡り、不忍通りを左に行くと大正時代に架けられた猫貍橋(猫又橋、猫股橋、根子股橋、ねこまた橋)の袖石と説明板が設置されている。この橋には、狸が人を騙すと言う伝説があったが、江戸名所図会では木の根っこの又を橋の名の由来とする説を紹介している。安永江戸大絵図にも、ここに橋が記されているが、当初は木橋だったのが、挿絵の描かれた頃には石橋になっていたという事かも知れない。説明板の右側の細い道が谷端川の跡で、この道を進んで行くと、右斜め方向に都道436号(通称千川通り)に出る道があり、谷端川はここで千川通りを横切っている。明治時代、ここに道路が開通した際、架けられたのが氷川橋である。

千川通りには出ずに細い道を先に進むと、左手に簸川神社があり、谷端川を昭和9年に暗渠化したことを記念する千川改修記念碑が建っている。谷端川は下流では小石川と称していたとされているが、地名と紛らわしいので使われなかったらしく、東都小石川絵図では小石川大下水と記している。谷端川は千川上水長崎村分水でもあり、略して千川分水とも呼ばれていたので、千川の名を使うようになったのかも知れない。明治になってからは、千川の名が定着したようで、小石川谷と称すべきところを千川谷と呼んでいる。簸川神社から近い小石川植物園の中をちょっと覗いてから右に行き、交差点を渡って窪町東公園に行く。谷端川は窪町東公園を横切って湯立坂の下を流れていた。

新編武蔵風土記稿ではここに架かる橋の名を氷川橋としているが、御府内備考や江戸名所図会では祇園橋としている。この橋は安永の江戸大絵図にも記されている古くからの橋で、当初は土橋で後に木橋になったともいう。橋の名も変わったかも知れない。千川通りを左側の歩道に移って先に進むと、右側から桜並木の播磨坂が下ってくる。この交差点の辺りで、谷端川に架かっていた橋が久堅橋である。上水北小日向小石川辺絵図には、祇園橋の次の橋として、善仁寺と宗慶寺の間の道から大雲寺と新福寺の間の道に出る、橋戸町と戸崎町の橋が記されている。この橋は、安永の江戸大絵図にも載っている古くからの橋で、御府内備考ではこの橋を石橋と記しているが、無名の橋だったらしく、明治になって成立した久堅町の名に因んで久堅橋の名が与えられ、明治16年の東京図測量原図でも久堅橋と記している。明治40年の小石川区全図では祇園橋と久堅橋の間に橋は無いが、昭和6年の小石川区地籍図からすると、祇園橋の下流に幾つもの橋が新たに架けられていたようである。
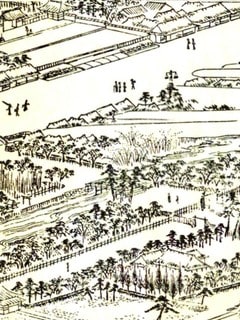
久堅橋から先は明治40年の小石川区全図を参考に、植物園前の交差点から千川通りを先に進む。次の信号の少し先を左に入る道は御殿坂近くに出る道で、途中の谷端川には明治時代に橋が架けられていたが、橋の名は分からない。先に進んで念速寺を過ぎ、その先の交差点に出る。江戸時代、ここを左に入ったところに祥雲寺、右側には無量院があった。上の図は江戸名所図会の挿絵の部分図で、上側が祥雲寺と門前町、下側が無量院で、中ほどには谷端川に架かる橋が描かれている。祥雲寺は後に池袋に移ったが、移転先の祥雲寺の坂の下にも谷端川が流れていた。一方、無量院は明治になって廃寺になっている。無量院の前に架かっていた橋は、明治16年の東京図測量原図にも記されているが、橋の名は記されていない。小石川区全図から、明治40年までには、この橋の少し上流にも橋が架けられていた筈である。この橋は、戸崎橋と呼ばれていたかも知れない。なお、戸崎町は念速寺近くから大雲寺に至る町で、途中の白山裏の通りには石橋があったようである。

先に進むと右側に八千代町児童遊園がある。この付近には先手組の組屋敷の橋があったが、明治になって組屋敷跡が掃除町に組み込まれたため、この橋は掃除橋の名で残ることになった。その先、柳町小前の交差点付近には、柳町から掃除町に渡る橋があったが、地元の意向もあってか、東京図測量原図ではこの橋を千川橋と記している。この先、小石川三の交差点から右に折れて先に進むが、谷端川は道路に沿って南に流れていた。次の交差点に架かる橋は伝通院の裏手に出る橋であり、柳町に渡る橋でもあったが、東京図測量原図では、この橋を裏柳橋と記している。さらに先に進むと源覚寺に渡る橋があり、東都小石川絵図では源覚寺橋としているが、明治時代に架かっていた橋の柱に嫁入橋とあったため、東京図測量原図でも嫁入橋と記している。この橋については、名主家の嫁入りを祝って橋を新しくしたという話も伝わっている。源覚寺橋から先にも幾つかの橋があるが、そのうちの一つは丸太橋という橋で、もともとは丸太の一本橋だったようだが、明治時代には石橋に変えられていた。富坂の下にも橋はあったが、江戸時代の坂下は今より南に位置していたため、富坂橋の位置は異なっている。富坂橋から先、谷端川は水戸家の屋敷内(明治以降は砲兵工廠内)を通り、市兵衛河岸で神田川に合流していた。河岸に架かる橋は仙台橋で、谷端川最下流の橋になる。
<参考資料>
「旧谷端川の橋の跡を探る」「千川上水関係資料Ⅰ」「豊島区の湧き水をたずねて」「新編武蔵風土記稿」「御府内備考」「御府内場末往還其外沿革図書」「いたばしの河川」「東京の橋」「江戸名所図会」「東京名所図会・小石川区之部」「巣鴨乃むかし1」「豊島区地域地図集」「豊島区史地図編」「東京図測量原図」その他江戸切絵図など各種地図など。