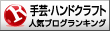『紅花は寒い時に染める』と言います。
お湯を使わず冷たい水で揉みだすので、冷たいことこの上ないのに、
寒い時でないと染め上がりがよくないのです。
もっと寒い時期に染めたかったんですが、娘の看病があったり、なんだかんだと忙しかったです。
まだ寒い! と思って、今季最後の機会になると思って染めに入りましたが・・・
見事に失敗しました。
そんな失敗作をアップしてどうする と躊躇しながらも、これはこれで色の出具合はいいのではないか、
と躊躇しながらも、これはこれで色の出具合はいいのではないか、
つまり、紅花の紅色は出なかったけど、色はいいのでアップしてしまえ
そんな乱暴なお話です。
紅花 560gあります。 これを染めます。

1日中冷水で浸けおきます。
紅花は黄色と紅色の2色染めることができます。
最初の揉みだした色で黄色を染めることができ、残った紅花で紅色を染めます。
というか、黄色を出さなければ、紅色を染める染め液が出せないのです。
というわけで下が黄色を染める黄水です。2度揉んで出した色です。

揉んで絞った紅花をさらに別の水で揉みだし、水を変えて4度揉みだし
出た染め液が下です。

明らかに色が赤くなっています。
染める糸たちが精練されて染められるのを待っています。

※精練(せいれん)というのは糸の汚れや脂を落とすための染めの作業です。
ぬるめのお湯に糸を入れ沸騰したら火を止め20分おいてよく洗います。
さて、最初は黄水で黄色を染めますが、これは真綿糸巻きスラブ糸1/6 106g 635m 1綛を染めます。
① 精練した糸をミョウバンで媒染します。これは色落ちを防ぐためです。
黄水は熱を加えても色素が壊れないので、ミョウバン媒染したあと洗った糸を
黄水染め液に入れて火にかけ、沸騰したら火を止めて 翌朝まで浸しおきます。
残り、平巻糸1/6 52g 317m 3綛、 真綿糸巻きスラブ糸1/6 1綛、
絹紡太カベ糸 106g 2540m 1綛 を染めます。
紅色水は熱を加えると色素が壊れてしまうので、冷水のまま使います。
① 紅色水に炭酸カリウム10gを入れて1時間おきます。(炭酸カリウムが溶け込むまで)
炭酸カリウムを使うのは染め液をアルカリ抽出するためです。
② その液に今度はクエン酸を入れてリトマス試験紙でphを測ります。
ph 6 になるように、そためにクエン酸を加え続け、けっきょく 19gのクエン酸を使いました。
そこに精練して洗った糸を浸けこみ、翌朝までおきます。
③ 翌朝、酢酸100㏄を水5リットルに溶かして、紅色水に染めて洗った糸を浸け込んで10分間。
洗って干します。
洗って干されるところです。左が黄水で染めた糸。あとは紅色水で染めた糸です。

ここで、黄水で染めた糸ははいいのですが、
紅色とはとんでもなく違う色だということにお気づきですね
タッハハ、もう笑うしかないのです。
バットの上に降ろしてみる
あまりにも悲しいので写した写真の明るさを補正してみます
このほうが、実際の色に近いです(言い訳ですが)
紅色とは似ても似つかない色ですが、冷静に考えてみれば、こんな”やまぶき色”を草木染めで出せるなんて
あり得ないのです。
どうにもこうにも 言い訳とやせ我慢の言辞を弄しているとしか思えませんが、
なぁに、あとは織りの技術で 素晴らしく織り上げるんだと開き直りの今です。
気温かなぁ、いえいえ 稚拙な技術かなぁ、
あまりにも前の紅花染めとは違いすぎる結果に気落ちしておりますデス。
















 )
)