今回の記事では、山荘のある別荘地(八ヶ岳中央高原三井の森)周辺をご案内する。
先週から今週にかけて我々が山荘に滞在していた間、若い別荘オーナー予備軍が続々と見学のため別荘地内に入って来た。今も別荘地及び中古別荘の価格は暴落中。きっとさらに下がるだろう。さあ、買いなはれ! 原村の別荘地に行くなら、中央道の最寄りのインターチェンジは諏訪南ICだ。皆さん「諏訪南」ですよ。「諏訪」ではないからね。間違える人が多いらしいので一応注意を喚起。諏訪南ICを下車したらズームラインをまっすぐ東へ(八ヶ岳のある方角)向かって上がる。

原村は全体的に標高が高い。例えば原村では「低地」にあたる原村役場のあたりでもすでに標高は1000mを超える。しかしそこでもまだ森はない。上の画像はズームラインを上がった深山交差点。「みやま」と読んでね。「ふかやま」「しんざん」ではありませんからね。この深山交差点あたりで標高が1100mくらいだが、ここまでは木々がまったくない。ここから先の方で(地図では東へ)やっと森が始まり、木陰が多くなり、グッと涼しくなるのだ。この交差点でズームラインはエコーラインと交差する。このズームラインが今の形になったのは10年ほど前で、エコーラインがこの形になったのはさらにそのずっと後である。これにより原村の森のうち、標高が低い部分の開発がかなり進んでしまうこととなった。
下の写真で道路より右手(地図では東、標高が高い方)には森があるが、左手(地図では西、標高が低い方)にはそれがない。いくら標高が高くても、当然ながらこの道路から下は、木陰もないので夏の昼間は暑い。

これが概念的な地図である。原村の北は茅野、南は富士見。原村においてはエコーラインは標高1100m前後、鉢巻道路は1300m~1400mあたりだ。非常に大雑把に区切れば、エコーラインと鉢巻道路の間の森は、集落からあまり離れないことを望む別荘族と新規参入の永住者向きの土地。鉢巻道路より上は純然たる別荘地風で、喧騒から隔離されたイメージを望む人向きの土地である。我が山荘がある八ヶ岳中央高原三井の森は、原村でも鉢巻道路より上で、標高1400m~1600mあたりに位置する。

(株)三井の森が会員に配布する季刊誌最新号ではこの別荘地の分譲開始以来の変化を特集していたが、そのひとつに「自動車の走行音がうるさくなった」というのがあった。中央道の交通量の増加もあるが、高速道路並みにクルマが飛ばすエコーラインやズームラインの完成が影響を与えている。
原村を目指すクルマだけでなく、東京方面から来て蓼科方面に抜けるクルマも、そのうちの一定割合が、中央道をわざわざ遠い諏訪ICまで行くことをせず、手前の諏訪南ICで下りて、このエコーラインを北上するようになった。しかも幹線道路が整備されるにつれ、エコーラインと鉢巻道路の間の標高1100~1350mあたりの森林が伐採され、新規別荘地の分譲が続いたことが、クルマの音を筒抜けにしている。
鉢巻道路より下の別荘地になると、周囲の幹線道路の音は、以前と比較すると、かなり直接的にかつ頻繁に聞こえるようになった。人は静かになるほど、その環境に馴れるほど、わずかの音でも敏感になってしまうものだ。ところが逆に鉢巻道路は、その下に使いやすいエコーラインが並行して開発されたことで、その分交通量は減っていると言われる。
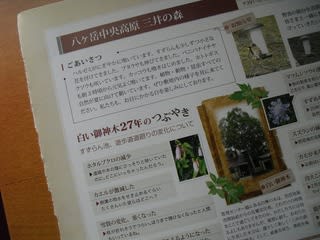
阿弥陀岳(八ヶ岳連峰の主峰のひとつ)を正面に見ながらズームラインを上がる(東へ)ところだ。森の中、両側にはラベンダーがずっと植えられている。これを図々しくも抜いて持って帰る人々がいるらしい。そういうセコイことは止めましょう。

ズームラインの突き当りを左折すると、これが鉢巻道路。八ヶ岳山麓をグルッと巻くように設置された道路だ。甲州の北杜市側にある太平交差点を過ぎて信州側に入ると、信号もないまま富士見から原を経由して茅野の美濃戸まで行ける、景色が見事な道路だが、それに見とれ、ぶっ飛ばしていると急に鹿が現われるので危険。事故は多く、鹿も死ぬがクルマも破損する。廃車になった例も多数。

八ヶ岳中央高原三井の森の入口は鉢巻道路から上がってスグの所にある。この看板が立っているのが別荘地の管理センター前で、そこが別荘地だ。管理センターの従業員の皆さんはよく働く。雑草刈り、倒木の処理、道路の補修、ゴミ処理、冬場の除雪、別荘地の警備としての巡回、建物や駐車スペースの管理。その他いろいろ。

ここから上が全部八ヶ岳中央高原三井の森別荘地。冒頭述べたように只今価格下落中。ちょっと高めのクルマ1台分の購入費用で買える中古別荘をあなたもいかが? クルマを買うより楽しいことも多いが、意外とメンテや税金や光熱費や管理費にカネがかかるので注意。それはクルマも同じようなものだけど。

阿弥陀岳を真東に見ながら、登る。別荘地が広がる。最上部はここ。原村内では最高標高にある交差点。交差点とは言え、平均的交通量は1時間にクルマ2台、ヒト3人くらいか。

こういう親切な看板があるのに、さらに上へ上がろうとするクルマを見かける。ここで終わりですから、これ以上進むのは止めましょう。上がっても、スグ先でUターンするのに苦労するだけ。ここから先は阿弥陀岳山頂までタダの山道。クルマは無理。

別荘地内では蓼科山が真北に見える。

管理の行き届いたお宅。見習わないと。

いつの間にか大きく太く育った我が敷地内のカエデ。11年前にはひょろひょろした木だったのに。記憶が曖昧だが、確か購入価格は4,000円だ。

ここも気候は徐々に変化しているが、夏の夕立ちは以前と変わらずよくある。面白いのは、雑音が少なく見通しがきくため、雨の降り始めが認識しやすいことだ。雨がやって来る方向もわかることがある。ザーっと来る雨は気持ちが良い。

雷もゴロゴロ。毎日のように鳴る。シラカバも濡れる。

通年利用を前提にしているから、冬は除雪サービスも頻繁に行われるし、かつ寒冷地なため、相当深く念入りな舗装工事が行われている。交通量もないのに幹線はアスファルトの2車線で、それをやってしまうと、今度は雨水の処理もきちんと行わねばならない。側溝も整備されていて、流量の調整も行われる。

雨に打たれる木製の階段。防腐塗料(シッケンズ)を毎年塗り重ねてある。11年、何事もなく今もしっかり。

雨の時は草刈作業もストップして読書。矢作弘著「都市縮小」の時代を読む。産業構造の変化、人々の考え方の変化により、アメリカでもドイツでも多くの古い都市は衰退、縮小している。空き家が増えることは景観保全からも犯罪防止の意味からも問題があるとして、少なくなった住宅をより小さな地域に集約して、それ以外の元住宅地あるいは荒廃した都市部を緑地や森林に戻して街をより小さくより美しく復活させた事例を紹介している。これにより人類史上稀なことに、環境も大幅に改善する。「立派でポジティブな縮小」である。
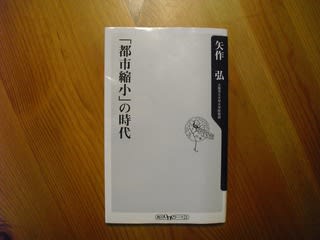
読んでいてドキッとする。自宅と別荘という家を2つ持つこと。環境的に、犯罪防止的にあまり褒められたことではない。「いや、私は頻繁に2つの家を使い、それに必要な税も納めているし、美しく保つよう努力を怠っていない」と言い訳したところで、自分の体が二つに割れるわけではない。2軒のうちどちらかの家にいる間はもう一方の家を必ず不在にしている。2軒の家のうち常にどちらかが空き家となっていて、その「不在時間」を合計すれば必ず毎年365日あるはずだ。2軒の家の近隣に対し、合計でそれだけのネガティブな影響をを与えている事実は変わらない。
しかもここは、人口が世界で最も急激に減少し始めた日本であり、そこら中で深刻な過疎や地方の街の衰退が見られる。ところが一方で別荘地が開発され、別荘が建ち、その大半が実際のところ開発後スグに、あるいは長くてもせいぜい10数年で多くが見捨てられる。国土全体をマクロ的に見るとまったく矛盾であり、少なくとも環境的には大きな損失である。しかも日本では上記のような開発の逆行を伴う「賢い縮小」は起こらない。廃墟の街、廃墟の別荘地が残るだけである。

などと考え込みつつ、別荘地の中を歩き回る。
更地に新たな別荘が建つ。長い間更地だったところだから、別荘の建築は近隣からも歓迎されよう。

我が別荘地に隣接するのが四季の森こけもも平。アルピコ・グループの開発したところだ。分譲開始から10数年経ったけれど、未だに空き地だらけ。茶々之介君もよく見学している。開発された以上は、うまく利用されればよいのにと思う。皆さん、山荘を建ててみませんか?

広い土地。冷涼な気候の土地。清潔感溢れる分譲地。こけもも平は別天地(私は別にアルピコ・グループの回しモノじゃないけれど)。皆さんいかがでしょう? 至れり尽くせりの広いアスファルト2車線道路完備。管理体制はばっちり。
地図では、厳密にはこのこけもも平は原村ではなく、ギリギリ茅野市のエリアに入るように見える。しかし水道は原村がまとめて面倒を見ているらしい。推測だが、固定資産税は茅野市に払うのだろうなぁ。ゴミはどちらの自治体の担当なのか。

昔から販売中。今も販売中。是非お仲間に。

先週から今週にかけて我々が山荘に滞在していた間、若い別荘オーナー予備軍が続々と見学のため別荘地内に入って来た。今も別荘地及び中古別荘の価格は暴落中。きっとさらに下がるだろう。さあ、買いなはれ! 原村の別荘地に行くなら、中央道の最寄りのインターチェンジは諏訪南ICだ。皆さん「諏訪南」ですよ。「諏訪」ではないからね。間違える人が多いらしいので一応注意を喚起。諏訪南ICを下車したらズームラインをまっすぐ東へ(八ヶ岳のある方角)向かって上がる。

原村は全体的に標高が高い。例えば原村では「低地」にあたる原村役場のあたりでもすでに標高は1000mを超える。しかしそこでもまだ森はない。上の画像はズームラインを上がった深山交差点。「みやま」と読んでね。「ふかやま」「しんざん」ではありませんからね。この深山交差点あたりで標高が1100mくらいだが、ここまでは木々がまったくない。ここから先の方で(地図では東へ)やっと森が始まり、木陰が多くなり、グッと涼しくなるのだ。この交差点でズームラインはエコーラインと交差する。このズームラインが今の形になったのは10年ほど前で、エコーラインがこの形になったのはさらにそのずっと後である。これにより原村の森のうち、標高が低い部分の開発がかなり進んでしまうこととなった。
下の写真で道路より右手(地図では東、標高が高い方)には森があるが、左手(地図では西、標高が低い方)にはそれがない。いくら標高が高くても、当然ながらこの道路から下は、木陰もないので夏の昼間は暑い。

これが概念的な地図である。原村の北は茅野、南は富士見。原村においてはエコーラインは標高1100m前後、鉢巻道路は1300m~1400mあたりだ。非常に大雑把に区切れば、エコーラインと鉢巻道路の間の森は、集落からあまり離れないことを望む別荘族と新規参入の永住者向きの土地。鉢巻道路より上は純然たる別荘地風で、喧騒から隔離されたイメージを望む人向きの土地である。我が山荘がある八ヶ岳中央高原三井の森は、原村でも鉢巻道路より上で、標高1400m~1600mあたりに位置する。

(株)三井の森が会員に配布する季刊誌最新号ではこの別荘地の分譲開始以来の変化を特集していたが、そのひとつに「自動車の走行音がうるさくなった」というのがあった。中央道の交通量の増加もあるが、高速道路並みにクルマが飛ばすエコーラインやズームラインの完成が影響を与えている。
原村を目指すクルマだけでなく、東京方面から来て蓼科方面に抜けるクルマも、そのうちの一定割合が、中央道をわざわざ遠い諏訪ICまで行くことをせず、手前の諏訪南ICで下りて、このエコーラインを北上するようになった。しかも幹線道路が整備されるにつれ、エコーラインと鉢巻道路の間の標高1100~1350mあたりの森林が伐採され、新規別荘地の分譲が続いたことが、クルマの音を筒抜けにしている。
鉢巻道路より下の別荘地になると、周囲の幹線道路の音は、以前と比較すると、かなり直接的にかつ頻繁に聞こえるようになった。人は静かになるほど、その環境に馴れるほど、わずかの音でも敏感になってしまうものだ。ところが逆に鉢巻道路は、その下に使いやすいエコーラインが並行して開発されたことで、その分交通量は減っていると言われる。
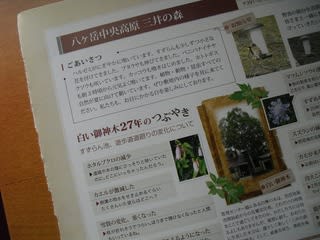
阿弥陀岳(八ヶ岳連峰の主峰のひとつ)を正面に見ながらズームラインを上がる(東へ)ところだ。森の中、両側にはラベンダーがずっと植えられている。これを図々しくも抜いて持って帰る人々がいるらしい。そういうセコイことは止めましょう。

ズームラインの突き当りを左折すると、これが鉢巻道路。八ヶ岳山麓をグルッと巻くように設置された道路だ。甲州の北杜市側にある太平交差点を過ぎて信州側に入ると、信号もないまま富士見から原を経由して茅野の美濃戸まで行ける、景色が見事な道路だが、それに見とれ、ぶっ飛ばしていると急に鹿が現われるので危険。事故は多く、鹿も死ぬがクルマも破損する。廃車になった例も多数。

八ヶ岳中央高原三井の森の入口は鉢巻道路から上がってスグの所にある。この看板が立っているのが別荘地の管理センター前で、そこが別荘地だ。管理センターの従業員の皆さんはよく働く。雑草刈り、倒木の処理、道路の補修、ゴミ処理、冬場の除雪、別荘地の警備としての巡回、建物や駐車スペースの管理。その他いろいろ。

ここから上が全部八ヶ岳中央高原三井の森別荘地。冒頭述べたように只今価格下落中。ちょっと高めのクルマ1台分の購入費用で買える中古別荘をあなたもいかが? クルマを買うより楽しいことも多いが、意外とメンテや税金や光熱費や管理費にカネがかかるので注意。それはクルマも同じようなものだけど。

阿弥陀岳を真東に見ながら、登る。別荘地が広がる。最上部はここ。原村内では最高標高にある交差点。交差点とは言え、平均的交通量は1時間にクルマ2台、ヒト3人くらいか。

こういう親切な看板があるのに、さらに上へ上がろうとするクルマを見かける。ここで終わりですから、これ以上進むのは止めましょう。上がっても、スグ先でUターンするのに苦労するだけ。ここから先は阿弥陀岳山頂までタダの山道。クルマは無理。

別荘地内では蓼科山が真北に見える。

管理の行き届いたお宅。見習わないと。

いつの間にか大きく太く育った我が敷地内のカエデ。11年前にはひょろひょろした木だったのに。記憶が曖昧だが、確か購入価格は4,000円だ。

ここも気候は徐々に変化しているが、夏の夕立ちは以前と変わらずよくある。面白いのは、雑音が少なく見通しがきくため、雨の降り始めが認識しやすいことだ。雨がやって来る方向もわかることがある。ザーっと来る雨は気持ちが良い。

雷もゴロゴロ。毎日のように鳴る。シラカバも濡れる。

通年利用を前提にしているから、冬は除雪サービスも頻繁に行われるし、かつ寒冷地なため、相当深く念入りな舗装工事が行われている。交通量もないのに幹線はアスファルトの2車線で、それをやってしまうと、今度は雨水の処理もきちんと行わねばならない。側溝も整備されていて、流量の調整も行われる。

雨に打たれる木製の階段。防腐塗料(シッケンズ)を毎年塗り重ねてある。11年、何事もなく今もしっかり。

雨の時は草刈作業もストップして読書。矢作弘著「都市縮小」の時代を読む。産業構造の変化、人々の考え方の変化により、アメリカでもドイツでも多くの古い都市は衰退、縮小している。空き家が増えることは景観保全からも犯罪防止の意味からも問題があるとして、少なくなった住宅をより小さな地域に集約して、それ以外の元住宅地あるいは荒廃した都市部を緑地や森林に戻して街をより小さくより美しく復活させた事例を紹介している。これにより人類史上稀なことに、環境も大幅に改善する。「立派でポジティブな縮小」である。
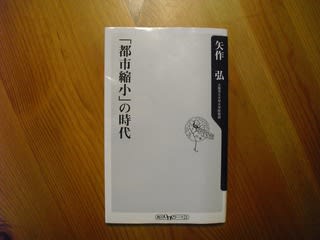
読んでいてドキッとする。自宅と別荘という家を2つ持つこと。環境的に、犯罪防止的にあまり褒められたことではない。「いや、私は頻繁に2つの家を使い、それに必要な税も納めているし、美しく保つよう努力を怠っていない」と言い訳したところで、自分の体が二つに割れるわけではない。2軒のうちどちらかの家にいる間はもう一方の家を必ず不在にしている。2軒の家のうち常にどちらかが空き家となっていて、その「不在時間」を合計すれば必ず毎年365日あるはずだ。2軒の家の近隣に対し、合計でそれだけのネガティブな影響をを与えている事実は変わらない。
しかもここは、人口が世界で最も急激に減少し始めた日本であり、そこら中で深刻な過疎や地方の街の衰退が見られる。ところが一方で別荘地が開発され、別荘が建ち、その大半が実際のところ開発後スグに、あるいは長くてもせいぜい10数年で多くが見捨てられる。国土全体をマクロ的に見るとまったく矛盾であり、少なくとも環境的には大きな損失である。しかも日本では上記のような開発の逆行を伴う「賢い縮小」は起こらない。廃墟の街、廃墟の別荘地が残るだけである。

などと考え込みつつ、別荘地の中を歩き回る。
更地に新たな別荘が建つ。長い間更地だったところだから、別荘の建築は近隣からも歓迎されよう。

我が別荘地に隣接するのが四季の森こけもも平。アルピコ・グループの開発したところだ。分譲開始から10数年経ったけれど、未だに空き地だらけ。茶々之介君もよく見学している。開発された以上は、うまく利用されればよいのにと思う。皆さん、山荘を建ててみませんか?

広い土地。冷涼な気候の土地。清潔感溢れる分譲地。こけもも平は別天地(私は別にアルピコ・グループの回しモノじゃないけれど)。皆さんいかがでしょう? 至れり尽くせりの広いアスファルト2車線道路完備。管理体制はばっちり。
地図では、厳密にはこのこけもも平は原村ではなく、ギリギリ茅野市のエリアに入るように見える。しかし水道は原村がまとめて面倒を見ているらしい。推測だが、固定資産税は茅野市に払うのだろうなぁ。ゴミはどちらの自治体の担当なのか。

昔から販売中。今も販売中。是非お仲間に。

















