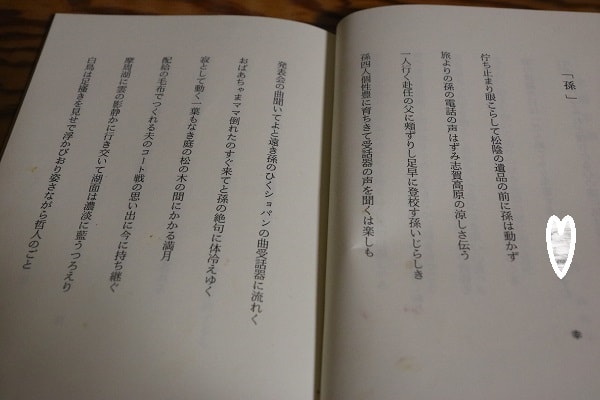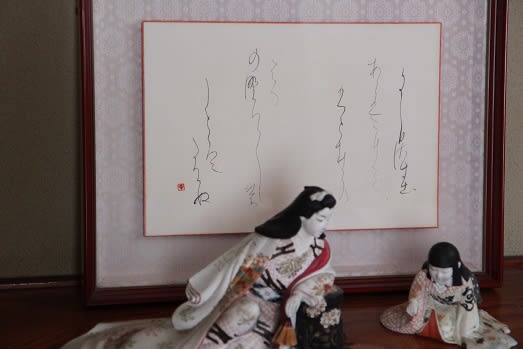旅行記が終わり、通常の日記を綴れる日が、やっと訪れました。
さて今日は、何を題材に取り上げましょうか。
オリンピック、我が家の夏の庭、ささやかなリフォーム、私のその後の体調等々、心にいろいろ浮かびはしますが・・・・・・
浮かぶだけで、それを文章にするとなると、また別問題。
うまく表現する自信がなくて、ブログは私にとって、相変わらずチョッピリ生活のストレスです。
いつものように、衒うことなく、素直に正直に、自分の心情を綴れば、何とかまとまる、との気持ちで、これからもまいります。
案ずるより生むが易し、といったところでしょうか。(笑)
いろいろ心に浮かぶ、書けそうな題材を挙げてみましたが、それ以外に取り上げたい大切な事が、もう一つありました。
自分の生い立ちから、見過ごすことはできなくて・・・・・・・
それは、一昨日の原爆の日、平和祈念式典です。
今年は、67回目に当たります。
懐かしい平和公園がテレビに映り、例年通り、炎天下にもかかわらず、大勢の参列者で溢れていました。

このブログで、すでに触れたことがありますが、原爆についての私の思い出と思いを、再度、お話しさせて頂こうと思います。
同じことの繰り返しになりますが、重複の程は、ご勘弁下さい。
私が生まれ育った故郷、広島。
山の幸、海の幸に恵まれ、川の風景がとても美しい、爽やかな雰囲気のする街です。
原爆投下で焼け野原となった悲惨な状況から、目覚ましい復興を遂げ、今日の繁栄があります。
奇跡といってもよいほどかもしれません。
私は、この土地で、原爆投下の前年、日本の敗戦色が濃くなった、まさに非常事態の状況下で、生を受けました。
そして翌年、爆心地から三キロ離れた地点で、被爆。
私の家族はその時、九死に一生を得ると言った、幸運に恵まれました。
原爆投下が、8月7日ですと、家族は全滅していたからです。
爆心地から徒歩10分程度の場所に父の勤める会社がありました。
出勤していた人は、恐らく全滅だったに違いありません。
父が助かったのは、前日まで出張で、その翌日は出社を30分遅らせることができたから。
我が家の裏に当たる通りの主婦も、爆心地近くの勤労奉仕に出ていたため、全員亡くなったと、聞かされています。
翌日は、我が家の通りの番でした。
ですから、もし原爆投下が、8月7日なら、父母も私も、生きていませんでした。
私の家族のように、紙一重が、生死を運命づける出来事が多かったのも、原爆の日の一面でしょう。
当日、父は、会社まで出かけ、悲惨な会社の状況を我が目で確認。
帰りは黒い雨を浴びて、帰宅しています。
その後しばらく、私達は、母の郷里に疎開したようですが、さほど間をおかず、広島に家族で戻りました。
こんな運命的な出来事を乗り越えて、暮らしてきた我が家ですが。
私は、物心が付き、今日の暮らしに至るまで、原爆の影やその負担を辛く感じたことは、全くと言って良いほどありません。
(妹夢路のブログに、ABCの事が書かれていますね~記憶にあまりないなぁ~一度出かけたにはよく覚えていますが。)
唯一の哀しい思い出は、約1年ほど、祖父母の家に預けられたこと。
母が、戦争前後の苦労で結核を患い、入院することとなりました。
入院日に、黒い車がお迎えに来た時のことを、よく覚えています。
母のあとを、泣き叫びながら私は追いました。
預けられた祖父母の家近くで、近所の子供達と遊んででいる時の事。
傍を霊柩車が通りました。
親指を隠さないと、親が死ぬと友達に言われ、慌てて隠そうとしたのですが、間に合いません。
「そのせいで、離れて暮らしているお母さんが、死んでしまうかもしれない」と、幼心を非常に痛めたものでした。
まだ年端もいかない年齢ながら、鮮明に記憶しているのは、あまりに辛い出来事として、心に深く刻まれたからでしょう。
母は、実家の援助もあり、ストレプトマイシンという、その当時大変高額な薬が服用でき、命を取り留めることができました。
その後も、戦後の物資が乏しい中、荒廃しきった広島での子育ては、想像を絶する苦労があったに違いありません。
母専用の子守が付く程のお姫様のような娘時代を送った母が、一転、どん底に突き落とされてしまいました。
そのギャップに寄るすさまじい苦労は、推して図られます。

夕焼けが美しかったので、我が家のベランダで撮りました。
しかし、そのような我が家ながら、原爆の苦労話が話題にのぼることは、ほとんどありませんでした。
両親は、余りに悲惨なことゆえ、触れることさえ、ためらわれたのでしょうか。
忘却の彼方に押しやって、放射能の体への影響といった不安や心配の要素はすべて掻き消し、平凡な日常を送りたかったのかもしれません。
そのお陰で、私も、被爆者といった意識を全く持たないで、人生を送ることができました。
被爆者手帳を利用すれば、医療費、居住市の交通は無料といった恩恵がありましたが、被害者意識が皆無だった私。
ゆえに、被爆者保護の手当てを利用し始めたのも、40代の中頃からでした。
問題意識の強い方には、呆れた人生と映るかもしれません。
けれど、広島県人には、原爆の苦労を話題にする人は、意外に少ないです。
私の知る限り、広島における小、中、高の生活でも、そのことが大きな問題として取り上げられた記憶がありません。
友人達と、それが話題になったこともありません。
原爆の傷跡は、至る所にあったはずですが・・・・・・・・
広島市民の大方の人は、忘れ去ることで、心の平安を取り戻すことができたのではないでしょうか。
被爆者の意識からは解放された、意外にも、屈託のない暮らしぶりでした。
その点、福島の人達は、情報過多の中にあり、苦労が一層増幅されているようで、気の毒に感じもします。
時代の違いで、致し方のないことではありますが。
低放射能の影響などが、あまりオーバーに声高に吹聴されると、差別の要因になりはしないかと、心配にさえなります。
個人の力でできることには限りがあります。
心許ない政府ですが、行政を信じ、いやなことは忘れて、静かな平穏な日常を取り戻したい、と願う方々も大勢いらっしゃるに違いありません。
政府は、原発の事故で、苦労を背負わされた人達への目配りを、もっともっとしなければ、責任を果たしたとは言えません。
健康管理の医療の助成も当然でしょう。
その要請の働きかけは、然るべき人たちに、是非頑張ってもらいたいものです。
一方で、福島の人達には、あまり周りの情報に心を惑わされることなく、穏やかに平穏な日々を暮らしてほしい、と願うのは、私だけでしょうか。
関東地区の放射能の量で一喜一憂して暮らす過敏さには、正直言って、私は理解に苦しみます。
そんなに心配しなくても大丈夫、と生きた証人の私は、伝えたい心境です。
当日爆心地近くまで出かけ、黒い雨まで浴びた父は、82歳まで生を全うしました。
最後はがんを患ってなくなりましたが、それまで病気とは全く縁のない人でした。
放射能の影響を受けやすい乳児だった私も、今なお、元気に暮らしています。
しかし、核廃絶と、核の平和利用をへの対応となると、あまりに難しい問題で、私には未だによく分かりません。
核を平和利用している限り、何時それが戦争に転用されないとも限りませんものね~
核が、世界の平和にとって脅威であることは変わりないでしょう。
昨夜、夫に夕食の時、「あなたは、原発は廃止すべきと思う?」と尋ねてみました。
夫は、「反対ではない」と答えました。
その理由は、化石燃料は、いつまでも持たないし、自然エネルギーはまだ未発達の状況だから、というものでした。
私も、夫と同意見です。
野田総理も平和式典で述べられたように、脱原発依存の基本理念は私も変わりありませんが。
あまりに性急に、この問題に対応し、廃止か持続かの結論を下すのは如何なものでしょうか。
自然エネルギーの開発に全力で臨む一方、今はある程度の原発の利用も止むを得ないのでは、と思います。
その安全性を高めるための研鑽に、日本の最先端の科学技術と知識を生かし、精魂を傾けて取り組んでほしい、と。
そして我が国のみならず、原発利用をする国々のためにも、その安全性が高められるよう、国際的な尽力と貢献をしてほしい、と願って止みません。
最後にまた、同窓生の慶応義塾大学の元工学部教授のお話を、再度ご紹介しましょう。
私の心にかかり、拭い去ることのできない言葉です。
今の私は、複雑な心境で、受け留めていますけれど・・・・・・
「核を平和利用する以外に、人類が生き延びる道はない。
どんなきれい事を述べても、人類が滅亡すれば、元も子もありませんよ。
私達は、子や孫の世代より、もっともっと先を見据えないといけないんだよ」
 にほんブログ村
にほんブログ村
お立ち寄り下さいまして、有難うございました。
ランキングに参加中です。
60代のバナーをポチっと、宜しくお願い致します。