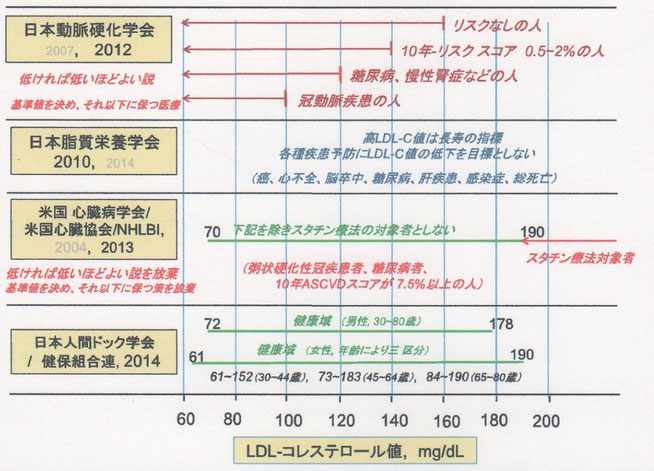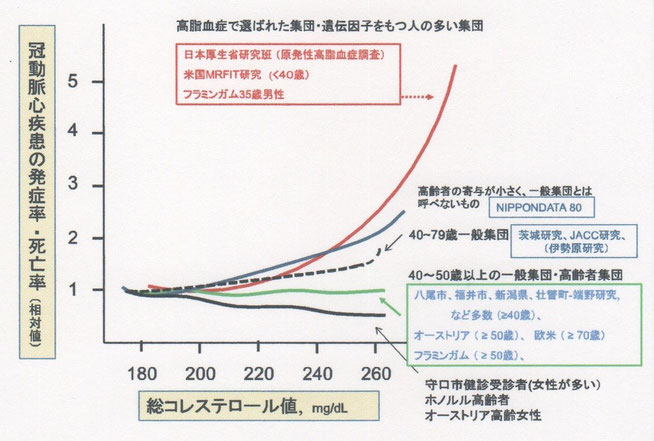メタボ・糖尿病からサヨナラする最善の方法
メタボ・糖尿病に関連する10本ほどのブログ記事を要約したものをホームページ「生涯現役をサポート:三宅薬品のHP」に掲げていますが、このブログで再掲することにします。
メタボ・糖尿病のコーナー
● はじめに
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)という言葉が一躍有名になったのが2006年。これは厚労省のキャンペーンによるもので、この年に流行語大賞ベストテンにもランクインしました。
同じ年に国連総会で「世界糖尿病デー」が定められました。世界的に糖尿病が蔓延し、その予防を喚起しようというものです。定められた日にちは11月14日。この日はインスリンの発見者、バンディング博士の生誕日。日本にとっては食欲の秋真っ盛りでグッドな日にち設定です。
メタボがなぜ良くないかというと、肥満、高血糖、高血圧、高脂血症(今は脂質異常症)の4つが重なりあうことが多くなり、成人病(今は生活習慣病)の危険が高くなるからです。これは、メタボという言葉が登場したときから更に遡ること20年、「死の四重奏」という言葉があり、かなり以前から言われていたことです。この言葉はメタボと同義語と考えてよいです。
「死の四重奏」について、随分前に当店の啓蒙チラシで説明したものがありますので、それの要約を以下に示します。
毎日、満腹するほどに食べれば、体にいいわけがありません。これは石炭ストーブに例えられます。石炭を少なめに入れると良く燃えますが、いっぱい詰め込むと燃えが悪いです。空気つまり酸素が入りにくくなってしまうからです。
ヒトの体もこれと一緒で、満腹に食べると栄養がいっぱい入ってきて、燃やすのが大変です。当然ですよね。肺から取り入れられる酸素は栄養摂取の多少にかかわらず一定です。栄養を取り過ぎると、血液中に栄養がいっぱいになり、ドロドロになって血液の流れが悪くなり、全身の細胞への酸素の供給が滞りがちになります。
すると、栄養を燃やすこと、つまり代謝が進みにくくなり、よけいに栄養がだぶつきます。ヒトの体は、余分な栄養が入ってきたら、これを飢餓に備えて限りなく備蓄しようとします。先ずは皮下脂肪にします。これは、たくさん付いても特に問題はありません。
ある程度皮下脂肪が付くと、今度は内臓に脂肪を付けます。これが進むと、内臓の働きを悪くします。膵臓に付き過ぎるとインスリンの出が悪くなり、糖尿病になります。(注:ただし、多くは別の原因。後ほど説明。)
皮下や内臓にある程度脂肪が付くと、栄養の受け取り手がなくなり、栄養が血液中を漂うようになります。これが高脂血症(脂質異常症)です。
すると、過剰な栄養が血管壁に張り付くようになり、血液の通りが悪くなります。でも、心臓は、休みなく体中に酸素を送り続けねばなりません。よって、心臓は無理に力を入れて血液を流そうとします。これが高血圧です。
こうして、肥満、高血糖、高脂血症(脂質異常症)、高血圧の4つが次々に連動して起こり、糖尿病、血管性疾患(脳梗塞など)はじめ、様々な生活習慣病を誘発することになってしまいます。(要約ここまで)
これら生活習慣病の中で、飽食によって最も多く発症するのが糖尿病と言えましょう。食べる方は制限せずに体を動かすことを少なくすればするほど発症率が高まるのが糖尿病です。
日本人の糖尿病(強く疑われる人を含む)者数は、推計で成人の12%ですが、全く働くことをしないナウル共和国(太平洋の小さな島国:リン鉱石産出で莫大な外貨収入(ただし今は資源枯渇で諸外国から援助))では糖尿病患者は31%、似たような生活のアラブ産油国は30~20%となっています。
日本人はまだ大丈夫、と考えてはなりません。年々漸増しているからです。

参考までに、厚労省の国民健康・栄養調査における成人の糖尿病(強く疑われる人を含む)者数の推計値は次のとおりです。
1997年 690万人
2002年 740万人
2007年 890万人
2012年 950万人
(5年毎にこの調査が行われます。)
● 糖尿病の基準値、判定基準
糖尿病の判定は、空腹時血糖値、負荷後2時間血糖値、HbA1cの3つの指標でもって細分化された判定基準チャートによってなされますから、あたかも正確な判定方法に思えてしまいますが、画一的すぎて問題がありそうです。
3つの指標のうち最も基本的な判定基準は、空腹時血糖値であり、正常型(~109)[うち正常高値(100~109)]、境界型(110~125)、糖尿型(126~)と定められています。
でも、血糖値には個人差があって、ずっと境界型に入っていても何ら問題がない方もあります。また、性差があって男のほうが数ポイント高めです。なお、年齢差も若干あり、4、50歳までは若干上がる(数ポイント)傾向にあるようですが、その後安定します。(参照:男女別、年齢階層別の本来の基準値)
こうしたことから、判定基準からして自分は大丈夫だ、と考えるのは危険です。個々人の判定基準は、「数値に変化がなければ問題なし」、「数値がだんだん上がってきたら要注意、いや、既に糖尿病になっている!」と考えねばならないでしょう。ただし、ストレスで血糖値は上昇しますから、定期検診のときに大きなストレスがかかっていたかどうか、その点に留意してご判断ください。
● 糖尿病の発症原因
わざわざ説明するまでもないでしょうが、前項で「数値がだんだん上がってきたら要注意、いや既に糖尿病になっている!」と書きましたのは、少々古い話ですが、2001年の講演録(昭和薬科大学:田代眞一教授)が元です。
それを概説することにします。これは今でも通用することです。
食事をすると、消化された糖(ブドウ糖)が血液中に入ってきて、食後にどんどん血糖値が上がります。これを膵臓のランゲルハンス島がキャッチしてインスリンを大量に放出します。肝細胞や脂肪細胞に一定量のインスリンが届くと、血液中の糖を肝細胞にあってはグリコーゲンに、脂肪細胞にあっては脂肪に作り替えて蓄え、ほどなくして血糖値が下がります。
無茶な過食を反復していても、とりあえずは膵臓が必死にインスリンを出してくれ、脂肪細胞で蓄えますから、血糖値は上がらずに済みます。
ところが、インスリンは脂肪細胞の数を増やす働きを持っており、脂肪の倉庫をポンポンにしながら、倉庫の増設もどんどん行うのです。つまり、脂肪細胞の数がだんだん増えてきます。当然、体は肥満していきます。
ここで困った問題が発生します。脂肪細胞が増えたら、増えた分だけインスリンの量が多く必要になり、以前と同じ量を食べてもインスリンの量は以前よりも多く放出せねばならなくなるのです。これを「インスリン抵抗性」と言います。
この段階でも、膵臓は必死にインスリンを作り続けますから、まだ血糖値は上がりません。でも、膵臓は酷使され、やがて疲れきってきます。
この状態を過ぎても過食が続くと、ついに膵臓は弱り果て、インスリンの分泌量が少しずつ落ちてきて、いよいよ血糖値が上がり始めます。
「血糖値が上がり始めた。でも正常値の範囲内だから大丈夫だ。」という考え方を多くの方はなさるのですが、これは以上のことから間違っています。
「膵臓は一生懸命働き続け、過酷な労働にずっと耐えてきた。でも、とうとう限界が来てガタガタになってしまった。事ここに至っては、元どおりの元気な膵臓に戻すのは至難の業だ。決して初期ではない。」ということを理解していただきたいのです。
「今のうちなら、まだ直せるかもしれない。その努力を今すぐ始めよう。」という意味での警告と捉えれば初期と言えましょう。でも、本当は初期ではない。
いかがでしょうか。定期検診の目的は、早期発見・早期治療などと言われますが、検査数値に頼って安心していては、“時すでに遅し”となってしまうのが糖尿病なのです。肥満体の方は、今すぐに飽食を戒め、少なくとも腹八分に落とさないことには、本質的な予防は難しいのです。
なお、生まれてこの方、過食したことはなく、ずっとやせ型であっても糖尿病になる方がけっこういらっしゃいます。
その原因の一つには、糖尿病になりやすい体質(膵臓のインスリン分泌量が加齢によって落ちてくる)であって、これは遺伝性のものが多いようです。
他の原因として、注目していただきたいのは、続発性糖尿病(他の疾患によって引き起こされるもの)と類似しますが、「冷たい物中毒、口呼吸」によって発症することが往々にしてあると西原克成氏は強く訴えかけておられます。
これは、冷たい物中毒にあっては腸粘膜からの腸内細菌の体内侵入、口呼吸にあっては口腔・鼻腔粘膜からの常在菌の侵入によって体内細胞が細菌感染し、その感染が膵臓に特化した場合に膵臓の働きが落ちて糖尿病になるというものです。このことについては、 アトピーのコーナー「アトピーの真の原因」で解説しましたが、原理は同じですから参考になさってださい。
(2016.9.9追記:2014年6月、順天堂大学の研究グループが、“腸内細菌が血液中に移行することを初めて発見した”と発表し、糖尿病との関わりを論文にしています。)
● 高血糖が続くとなぜ悪いのか
高血糖が続くと良くない理由として、“血液がベトベト”状態になり、赤血球がくっついて塊になって血液の流れを悪くする、そして糖が血管を変質させ、傷つけ、血管壁にコレステロールを沈着しやすくする、加えて膵臓のランゲルハンス島のβ細胞(インスリンを分泌)を破壊する、といったことが挙げられます。
それはそれとして、ブドウ糖の害について、高血糖でない方にあっても、特に甘い物好きの方には、十分に理解していただきたいです。
ブログ記事「古典的な砂糖の害は間違い。本当の害は“ブドウ糖の暴走”」から、その要旨を以下に記します。
ブドウ糖は、様々な物質と化学的、物理的に結合するという特性を有しています。
まず、良い点を挙げましょう。
配糖体と呼ばれるものがそうで、ブドウ糖が他の物質と化学的に結合していて、有用な作用をするものが非常に多いです。
例えば、抗酸化物質で有名なポリフェノールの代表的なものとしてフラボノイドがありますが、これは別名フラバン配糖体とも呼ばれます。
次に、ブドウ糖が他の物質と化学的に結合することによって、困ったことが発生する例を紹介します。
基本的に生体内における化学反応は酵素の働きで行われるのですが、ブドウ糖は酵素なしで勝手に他の物質と化学的に結合しやすい性質があります。
その代表的なものがメイラード反応です。メイラード反応は、食品加工で良く知られた化学反応なのですが、加熱によってブドウ糖とアミノ酸(たんぱく質のアミノ基)が結合し、香気がある褐色物質を生み出します。
このメイラード反応が生体内で起きる一例が、糖尿病の指標となる糖化ヘモグロビン(HbA1c)です。高血糖が続けば、ブドウ糖がヘモグロビンとメイラード反応を起こしやすくなり、糖化ヘモグロビンの量が増えて、ヘモグロビンの活性が失われ、酸素供給力が落ちることになります。
これは、人体にさしたる悪影響を与えませんが、生体内で起きるメイラード反応で、健康に大きく悪影響するものがかなりありそうなのです。
まず、体内で作られる代表的な抗酸化物質であるSODがメイラード反応を起こしてしまい、その機能が発揮できなくなります。
次に、細胞外たんぱく質であるコラーゲンがメイラード反応を起こしてコラーゲン間に架橋ができ、例えば水晶体に濁り(白内障)が生じます。
3つ目に、免疫グロブリン(血液中にある抗体)の活性が失われます。免疫グロブリンはそもそも配糖体なのですが、ブドウ糖が新たに違う箇所にも化合してしまうことによります。
生体内におけるメイラード反応は、この他にもいろいろあります。その程度はまだ研究が始まって間がないようですから、情報が少なく、私の調査不足で十分に説明できませんが、何らかのメイラード反応を起こすことが分かっているものを以下に例示しておきます。
酵素:カテプシンB、リゾチーム、膵リポアーゼ、炭酸デヒドラクターゼ
血清:アルブミン、フィブリン、フィブリノーゲン
ホルモン:甲状腺ホルモン、インスリン
細胞:赤血球膜たんぱく質
このように生体内におけるメイラード反応は多義に渡りますから、糖尿病の合併症には様々なものが出てくるのでしょう。
ところで、メイラード反応は、何も糖尿病患者に限ったことではなく、健常者であっても砂糖を取りすぎると一時的に高血糖になり、そのときにメイラード反応が生じているのですから要注意です。
現に、砂糖の取りすぎで免疫力低下をきたすと言われますが、これは、先に取り上げました抗酸化物質であるSODと免疫グロブリンのメイラード反応も一因となっていましょう。また、砂糖の取りすぎで、免疫細胞の1種であるマクロファージ(最前線で細菌やウイルスを飲み込んで消化する白血球)の活性が大きく落ちることが知られています。これは、メイラード反応かどうか不明ですが、いずれにしても高濃度のブドウ糖が原因していると考えるしかないでしょう。
● 糖尿病の改善方法
<何よりも少食に>
これも、わざわざ説明するまでもないでしょうが、現在採られている糖尿病食は、はたしてこれで良いのか、疑問が多いです。
最大の問題は「1日3食」としていることです。糖尿病食マニュアルの中には、『典型的な悪い食べ方として、「朝抜き、昼そば、夜大食い」があげられます。気をつけましょう。』とあり、皆さん、朝食をしっかり取っておられます。
しかし、1日3食きちんと食べる民族は日本人ぐらいなものです。朝食が有害なことは西欧では分かり切ったことになっていて、ごく軽くしか食べません。
欧米人に比べて日本人に糖尿病が多いのは、ここに起因しているものと私は捉えています。ここは“膵臓さん”の立場になって、よーく考えてください。
疲労困憊している膵臓ですから、何よりも膵臓が欲しがっているのは「休み時間」です。1日に3度も食べればほとんど休んでいる暇がありません。
そこで、思い切って「朝食を抜く」のです。そうすれば、膵臓は毎日連続12時間程度インスリンを出す必要はなくなり、ゆっくり休めるのです。
なお、朝食を抜くことによって生ずる困った問題は、空腹感と食欲煩悩の高まりですが、慣れれば完全に解消します。もっとも、いきなり抜くのはきついですから、だんだん減らして体を慣らさせねばなりません。そうすれば、体内脂肪をエネルギー変換する回路が円滑に回るようになり、空腹感が消えます。
参考記事:朝食抜き、1日2食で健康!
そして、より膵臓を休ませるには、「昼食も抜いた1日1食」、「週1回の断食」へ持っていくことです。
ここで、絶対にしてはならないのは食事を抜いたあとの「ドカ食い」です。
人間、腹八分で健康といいますが、腹五分いやそれ以下であっても栄養失調になることは絶対にありません。糖尿病の方は、ここのところをしっかり頭に置いて食生活の改善をなさるべきです。
参考記事:腹「X」分目健康法…腹五分そして腹二分まであります
<食事の質が重要>
(詳細はブログ記事:糖尿病改善「食養」三則 をご覧になってください。ここではその要約を記すこととします。)
糖尿病改善「食養」三則
第1 腸内環境を良好に保つ
1 カロリーオーバーの解消
大量のウンチが出れば、必然的にカロリー吸収量を少なくします。便秘すると、それだけ身に付くことになります。
2 免疫力アップと毒素吸収抑制
便秘すると悪玉菌が毒素を作り、これが体中を駆け巡り、膵臓も弱ります。
(2016.9.9追記:腸内環境が悪いと、腸内細菌が血液中に移行し、糖尿病を発症する恐れがあることを、2014年6月、順天堂大学の研究グループが発表しています。)
3 ミネラル吸収アップ
善玉菌が活発に働くと、大腸からのミネラル吸収を良くします。
そこで、腸内環境改善の心得「五箇条」
1 たんぱく質を控える
2 脂肪・油脂を控える
3 食物繊維・オリゴ糖を積極的に摂取
腸内善玉菌の餌になるもので、特に「オリゴ糖」で善玉菌が活動的になります。中でも「オリゴ糖」がたっぷりの「ヤーコン芋」が最高に良いです。
4 消化促進
良く噛んで食べるのが基本。消化薬を補助的に使うといいです。
5 整腸剤
快適なお通じが得られないときは整腸剤の助けを求めましょう。
第2 食後過血糖を解消する食材
血糖値を抑える薬は、強烈に効き、長期連用すると副作用を伴いがちです。
血糖値を抑える力が弱くても、副作用がない自然食品を愛飲したいです。
おすすめは「ヤーコン葉エキス」と「桑葉エキス」の併飲です。消化されて出来たブドウ糖をゆっくりゆっくり吸収させるだけですから、決して低血糖にはならず、食後過血糖を防いでくれます。なお、「ヤーコン葉エキス」はインスリン様作用があって、その分インスリン分泌が少なくて済み、膵臓を休ませてくれる、すぐれものです。
ところで、炭水化物はブドウ糖に消化されるから、食後過血糖を防ぐために、たんぱく質を多く摂って、これをエネルギー源になさる方がおみえですが、これでは腸内環境を悪化させ、かえって良くないです。
これと類似した方法として、たんぱく質に代えてオリゴ糖たっぷりのヤーコン芋を多食する方法があります。オリゴ糖は消化されず、善玉菌の餌になり、ブドウ糖が作られないからです。なお、この場合には、有機酸が多量に作られ、これがエネルギー源となります。また、オリゴ糖で善玉菌が増え、腸内環境が抜群に良くなり、最高におすすめの方法です。
参考記事:「ヤーコン芋で糖尿病が奇跡的に完治」
第3 不可欠なミネラルをしっかり補給
生命活動は、酵素(多くはミネラルを中心に据えた有機物)が触媒となって、休むことなく細胞に必要なものを合成したり分解したりして営まれています。
インスリンの生産をスムーズにするにも各種ミネラルは必須です。
しかし、飽食時代にあっても、そのミネラルが不足しがちです。
そこで、積極的に総合ミネラル剤を補給したいものです。
<糖尿病改善に不可欠なミネラル>
亜 鉛 インスリンの合成とインスリンの活性化、糖の燃焼促進
*マグネシウム インスリンの合成とインスリンの活性化、糖の燃焼促進
*カルシウム インスリンの合成に関与
セ レ ン インスリン類似作用、糖の燃焼促進
マンガン インスリンの合成に関与、糖の燃焼促進
ク ロ ム インスリンの作用を良くする
モリブデン 糖の燃焼を助ける
(*2016.9.30挿入)
かなりの長文を最後までお読みいただき、ありがとうございました。これをお読みになった皆様がメタボ・糖尿病からサヨナラできるのを陰ながらお祈りいたしております。