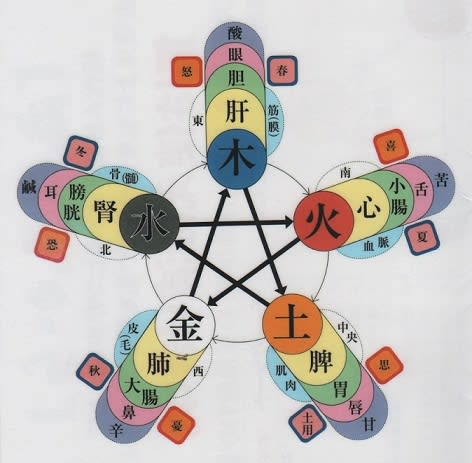高血圧の話はもう終わりにしませんか、そして高血圧の薬を飲むのは止め!
(2016.8.13改題)
このブログで最もアクセスが多い記事は高血圧に関する記事でして、コメントも数多く寄せられ、またメッセージなどからの相談も度々入ってきております。
そうしたことから、高血圧をテーマにした記事を今までにこのブログで11本(まとめや改訂で実質7本)も書いてきました。
しかしながら、高血圧というものは、つまるところ測定数値の大小で一喜一憂させられるだけのことでして、血圧がどんなに高くても何ら支障ないと言い切っても、まず問題にならないと、ますます最近思えるようになりました。
そこで、このブログでまだ紹介していない戦前の古典的な適正血圧の捉え方を本稿で紹介し、 これでもって高血圧の話を終わりにしたいと思います。
なお、以下の記事は、先日、別立てブログ「薬屋のおやじの“一日一楽”&“2日前”の日記」に2回に分けて書いたものを再編集し、松本光正著「高血圧はほっとくのが一番」を参考にするなどして一部書き添え、まとめあげたものです。
<戦前の古典的な適正血圧の捉え方(その1)>
下(拡張期)の血圧[最低血圧]は上(収縮期)の血圧[最高血圧]の11分の7が理想的なようです。これは、昭和9年頃に健康医学の大家、西勝造氏が提唱され、力説されていたことです。しかし、今日、これを支持する医学者は残念ながら誰もいないようです。
ところで、なぜに11分の7なのか。その説明は手持ちの書には書かれておらず、どうしてだろうと疑問を持ち続けていたところ、先日、それにハッと気が付きました。
西氏の弟子として有名な甲田光雄医師(故人)の古いラジオ放送がYou Tubeで流されており、それを聞いていたら、少食を第一とする健康生活を送っておられた甲田氏が、“自分の血圧は、ずっと上が110で下が70だ”と言っておられました。
なあんだ、そうか。これを聞いて、類まれなる健康体であれば皆そうなるのだし、110と70ということは、比率は11:7で、「下の血圧は上の血圧の11分の7」になる、という簡単な算数です。これに気付くのがとんと遅い小生。
粗食で毎日動き回っている狩猟採集民の血圧は、上が110で、下が70であるし、軽いジョギングを続けていると、だんだん上110、下70に近づいていく傾向にあるという臨床データもあります。このことについては、このブログで既に紹介(「ゆっくり走って治す高血圧…」)しているし、自分でもしっかり記憶できてもいるはずです。
それにもかかわらず110と70が11分の7と表現されると、全く別のものに思えてしまって、同じことを言っているのがいつまで経っても分からなかったのは、いかに小生の脳が硬くなっているのかを示しています。お恥ずかしいかぎりです。
ところで、文明生活にどっぷり浸かっていると、過食が元で動脈硬化が進み、血圧は年とともに必ず上がっていきます。これは常識であり、間違いないことです。
そして、西勝造氏の言によれば、過食傾向にあっても、その食事内容が正しく、適度な運動を毎日していれば、血圧の上下とも同じ比率で上がっていき、つまり下の血圧は上の血圧の11分の7が保たれるといいます。加えて、この11分の7が保たれている限り、上の血圧はのちほど紹介する年齢を加味した「正常なる最高血圧」の2倍あっても差し支えないとまでおっしゃっておられます。つまり、血圧は200数十あったって何ら問題はないということも往々にして有り得るというものです。これには小生もたまげました。でも、西氏であれば、数多くの臨床データからの解析結果に違いなく、信頼できる発言でしょう。
西氏が力説されていることは、次のことです。
注意せねばならないのは、血圧がごく普通の数値であっても、最低血圧が最高血圧の11分の6を下回ったり、逆に11分の8を超えたりした場合です。
戦前の日本人は、これが7を下回る(平均では6.4)傾向にあり、その原因は手持ちの書だけでははっきりしないものの、どうやら白米の多食によるビタミンB1欠乏が第1のように思われるのですが、7を超えるのが米国人(平均では7.4)であり、その原因は肉や乳製品の多食にあることははっきりしています。
さて、小生はいかに。測ってみたら、上137、下84。11分の6.7と出ました。11分の7に近いとはとうてい言えない数値。でも、白米の多食はないし、白米といっても七分搗きであるし、かつ、ビタミンB1を多く含む豚肉が食卓にのぼることが多いから、ビタミンB1欠乏ではないでしょう。すると、原因は別のところにありそうなのですが、残念ながら真の原因はとんと分かりません。
さてさて、久し振りに血圧測定したその翌日は外食したのですが、小生の11分の6.7という数値からして中華料理店に行き、ご飯を少なくし、酢豚をたっぷり食べ、グルメを満喫しました。そして、これからは野菜も大事だが、しっかり肉食もしていれば、血圧が理想的な11分の7に近づきはしまいか。年寄りは肉を食いたがるのは自然の流れであると、つい最近、別立てブログで記事「年寄りは肉を食え」にしたばかりだし。
こうした口の卑しさに対して屁理屈をこねて正当化しようとする意地汚さに我ながら辟易するのですが、この年(67歳)になると、ますます何よりも食うことが最大の生きがいになってきていて、我が煩悩のなせるままにするしかないでしょうね。
<戦前の古典的な適正血圧の捉え方(その2)>
ここからは、上の血圧について述べることにします。
上の血圧が幾つなら正常なのか、あるいは理想的なのか、そして危険なのか。これについては、戦後の日本において医学界はどんどん低い数値を基準値に設定し、改定を繰り返しています。ということは、その医学が正しければ、日本人は高度文明社会に別れを告げて順次狩猟採集民生活へ逆戻りしていることを意味します。
現実は逆です。狩猟採集民、農耕民、文明社会人と進むにつれ、血圧が高まってくるのは医学界でも常識であり、医学界がまっとうであるならば、戦前より戦後は血圧の基準値を上げねばならないのですし、高度成長後はもっと上げねばならないのですし、車社会になってからはまた一段上げねばならないのです。
飽食して運動不足が重なれば、これによって血圧が上がっていくのは因果の法則に基づくものですし、平和が続き文明が高度化すれば、必然的にこうなり、これを認めずして基準も設定のしようがないのです。
さて、すこぶる健康で理想的な血圧は、先に書いた狩猟採集民の上110、下70で、人間の理想値はこれ一つで不動のものです。ヒトと同程度の大きさの健康な大型犬の血圧は上90で、ヒトは四足から二足直立したがために頭へ血液をポンプアップする必要が生じ、20アップして110となったのです。
ということは、すこぶる健康な寝たきり老人(有り得ない存在ですが)の上の血圧は90が理想値となります。
血圧がいつも高めに出て、お医者さんに脅されることが多い方は、緊張感もあって定期健診などで測ってもらうと、より高い値が出がちです。そんなときは、“緊張しちゃって…。横になるとリラックスできますので、そこのベッドで横になってから測っていただけませんか。”と申し出られてはいかがでしょうか。お医者さんに嫌がられるかもしれませんが、これで20下がります。こうした申し出をしたときにクスリと微笑めば、緊張感も抜けて、それ以上に下がるでしょう。血圧低下の一番の薬は“クスリと笑う”ことなのですからね。
今どき上110、下70という理想的な血圧の持ち主は珍しい存在です。でも、小生は還暦前あたりまでは、上110台、下70台前半でした。それが維持できたのは、1日1食(夕食のみ)で肉少々・野菜たっぷりの食事とし、店や畑仕事で毎日体をよく動かしていたからです。
それが今は前日に測定したように上137、下84となってしまいました。10年ほど前に比べて上20アップ、下10アップです。1日1食生活を続けているも、以前に比べて腹いっぱい苦しいほどに食べるようになりましたし、店や畑仕事での体の動かし方も減ったからです。また、加齢も原因していましょう。
この小生の上の血圧をどう評価するかですが、ちょうどピッタリ当てはまる基準値がありました。これまた西勝造氏が昭和9年頃に提唱された「正常なる血圧」の項で示された「正常なる最高血圧」でして、これは次の算式で求められます。
男子 最高血圧=115+(年齢ー20)/2
(婦人に対しては男子より一般に5ミリ低いのを正規とする。)
これに小生の年齢(67歳6か月)を入れて計算すれば、約139となり、極めて「正常なる最高血圧」となります。“どうだ、立派だろう”と威張りたくなります。少なくとも昭和初期の時代の人と同等の食生活や体の動かし方をしていると言えるのだからと。
小生も日本人、こうした数字にとても弱いです。検査測定値に一喜一憂させられます。今回の血圧測定で上137と出て、昔の正常値が139とあるから、大喜びしているのですが、測り直せば140と出ることもありましょう。そうすると、たったの1超えただけですが、がっかり、しょんぼり、悔しーい、となってしまいます。
冷静になって客観的に判断するに、西氏が提唱された「正常なる最高血圧」は昭和初期の人たちに適用されるのであって、今日の高度文明社会人に適用するのは無理がありましょう。より飽食時代になり、より体を動かさなくなっているのですから、戦後の高度成長期頃に言われた次の算式が「正常なる最高血圧」となりましょう。
最高血圧=年齢+90
これによれば、小生の血圧は157あってかまわないのです。
そして、今は当時に比べ、段違いの車社会となりましたから、さらに血圧は高くなり、「正常なる最高血圧」は、もっと単純明解な次の算式で示してよいのではないでしょうか。
最高血圧=年齢+100
非常に分かりやすい基準値です。小生は167あってしかるべき。それが137と30も低いのは、あまりに時代遅れな原始人だ、ということになります。考えてみるに、小生が1日1食でずっと通していると言うと、皆、目を丸くしてびっくりするし、店の暇を見つけては野良仕事をしているのですが、よう動くなあ、と感心されます。自分ではマイペースでそうしているのでして何も無理していないのですが、傍目からはそう映るのであり、どれだけか原始人的ではありましょう。
文明は後戻りせず前へ前へと進みます。これから10年20年経てば、世の中はよりグルメになり、指先だけを小まめに動かすだけの生活となるのは必至で、小生が唱える単純明快な“正常血圧式”が正しいものであるとして評価されてほしいものです。
平和で豊かで便利な社会、これが何と言っても誰にも最優先で求められるものでして、これによって人々は幸せを満喫できるのです。誰も狩猟採集民に戻りたいとは思わないです。おらの村には電気もねえ、車もねえ、こんな村にはとてもじゃねえが住めたものじゃねえ、です。そう思いませんか、皆さん。
それと引き換えに脳梗塞、脳溢血、心筋梗塞といった血管の詰まりや破れによる病気に罹る確率が増えていくのですが、電気もある、車もある、コンピュータもある、グルメも満喫できる、そうした高度文明の恩恵に浴しているのですから、これは必然でして、血圧測定の数値を見て悪あがきしても全く無駄なことです。血圧が高くても低くても、こうした疾患は皆、等しく発症する危険性を同程度の確率で持っているのが現実ですし、それよりも、数値の大小にかかわらず、加齢によって循環器・脳血管疾患の危険度はグングン増すのであって、これは防ぎようがない性質のものなのです。
話はちょっとずれますが、簡単に健康測定できるものに何があるでしょうか。一つは体重計ですが、秤に乗らなくてもメタボかどうか見当がつきますから、なくてもいいものです。2つ目が体温計ですが、これもおでこに手を当てれば見当がつきますし、測ってみて39度もあればびっくりしてあわてふためくだけで、意味をなさないです。3つ目が血圧計です。小生がそうですが、血圧測定して一喜一憂させられるのですが、どんな数値が出ても、実際のところ、これまた何の役にも立たないのです。
ただし、体温が40度もあれば何か手を打たねばならなくなるのと同様に、血圧が300にもなれば何か手を打たねばならないでしょう。もっとも、戦後初期に対米交渉を行った吉田茂首相は、交渉時には血圧が常時300になったといいますから、風邪をひいて38度の熱があってもけっこう仕事はできるのですし、血圧が300であっても仕事をして差し支えないとも言えます。安静にせねばならない血圧が幾つ以上なのか、それは小生には分かりませんが、とんでもない高い数値になれば、体が異常を感じて生体反応が働き、横になってじっとしていたくなるでしょう。そうなったときに、血圧を測ってみて、とんでもない数値が出たら、何とかなる場合は何とかなるでしょう。ただ、それだけのことです。
血圧に関して困った問題は、医学界が適正血圧なるものを低めに設定し、事あるごとに血圧を測定させ、一度でも基準値を超えたら降圧剤を飲ませたがることです。これは日本の医療制度に大きな欠陥があるからでして、薄利多売の商売をせねばならないようになっているからです。医者は数多くの患者を創りだし、薬漬けにしないことには食っていけないのです。結果、世界中の降圧剤の生産高の何と5割を日本人だけで消費させられているのです。これには、うんざりさせられます。ようもこんなに毒を盛るとは、です。
簡単に健康測定できる血圧計というものがこの世にたまたま存在するから、こうなったとしか言えないのではないでしょうか。血圧計の発明者を恨みたくなります。
ちなみに、死亡原因が高血圧性疾患とされる割合は、65~79歳で0.3%、80歳以上で0.7%にすぎません。(平成25年人口動態調査)
実に恐ろしい世の中になったものです。じゃあ、どうすればいいかというと、いずれは循環器・脳血管疾患で死ぬ確率が極めて高いのですから、「ピンピンコロリ」運動を展開してみえる長野県では、お年寄りたちの最新の合言葉は、これが一番苦しまずに死ねるからでしょうが、「脳血管障害で95歳で死のう!」となっているようです。もっとも、救急車を呼んでもらっては困りますが。長野県民は長寿、一人当たり老人医療費もベッド数も全国一少ない、その長野県民は、死を恐れず、悪あがきせず、死を受け入れて、さあどうする、という発想法でもって対処しているから、きっと健康でいられるのでしょう。
ここまで、とりとめもないことを書き綴ってきましたが、小生思うに、血圧というものはヒトの体の原始性を測る道具にすぎず、それが低ければ原始人に近い生活を自ら望んでやっているだけのことであり、それが高ければ高度文明生活を十分に堪能なさっているのであって、どっちが良いの悪いのと決めることはできない性質のものでしょうね。
小生の血圧が大方の人より低いのは単に原始人の生活が好きなだけのことですし、女房は最近血圧がぐんぐん上がってきたのですが、仕事が楽になって立派な高度文明生活をエンジョイしまくっているだけのことです。小生はそのように理解しているところです。
健康で長生きしたかったら、食養生と適度な運動そしてこころのストレスの上手な抜き方、この3つをバランス良く、無理しない範囲で、自分なりにうまく見つけ出すことでしょう。いずれも相当に難しい課題ですが、これをクリアするしか他に方法はないと、つくづく思うようになったこの頃です。
最後に、「高血圧はほっとくのが一番」を著された松本光正医師は、「血圧測定なんかいらない、血圧計は今すぐ捨てなさい」とまでおっしゃっていられます。
ということは、小生に対して“ぐだぐだと血圧のことをこれ以上は書くな”というご忠言をいただいたことにもなり、真摯にこれを受け止めて、表題の「高血圧の話はもう終わりにしませんか」とした次第です。
本稿を最後までお読みいただいた読者の皆様には、長時間無駄話に拘束してしまい、誠に申し訳ありませんでしたが、この駄文が皆様の血圧に対するご理解にどれだけかでもお役に立てれば幸いです。
(2016.8.13補記)
最近、話題になっている週刊現代・週刊文春の対抗記事より、血圧の薬(降圧剤)についてポイントだけ要約して引用します。
<週刊現代7月16日、一部7月23・30日号>
高血圧には2つのタイプがあります。血管が外側から締め付けられるギュウギュウ型と、血液量が増えて起きるパンパン型です。日本人に多いのはパンパン型で、ギュウギュウ型は少ない。原因は塩分摂取量が多いこと。
パンパン型には利尿薬とかカルシウム拮抗薬といったタイプの薬がよく効きます。ところが、ギュウギュウ型に効くARB(ディオバン、アジルバなど)ばかりが処方されている。
カルシウム拮抗薬は長く飲み続けると交感神経が緊張し、心臓に負担がかかります。
<週間文春7月28日号>
高血圧薬は成人の28.1%、70歳以上だと51.5%が服用している。(平成26年 国民健康・栄養調査)
高血圧薬の中で、多くが第1選択としてあげるのがカルシウム拮抗薬。一番安全で使いやすく、たぶん最も飲まれています。
<備考>
2つの週刊誌で、相矛盾する説明がなされているところが、週刊誌らしいですね。
よって、どちらも信頼性に欠けますが、参考にはなりましょう。
いずれにしても、高血圧の薬(降圧剤)は飲んだところでどれだけの効果もなく、かえって害になることのほうが圧倒的に大きいのですから、飲むのを止めるべしです。
(2017.9.2追記)
もう血圧の記事は新たには書くまいと決めていたのですが、最近、180超えの女房を目の当たりにし、また、280くらいもあるお年寄りの例をある方の講演録で知ったものですから、次のとおり記事を1本起こしたところです。
最近、高血圧の薬を飲むのを止める方が増えてきた感がします