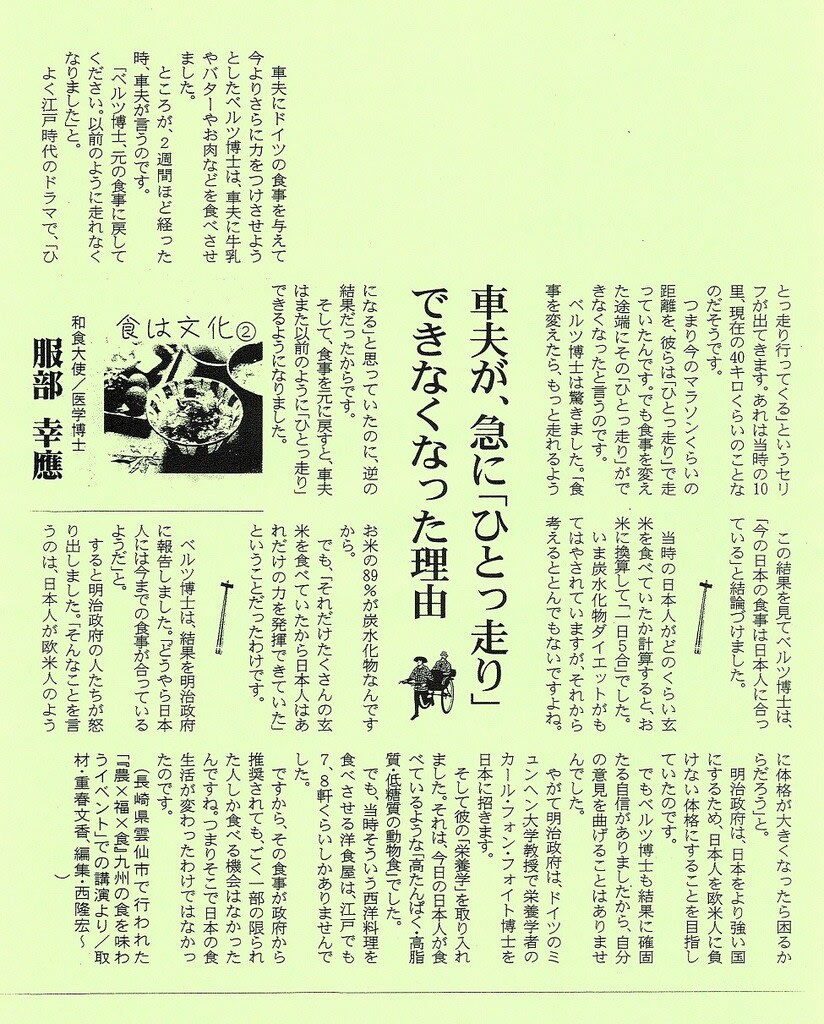年寄り同士諸君、そろそろ新型コロナウイルスで旅立つことを考えましょうよ
1月8日に「コロナの話はもう止めにしましょう、年寄りがちゃんとした死生観を持てばいいだけのことです」と題して、新型コロナウイルスについては記事止めしたのですが、その後、書き漏らしたことについて2つ記事にしました。
コロナ感染予防はやはり腸内環境改善が一番、わけても酪酸菌がものを言う
新型コロナウイルス・ワクチンを打つべきか打たざるべきか
さて、緊急事態宣言が解除されてホッとしたのもつかの間、ここへきて今度は「まん延防止等重点措置」を適用するという。1日の感染者数がたったの2千なり3千人、重症者数が3百なり4百人という“極めてわずかな数”で何を騒いでおる、と言いたい。(もっとも、フランスではここのところ1日3万なり4万人の感染者が出ており、人口が日本の約半分だから、これだけの数となると、少々騒々しくなるのはうなづけるが。)
コロナにはもうウンザリ。腹も立ってくる。そこで、1月8日に「年寄りがちゃんとした死生観を持てばいいだけのことです」として簡単に書いたが、もう少し詳しく(表題のとおり「年寄り同士諸君、そろそろ新型コロナウイルスで旅立つことを考えましょうよ」と)記事を書くことにした。なお、小生も年寄り(72歳:団塊世代)であるゆえ、「年寄り同士諸君」とさせていただいたところである。
今般のコロナ感染で、死ぬのは年寄りばかりであると言ってよく、我々年寄りは、いずれにしても、この先幾ばくもなく、あの世へ間もなく旅立つのであるからして、決して悪足掻きしてはならぬのである。また、あらかたの年寄りは、周りの者たちに迷惑がかからぬよう、ピンピンコロリと逝きたいと願っているのであるからして、コロナでピンピンコロリも、その選択肢の一つなのである。なぜならば、発症して1週間もすれば、運良く、コロリと逝けるであろうから。
これが結論となってしまうが、あまりにも平和ボケしている日本人社会においては、死生観をまともに論ずることは滅多にないし、死生観を考えもしない年寄りが多すぎる。その点、有史以来、侵略と虐殺が絶えなかった欧州人は、まっとうな死生観を持っていると言えよう。
このブログの過去記事のなかから、死生観に関係する部分を抜粋(一部要約)して、ここに紹介することとする。
年寄り同士諸君、これを機会に自分の死生観を確立しようじゃありませんか。
2019.5.14 人生100年時代の到来って本当でしょうか
日本人の平均的死亡年齢予測の推移
厚労省の生命表によれば、65歳まで生き延びた人は、戦前なら70歳台後半で死に、今は80歳台後半で死ぬ。つまり10年長生きするようになりました。さらに80歳まで生き延びた人は、戦前なら85歳ほどで死に、今は90歳前後で死ぬ。つまり数年(男4年、女7年)だけ長生きするようになりました。
このように、今と昔を比べると、年齢が高くなるほど、死ぬ年齢の開きが縮まります。これは、人の寿命というものは、どんなに元気な、どんなに質実剛健な人であっても自ずと限界があることを物語っていましょう。
ところで、健康寿命がどの程度か、です。
想像するに、今と昔の差はグーンと縮まりましょう。80歳の人の平均余命を見たとき、明治時代と昭和50年に大差ありません。それが平成時代になってから伸びだしてきています。これは、老人病院のベッドで“生かされている”人が増えてきたことを物語っていましょう。
2020.11.29 食の進化論 第11章 必ず来るであろう地球寒冷化による食糧危機に備えて
第8節 姨捨山思想の復活
日本には寝たきり老人がものすごい数にのぼる。寝たきりになっても点滴をし、鼻から流動食を流し込み、それができなくなっら腹に穴をあけて胃ろうをし、これでもかとばかり寝たきり老人の延命措置に手を尽くしに尽くす。西欧人は、この日本の現状を老人虐待という。彼らの世界には、今でもちゃんと姨捨山思想がしっかりとある。車椅子を自分で動かせなくなり、食事も自分の手で食べられなくなると、もはや神に召される日は近いと観念し、飲食を断つ。周りの介護者もそのような状態になったら手助けをしないのである。そうして飲食を断って1週間か10日すれば、静かに旅立つのである。日本でもこうしたやり方で寝たきり老人を一掃せねばいかんだろう。西欧にはそしてアメリカにも寝たきり老人は基本的に存在しないのであるから。
(それに対して、日本人社会で目立つのは)寝たきり老人の増加。高度成長後しばらくしてから肺炎死が一直線で増加傾向にあるのだが、その大半は寝たきりによる誤嚥(ごえん)が元での肺炎の発症によるものである。やれ点滴だ、胃瘻(胃ろう)だ、人工心肺だ、といった無駄な延命治療で命を引き延ばされているのが現状である。こうした延命治療は、日本に特有なもので、欧米にはない。
2016.9.19 高齢者の仲間入りをしたら死に方を考えましょうよ
死にざまが物凄い御仁が明治時代にいました。それは山岡鉄舟です。52歳で胃がんで没。
1888年(明治21年)7月19日朝、鉄舟は「腹痛や 苦しき中に 明け烏(がらす)」と歌いながら朝湯につかり、上がると白装束に着替え、左手に数珠、右手に団扇を持って座りました。やがて、見舞いに来た勝海舟としばらく世間話をしていましたが、鉄舟はおもむろに「只今、涅槃に入る」と告げました。それを聞いた勝が「左様か、ではお心安く御成仏を」と言って辞去すると、鉄舟はそのまま座を崩さず、皇居の方角に向かっていつの間にか息を引き取っていたそうです。
死に際にその人の生きざまが凝縮されるとするならば、まさしく山岡鉄舟こそ「ラスト・サムライ」といえるのではないでしょうか。
山岡鉄舟、いやあー、恐れ入ります。
とても人間業とは思えません。そんなこと絶対に不可能だ、となってしまいそうですが、どっこい小生の身近にそれに近い方がいらっしゃいました。
その方は、80歳で肝臓がんで亡くなられたのですが、死の近くまで農作業をされ、「もうあかん、動けん」と言ってから20日後に息を引き取られました。がんだと分かっても誰に言うこともなく、医師の手当ても受けず、そして自分の死期を悟られたことでしょう。
2015.6.12 高齢者は死を恐れるなかれ。死はこの世の卒業式みたいなもの
ヒンドゥー教の僧侶は、自分の死期を知るとパーティーを催して別れの挨拶をし、瞑想に入ってそのまま亡くなるのが一般的だそうです。これを「マハーサマーディー」といい、人間はこのような死に方をするときは脳内麻薬が分泌され、至福のうちに旅たつことができ、最も自然な死に方と考えられているとのことです。
死生観を持っているかどうかということに関しては、世界で一番の“後進国”といえる日本です。そろそろここらで真剣に考えねばいかんでしょうね、特に団塊世代(小生はその真ん中)は。そうしないと、いい年こいて“まだ死にとうない!”と、宣ふ(のたまう)往生際の悪い年寄りで日本中があふれ返り、後世に「日本の歴史上、最低だった集団は団塊世代」との汚名をしっかり残すことになりましょうぞ。
2014.12.29 「自然死」のすすめ(中村仁一著)読後感想
いよいよお迎えが来たという状態になって何日であの世へ逝くかですが、中村氏は次のようにおっしゃっておられます。以下、引用します。
点滴注射や酸素吸入は、本人が幸せに死ねる過程を妨害する以外の何ものでもないと考えていますので、私は原則として、行いません。…
では、点滴注射もせず、口から1滴の水も入らなくなった場合、亡くなるまでの日数がどれくらいかといいますと、7日から10日ぐらいまで(最長で14日間)が多いようです。…(死に際には)38度前後の、時には39度5分くらいの体温上昇をみることがあります。…この時点で、本人はスヤスヤ状態なので、何ら苦痛はありません。…
よく「点滴注射のおかげで1か月生かしてもらった」などという話を耳にします。しかし、良く考えてみてください。点滴注射の中身はブドウ糖がわずかばかり入った、スポーツドリンクより薄いミネラルウオーターです。「水だけ与えるから、自分の体を溶かしながら生きろ」というのは、あまりに残酷というものではないでしょうか。…
「脱水」は、意識レベルが落ちてぼんやりした状態になり、不安や寂しさや恐ろしさから守ってくれる働きをすることは、すでに述べたとおりです。それなのに、たとえ善意にしろ、せめて水だけでも、と無理に与えることは、この自然のしくみに反し、邪魔することになるのです。…ひどい仕打ちだとは思いませんか。
たしかに、見殺しにするようで辛い、何もしないで見ているだけなんてことはできないという気持ちも、わからないではありません。しかし、こちら側の都合だけで、何かをするというのは、「エゴ」といっていいと思います。その行為は誰のため、何のためなのか、やった結果、どうなるのかを考える必要があります。
本人は嬉しがるか、幸せに感じるか、感謝してくれるか、あるいは自分だったらしてほしいことなのかなど吟味してみなくてはいけません。
たしかに私たちは、何もせずに見守ることになれていません。辛いことです。
だからといって、自分が苦しさや辛さから免れるために、相手に無用な苦痛を与えてもいいという道理はありません。「そっとしておく思いやり」もあるのです。
また、たとえ延命したとしても、悲しみはなくなりも減りもしません。ただ先送りするだけなのです。
フランスでは「老人医療の基本は、本人が自力で食事を嚥下できなくなったら、医師の仕事はその時点で終わり、あとは牧師の仕事です」といわれているそうです。…
もっとも、かくいう私も病院勤務時代に、…何とかしてほしいと頼まれ、いろいろ工作し…た経験が、いくたびもあります。
片棒を担いで、死にゆく人間を無用に痛みつけたわけですから、もし地獄というものがあるなら、当然地獄行きでしょう。皆さんの中にも、身に覚えのある方が結構おられると思います。地獄行き、ご一緒しましょうね。
(引用ここまで)
いかがでしょうか。中村氏は、ここでフランスの例を持ち出しておられますが、これはフランスに限らず、欧米諸国皆ほとんど同じ対応が取られており、点滴注射も胃瘻も原則として行っていないのが実情であることは、このブログで「寝たきり老人をなくす術(三宅薬品・生涯現役新聞N0.239)」で記事にしたとおりです。
日本人は、やれ点滴注射だ、やれ胃瘻だと、なぜに利己主義的対応を取るのでしょうかねえ。日本人ならば、仏教の教えにより、ちゃんとした「死生観」を持ち合わせていて良いように思うのですが、残念でなりません。
2013.9.10 延命治療を受けないためのリビングウィル(死の間際にどんな治療を望むかをあらかじめ示した書)を書く
「1日で治る患者を1日で治す医者は病院を首になる。1日で治る患者を1年引き延ばせば院長になれる。」というブラック・ジョークがあります。医師の間では知られたことのようでして、これ、まんざらウソではなさそうです。
もう一つのジョーク、『「最近「予防医学」が全盛ですが、その実態は「“患者を呼ぼう”医学」。医者の“おいしい”お客様にならないよう気をつけましょう。』と言っておられるのは近藤誠医師で、氏は慶応大学医学部“講師”の肩書きのままで、孤軍奮闘40年間頑張っておられましたが、病院を首になっても仕方がない行動を取っておられました。
そして、氏曰く:医者を40年やってきた僕が、いちばん自信をもって言えるのは「病院によく行く人ほど、薬や治療で命を縮めやすい」ということです。…「信じる者は救われる」と言いますが、医者を簡単に信じてはいけない。
そして、「本書では、医療や薬を遠ざけ、元気に長生きする方法を解説していきます。」と、表紙の裏面で言っておられます。その本は「医者に殺されない47の心得」(2012年12月 アスコム)です。
近藤誠医師は、本書を執筆するにあたって、巻末でご自身のリビングウィルを紹介なさっています。その少し前の部分から引用しましょう。
どんな延命治療を希望しますか?
リビングウィルのことが、最近よく話題になります。自分の死のまぎわにどういう治療を受けたいかを、判断能力のあるうちに文書にしておくことです。
日本では、リビングウィルにはまだ法的な力はありませんが、書いておくことで、意識を失ったあとも、家族や医師に、延命治療についての自分の意思を伝えられます。「鼻腔チューブ栄養のような、強制的な栄養補給は一切不要」「人工呼吸が1週間続いて意識が戻らなかったら装置をはずしてほしい」…など、自分で説明できなくなったときの「どう死にたいか」の希望を、なるべく具体的に書いて、身内の同意をもらい、毎年更新していきます。
よい機会なので、倒れて病院に連れ込まれたとき用のリビングウィルを書いてみました。家人や知人がわかるところに保管します。あなたも、書いてみませんか?(引用ここまで)
ところで、ここに紹介したブラック・ジョーク(まんざらウソではない)、これは、日本に特質的な薬漬け医療を言っているのであるが、下記の過去記事に如実に現れている。
2017.5.31 日本の抗がん剤、脂質降下剤、タミフルの投与量、みな世界シェア70%?!
米国の健康保険は民間会社が運営しており、庶民が一般に加入しているエコノミークラスの健康保険においては、その投薬指針として“血圧が常時180を超える場合においてのみ、それも安価な降圧剤(保険適用薬の限定)を処方してよい”となっているところもあるようですから、この種のタイプの健康保険加入患者には医師は日本のようにやたらめったら降圧剤を出せないのです。そして、65歳以上の高齢者となると、政府が掛金の大半を負担する健康保険に加入できるのですが、この健康保険は恒常的に飲み続ける生活習慣病の薬は保険対象外となっていますから、そうした薬が欲しい場合には別の健康保険にも加入せねばならず、これは掛金が高額なものとなり、そうした健康保険にも加入している高齢者の割合は1割程度にすぎないようです。
こうして、米国では、保険制度上で薬漬けが防がれています。
いかがであろうか、年寄り同士諸君。これを機会に、自分の死生観を確立しようじゃありませんか。で、「コロナでピンピンコロリもいいもんだ」と、思うようになりませんでしたか、年寄り同士諸君たちよ。
ことはついでですから、新型コロナに感染した重症者数が、単位人口当たり欧米の30分の1程度である日本で、医療崩壊の危機到来だと、ずっと騒がれているのはどうしてでしょうか。イタリアでは感染拡大初期に、たしかに医療崩壊の危機が訪れたのですが、その後は乗り切っています。
これは感染症に対する危機管理がしっかり構築されているからですが、その背景には、西欧では有史以来、民族間紛争が絶えず、相互侵略・殺戮が繰り返され、近代にあっては生物兵器が開発され、東西冷戦下にあっては高殺傷力のある細菌ばら撒きの恐れもありました。今日、ソ連が崩壊しても、その危険性は拭い去ることはできず、いざというときに備えての感染症病棟がしっかり確保されており、医療スタッフも充実していることです。
平時において、医師や看護師など医療スタッフは余裕をもって仕事ができる体制が整っており、今般のような感染症に対しても、臨機応変、他分野の医療従事者を感染症部門へ人員を大量に振り替えることができるのです。
ちなみに、日本の人口千人当たり医師数は2.4人で、OECD(経済協力開発機構)の加盟国平均は3.5人です。
そして、日本は、高齢者医療費の増大(無駄な薬漬けと無駄な老人病棟の拡充)をいたずらに放置し続け、その財政負担を少しでも和らげようと、ほとんど発生しない感染症の対処費用をばっさばさと切り捨て、欧米のような感染症に対する危機管理はどんどん外される傾向にあったのです。
感染症対策の切り捨ては、結核患者の減少を理由に〝感染症の時代は終わった〟として、1996年の橋本政権による構造改革路線によって本格化し、2001年に発足した小泉政権以降、公費投入の抑制のため病床削減や病院の統廃合、医師養成数の抑制を、医療の市場化・産業化と一体で、精力的に進められてきました。
その結果、全国の感染症指定病床は1998年に9060床あったのですが、その後の20年で1869床(2019年 4月現在)まで減少しました。また、重症の感染症患者の治療が可能なICU病床数(人口10万人当たり)は、ドイツは29.2床と世界的にトップクラスで、医療崩壊が起こったイタリアでも12.5床あります。それに比べ日本はたったの4.3床しか使えない。加えて、医師・看護師の絶対数が不足していて、臨機応変に感染症対応に人員を振り替えることも難しいことが、緊急医療体制の弱体化を招いています。
このように、日本の医療体制は、なんともお粗末な状態にあるのです。どうでもいい医療に力を注ぎ、肝腎な医療を放棄している、と言っていいでしょうね。今般の新型コロナ対策で、政府は単に付け焼き刃的な施策をとるのではなく、抜本的な医療制度改革に目覚めてほしいところです。
ものすごい長文となりましたが、読者の皆様方には最後までお付き合いいただきまして有り難うございます。どれだけかの参考になれば幸いです。