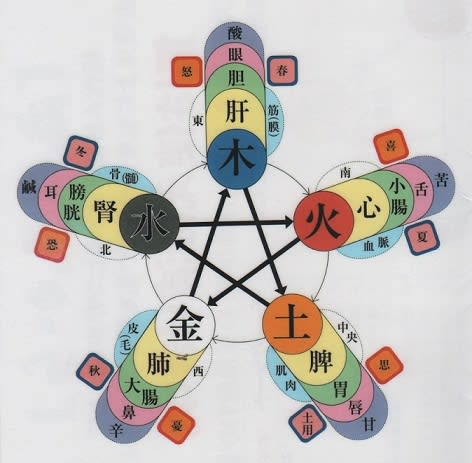がんとは無縁と高をくくっていた小生、ステージⅢの前立腺がんが見つかる。
(初稿2023.12.11 追記2023.12.22、2024.1.18)
15年前に還暦を迎え、これを第2の人生のスタートと捉え、それまでフルパワーで行っていた薬屋稼業生活を見直してファーマー・ファーマシーという半農半商生活を始めるとともに、自分の経験を元にして行い得る社会貢献に取り組んでいくことにしたところである。そして、高齢者となった65歳、後期高齢者となった75歳という節目にも、生活習慣と人生設計の見直しを行い、生涯現役をモットーとするも、何事もスローライフでいこうと心がけてきた。
そうしたことから、「がん」とは無縁と高をくくっていた小生であるが、今秋、尿の出の悪さから泌尿器科にかかったところ、ステージⅢの前立腺がんが見つかった。“えっ、なんで俺が”と、ビックリしたというか、あきれたというか、まったく恐怖感は生じなかったが、どれだけか複雑な気持ちにはさせられた。
さて、このがんとどう対処するか。がん全般の対処法に関しては、このブログで幾度か書いてきたのだが、いざ自分のがんとなると、少々面食らうことも生じた。やはり知識だけではなんともならない。実際に経験してみて初めて分かることも多いことを思い知らされたところである。
そうしたことどもを中心に、自分の経験を皆様にもお知らせし、参考にしていただければ、と思い、記事にしたところです。なお、この記事は、今までに別立てブログ「薬屋のおやじの“一日一楽”&“2日前”の日記」に投稿したものを一部編集して再掲したものです。
(2023年)
11.20 生き方を変えよう、自分の体にがんが見つかったんだから
還暦以降、年々ションベンの出が悪くなり、後期高齢者となった今年、この冬が乗り切れるか少々不安になってきた。そこで、わりと近くにあるH泌尿器科クリニックに掛かることにした。そこで処方された飲み薬(副作用はほとんどない)が即効的に効き、けっこう尿の出が良くなり、これでホッと一安心できた。
ところで、初回の検診でエコー検査があり、前立腺肥大が確認された。70歳以上の標準が20gに対して27gしかないから、そうたいしたことはないが。いっぽう膀胱は、だいぶボロボロになりかけているとのことで、説明はなかったが、頻尿はこのせいだと思われる。
そして、前立腺の腫瘍マーカー検査をするための採血をする。翌週に結果が出て、標準が4.0ngに対して11.99ngと出た。これは前立腺がんの可能性の指標となるも、加齢による数値上昇もあり、これだけではとうてい判定は下せない。そこで、M総合病院でのMRI検査を受けることになった。
MRI検査の結果は1週間後に出て、片方の前立腺にはっきりとした腫瘍が認められた。そう大きなものではなかったが。これで前立腺がんが確定したと思いきや、「強い疑いがある」だけのことで、最終的な診断を下すためにとのことでHクリニックで生検(調べてみたら、がん診断の正確性はMRI検査より劣るようだが)を受けることになった。これは、手術とそれほど違いのない大掛かりなもので、片方の前立腺から6か所、両方で12か所もの組織サンプルを採取するもので、部分麻酔を打たれ、検体採取後は足がもつれて車椅子に介助してもらって乗り、麻酔が切れるまで3時間ベッドに横になっていなきゃならんかった。もう生検なんてこりごり。
さて、その生検の結果が出たのが今日。医師から前立腺がんの確定が宣告され、グリソンスコアなるもの(下調べしておいたが、説明を受けてもどんなものかよく分からん)からして、悪性度は5段階のうち4段階目に高いとのことであった。
これで、医師の治療方針が下されるかと思いきや、けっこう悪性だからリンパ節や骨に転移している恐れもあり、そちらのほうを検査する必要があるからと、再びM総合病院へ行って専門医に診てもらえるよう手配がなされた。検査、検査で、もううんざりするのだが、自分の体がどうなっているのか、これを知っておくのも良かろうと受けることとした次第。
Hクリニックの医師が言うには、転移の有無を踏まえて治療方針を提示するとのことであり、まだ先のことになるが、自分の治療方針は女房とも相談して既に決まっている。それは「がんとの共生」であり、そのためには「生き方を変えよう」というもの。
11.26 「がんとの共生」のために「生き方を変えよう」と考えたのだが…
「11.20 生き方を変えよう、自分の体にがんが見つかったんだから」で記事にしたのは前立腺がんが見つかった、その経緯だけであり、これに今後どう対処していくかについては、具体的には何も書かず、次の一言で済ませた。
「がんとの共生」であり、そのためには「生き方を変えよう」というもの。
薬屋家業をするなかで、これまで20年以上、がんに関して幾冊かの本を読み、ネット情報を拾ったりするなかで、がんは無治療でいったほうがいいと感じた小生である。つまり、がんは、外部からの侵入者・せん滅すべき対象では決してなく、自らの体の一部であって「がんとの共生」をすべきものであり、がんがこれ以上暴れることなく、おとなしくしてくれる、これを願ったほうがいいと思うようになったのである。そうすれば、場合によっては、がんが自然と縮小してくれることさえあるようだ。
そのためには、今まで頑張りすぎてがんになったのであろうから、まずは自分を自分で褒めてあげようじゃないか、「今までよう頑張って来たな。ご苦労さん。褒めてつかわそう」と。そして、これからの人生は「生き方を変えよう」じゃないか、と過去を振り返って生活習慣全般を見直し、心身ともに無理がかからぬようにすることは当然のことながら、何か前向きな明るく楽しい人生のスタートを切る、となるようにせねばいかんだろう。
早い話、「がんになってよかった。新たな生きがいのある人生が始められた。」となればいいのである。けっこう多くの方が、そうやって「がんとの共生」をされているようだ。こうしたことを、少しばかりのお客様ではあるが、がんを患った方々に対応してきた。
さて、過去を振り返ってみての生活習慣全般の見直しは、すでに女房と相談し、おおよその方向性はまとまった。そのなかで、自分は決して頑張ってもいない、無理もしていない、という意識であったものが、他人から見れば、頑張りすぎ、無理しすぎ、ということが多々あるようなのである。ここは、素直にその意見に従って、出力ダウン(半分の出力にしたいのだが、なかなかそうはまいらぬが)を一つひとつの事柄について実行あるのみ、ということにして、取り組み始めたところである。これの具体的なことは後日順次記事にしよう。
ところが、何か前向きな明るく楽しい人生のスタートを切る、という「生き方を変えよう」という課題については、はてさてどうしたらいいのだろう?
これが、なかなか思いつかないのである。
薬屋という稼業は“暇つぶし、ボケ防止”のためにも女房と二人で続けたいし、百姓仕事は小生一人でやっているのだがこれも続けたい。ファーマー・ファーマシーの二足のわらじはいいものであり、両方の仕事はまだまだやりたい。ほかにアパート管理があるが、下駄ばきアパートの一角での薬屋稼業につき、これは稼業と一体のもので、引き続きやらねばならぬ仕事である。趣味としては、自然科学の分野、今では社会科学の分野にも広げ、幅広く論文(といっても小論だが)を執筆している。なお、これらについては、ホームページやブログを立てて発信し続けている。
これら(ちょっと多すぎるきらいがする)を引き続きやりながら「生き方を変えよう」としても、選択の幅はだいぶ狭められてしまう。頑張りすぎという量的な問題は、先に記したように出力ダウンでけっこう解決するだろうが、「生き方を変えよう」という質的な問題となると、はてさてどうしたものか、なかなか思いつかないでいる今日現在。
稼業の質を変える、百姓仕事の質を変える、アパート管理の質を変える、論文執筆の質を変える、なんて、どうやったらいいのか。こうした課題については、すでに何年も前から取り組み、けっこう変えてきているつもりだから、妙案が浮かばないでいるのである。
こうしたことをあんまり考えすぎると、かえって心的ストレスがたまり、逆効果となりかねない。今まで何人かのお客様に「生き方を変えよう」と無責任に、気楽に言ってきたが、はてさて自分のこととなると、“弱った、どうしたらいいんだろう?”となってしまった。
ここは、何か発想の転換をせねばいかんだろう。これは、あせってもできるものではない。そのうち何か閃くのをしばし待つことにしよう。
ところで、通常、医者から「あなたはがんの恐れあり」とか「あなたはがんになっています」とか言われると、“ガ~ン”と心が打ち砕かれて、シオシオッとなってしまいそうだが、小生の場合は、全然そうした気分にはならなかった。
医者から最初「がんかどうか検査しましょう」と言われたとき、“自分ががんに罹っているなら、み~んな、がんになっとる。肉体的ストレスも精神的ストレスも、自分はう~んと少ないんだから。”と高をくくっていたのだが、こうして自分だけが(とまでは言わないが)選ばれた存在になったとき、自分では意識していなかったが、“自分は人よりも肉体的・精神的ストレスが多くかかっていたんだろうなあ、きっと。”という気分になっただけで、恐怖心は全く湧かなかった。
“少しはがんを怖がれよ”といったところだが、これまたどうしたことか。暇ができたら、これについても書いてみよう。
12.1 一通りの前立腺がん検査がやっと終わり、治療方針の提示を受け、対処法を決定
小便の出の悪さが気になってH泌尿器科に掛かり始めたところ、あれこれ検査され、前立腺がんであることが判明し、すでに転移している恐れもあるとのことから、M総合病院送りとなり、またまた検査があり、全部で6つの検査でもって、やっとM総合病院の専門医から治療方針の提示を受けることができたのが、今日、12月1日。今までの検査を順を追って記録に留めておこう。
(10月12日)
H泌尿器科での初診時にエコー検査があり、これは瞬時に分かるもので、「前立腺が標準値20gであるのに対し、27gと肥大している。膀胱もけっこうボロボロになりかけている。」という説明を受けた。
“前立腺の肥大はたいしたことないじゃないか”というのが小生の印象。でも、小便の出の悪さと前立腺の肥大は必ずしも因果関係があるわけではないようだ。
(10月26日)
初診時に血液採取があり、その結果が出て、H泌尿器科医が「腫瘍マーカー(PSA値)が標準値4であるのに対し、あなたは11.99と高い値が出た。ここはMRIを撮って腫瘍の有無を調べましょう。」ということになった。
(11月8日)
M総合病院でMRIを撮る。これは割と簡単に済む。
(11月10日)
その画像データを持参してH泌尿器科へ行き、「がんの疑いあり」ということで、後日、生検を受けることになった。
(11月13日)
H泌尿器科で生検。これが大変。部分麻酔を打って、両側の前立腺の各6か所からサンプル採取。麻酔が切れるまで3時間寝かされ、その後で尿の採取。検体採取で炎症を起こしている前立腺ゆえ、尿の出がとんと悪く、ポタポタとしか尿が出ない。“これじゃあダメだから、管(くだ)を差して尿を取ろうか”と医師が言うも、“時間かけりゃ何とか出るから、管を差すのはご勘弁願いたい”と申し出て、事なきを得る。
しかし、その後、2~3日間は尿の出が、いと悪し。生検はもうこりごり。
(11月20日)
H泌尿器科で生検の結果を聞く。これで前立腺がんが確定した(といっても、断定できるものではなく、かなり高い確率でがんであるということになる)のだが、前立腺がんの場合は、リンパ節への転移と骨への転移の恐れがあるから、M総合病院でこの2つの検査を受けるよう促され、その検査を受けることにした。
(11月24日)
M総合病院の専門医から、小生の、今までの検査から言える、前立腺がんの状態のある程度詳しい説明(H泌尿器科医からは簡単な説明しかなかったが)を受け、転移の有無を調べる2つの検査の日程を決める。
(11月27日)
M総合病院でリンパ節転移を調べるためにCT検査。造影剤の静脈注射があったが、割と簡単に済む。
(11月29日)
M総合病院で骨への転移を調べるためにシンチ検査(骨シンチグラフィー)。早朝に造影剤の静脈注射後、いったん帰宅し、3時間後に再度来院し検査。これも割と簡単に済む。
これで一連の6つもの検査が終了し、今日12月1日、M総合病院の専門医から治療方針の提示(11月24日の説明を含む)を受けることとなった。
まずグリーソンスコア。前立腺がんの悪性度を評価する指標。生検で採取した組織を顕微鏡で検査したところの組織分類を言うというものだが、片方の6検体は全部陰性だが、もう片方は1検体が陰性だが、5検体が概ね同じでグレードが高く、悪性度は5段階分類で第4段階にあり、悪性度は高いと評価された。時に転移を生ずる恐れあり、という段階にある。
次にTNM分類。
前立腺がんの広がり・進行度や転移の有無から、がんの病期を評価するもの。
T:がんの広がり(T1~T4の4段階)のうち、第3段階にあり、広がりは大きい(前立腺の被膜を越えて精嚢へ少しだけ浸潤している)。
N:所属リンパ節への転移の有無 → CT検査の結果、転移無し
M:遠隔転移(所属リンパ節以外のリンパ節、骨、それら以外)の有無
→シンチ検査の結果、転移無し
TNM分類を分かりやすく分類したもの
病期A(ステージⅠ) 偶然に発見された小さながん
病期B(ステージⅡ) 前立腺の中に留まっているがん
病期C(ステージⅢ) 前立腺の被膜を越えて浸潤しているが転移は無いがん
病期D(ステージⅣ) 転移がみられるがん
小生の場合は、「病期C(ステージⅢ)」との判定。
して、その治療方針の説明は次のとおり。
まずはホルモン療法により前立腺がんの増殖を抑制する。ついで放射線療法によるがん巣の削除、場合によっては前立腺(浸潤の恐れのある精嚢も)の除去手術。
ホルモン療法は早速やったほうがいいと考える。
以上の提案がなされ、いかがされるかと問われた。小生のそれに対する回答は、次のとおり(11月24日の説明時に大雑把に行った回答を含む)。
後期高齢者となった今、これまで75年と、もう十分に生きてきたから、早々にがんで死んでもいい覚悟はできている。
年を重ねるにつれ、脳梗塞を患う恐れが高まってくる。脳梗塞でピンピンコロリと逝ければ最高だが、そううまくはいかず寝たきりになる恐れが大であり、そうなると家族に多大な迷惑をかける。脳梗塞にならなくても、長生きすれば認知症にかかる恐れもあり、これも家族に多大な迷惑をかける。
そうなる前に、がんで死ねたほうがありがたい。がんはそう苦しまずに、しっかりした意識を持ったまま死ねると聞いているから。
よって、なんら治療をせず、がんと共生しつつ、この世を去りたい。
と、まあ、こんな希望を出し、M総合病院の医師から了承をいただいた。
なお、検査結果や小生の希望は、かかりつけ医のH泌尿器科へ伝えていただけることになり、後日、今飲んでいる薬(尿道を拡張するもの)がなくなりかけたところで、H泌尿器科の医師を訪ね、今後の経過観察法を決めることとした。
(12.22追記)
昨日、かかりつけ医のH泌尿器科へ行ったところ、ホルモン療法を進められるも、これはお断りし、「前立腺がんはなんら治療せず」でいくことが決定した。
12.7「がんとの共生」のために生活習慣全般を見直そう
11月26日に次のように書いた。
今まで頑張りすぎてがんになったのであろうから、まずは自分を自分で褒めてあげようじゃないか、「今までよう頑張って来たな。ご苦労さん。褒めてつかわそう」と。そして、これからの人生は「生き方を変えよう」じゃないか、と過去を振り返って生活習慣全般を見直し、心身ともに無理がかからぬようにすることは当然のことながら、何か前向きな明るく楽しい人生のスタートを切る、となるようにせねばいかんだろう。(中略)
さて、過去を振り返ってみての生活習慣全般の見直しは、すでに女房と相談し、おおよその方向性はまとまった。そのなかで、自分は決して頑張ってもいない、無理もしていない、という意識であったものが、他人から見れば、頑張りすぎ、無理しすぎ、ということが多々あるようなのである。ここは、素直にその意見に従って、出力ダウン(半分の出力にしたいのだが、なかなかそうはまいらぬが)を一つひとつの事柄について実行あるのみ、ということにして、取り組み始めたところである。これの具体的なことは後日順次記事にしよう。(再掲ここまで)
今日は「生活習慣全般の見直し」について具体的なこと記事にしよう。女房と相談しながら、今までに考えついたことは次のとおりである。
まずは稼業の薬屋(化粧品、たばこ販売を兼業)関連
①休業日を2日から3日に5割増し
7年前、女房が高齢者(65歳)になったのを機に休業日を完全週休2日にし、日・月曜連休としたのだが、それを一歩進め、来年1月から土・日・月曜3連休とする。これによって、営業中の緊張感持続による精神的疲れが緩和されようし、休日に行う百姓仕事を“のんびりゆったり”こなせるようになる。
②年齢識別&新札対応たばこ自販機の導入決定
タスポが間もなく使えなくなり、運転免許証かマイナカードで年齢識別することになり、併せて新札発行となるから、新機種のたばこ自販機の導入が迫られる。1台80万円もして採算が取れないが、店頭販売は手間がかかり負担となるから、新機種の導入を決定し、楽することに。なお、自販機は2台あるが、新機種導入を機に1台に統合する。
③店頭花壇の永久撤去
この夏、あまりに長期間猛暑が続いたせいで、店頭花壇のプランターに植え込んでいた夏の草花の多くが枯れてしまい、いったん撤去した。冬の草花を飾る時期に花壇を再開するつもりでいたが、草花の世話はけっこう手間がかかるから、店頭花壇は永久撤去することに。
④石油ストーブの新設
厳冬期にはエアコンの暖房能力が落ち、店内は寒い。着込んだり、カイロを貼ったりせねばならぬ。快適な暖かさにするため、そうした日には石油ストーブを補助的に使い、寒さ我慢をしなくてすむよう、アラジン型の石油ストーブを置くことにしよう。ストーブ周りでお客様と話をするのも、また楽し、であるゆえ。
次に、アパート管理があるが、下駄ばきアパートの一角での薬屋稼業につき、これは稼業と一体のものとなるが、改善事項は次のとおり。
①リフォームをしない
築50年を過ぎたアパートであり、空き部屋は6室あるも、もうリフォームはしない。近隣にけっこう新築アパートがあり、新規入居者は見込めないから。
②新規入居者は基本的に入れない
1階の店舗従業者用に使っていた2室が空いているが、これ以外には新規入居者は入れないことにする。なお1室きれいな部屋があるが、これは何かの非常用に残しておく。
3つ目は、百姓であるが、10年ほど前から省力化を検討し、2年ほど前から本格的に「手抜き農法」に取り組んでいる。それをさらに一歩前進させることに。
①丸一日の農作業を半日化
今までフルパワーで丸一日農作業をすることが多かったが、肉体的ストレス軽減のため、半日で切り上げることにする。店の休業日を週2日から3日にしたことによって、これは実現できよう。なお、予定した百姓仕事がこなせないときは、店の営業日を遠慮なく使うことにしよう。月初め以外は店は暇だから。
②畑全面作付けを順次縮小
自宅前の畑(果樹園を含む)と須賀前の畑、ともに約400㎡あり、体力的に持て余し気味となってきている。来季の夏野菜から空き畝を順次作り、畑の淵と同様に草刈機による草刈管理だけの畝を増やしていこう。
③苗づくりを順次廃止
夏野菜の苗づくりで手間のかかるもの(白ナスが群を抜いて手間がかかる)を順次廃止し、苗購入で代替する。
④株間の拡大
今まで単位面積当たりの収量を十分に上げようと、株間を気持ち狭くしていたが、これを広く取り、作付けの手間を減ずることにする。
⑤新規栽培品種の作付けはしない
落花生を予定していたが、止め。今後とも新規栽培品種の作付けはしない。
⑥果樹の本数及び樹形の縮小
果樹は剪定作業が必ず必要で、特に柿の木が面倒だ。先日庭師に1本伐採してもらったが、毎年1本伐採し、柿の木は無しにしよう。柑橘類と梅の木は毎年の剪定が楽になるよう、樹形の縮小をしよう。
以上、ここに強く宣言しておく。
こうでもしないと、①以外は反故にしてしまいそうだから。
4つ目は、情報発信に関すること。当店お客様へのDMは欠かせないから、これは引き続き行うが、ホームページやブログ(8本)の更新は極力減らす。
今まで、新規の情報を頻繁に発信しようと悪あがきしてきた感がする。ここは背伸びしないことだ。冷静になって考えてみるに、精神的ストレスがかかりすぎているのではないか。
毎日のように発信するのは“一日一楽日記”だけにし、後は順次「休止」へ。
以上が、現時点での生活習慣全般の見直しであるが、これをきっちり実行すると、“暇で暇で困ってしまう”となりゃせんか。何かやっていないと落ち着かない、という性分ゆえ、そのように危惧されるところである。
何か新たな趣味でも作って穴埋めするとなると、毎日が忙しくなって、元の木阿弥となってしまうだろうし…。困ったことだ。
ここは、一つひとつの作業を「ゆっくり、のんびり」やって時間を潰すしかないか。ということで、何事も「ゆっくり、のんびり」することにしたいが、加えて何事も「楽しく」やっていきたいもんだ。
12.9「がんとの共生」のため「生き方を変えよう」 第1弾は「週休3日」の有効活用
小生の前立腺がんは、医師の判定では「悪性度は5段階分類で第4段階と高い。病期は4段階分類でC(ステージⅢ)と高い。」というものだが、他のがんと違って、前立腺がんは一般に進行が極めてゆっくりなようである。
男の場合、がん罹患数のトップ4は、前立腺、大腸、胃、肺で、他の部位を大きく引き離している。死亡数は、肺がダントツで、大腸、胃と続き、これがトップ3で、がん死全体の5割を占める。以下、膵臓、肝臓、そして前立腺と続き、前立腺は全体の6%。この統計からしても、前立腺がんは「罹患すれど死ぬことはさほどでない」となる。
病期が一番上の段階「D(ステージⅣ)=転移がみられる」であっても、5年相対生存率は65.6%、10年相対生存率は45.0%と高く、そうそう死ぬものではない。小生のステージⅢにあっては、10年相対生存率は98.5%と“死ぬことは極めてマレ”となる。しかし、前立腺がんの死亡者数はけっこうあり(がん全体の6%)、ステージⅢがやがてステージⅣに進んでお陀仏となる可能性は、ままあることになろうというもの。
さて、ステージⅢのがんが見つかったところで、今までどおりの生き方、生活習慣を続けていけば、やがてステージⅣへ進むと考えたほうがよかろうし、ここで「生き方」と「生活習慣」を改めれば、がんはステージⅢで留まってくれる、と考えてよかろうというものだ。
「生活習慣」の見直しについては、11月26日の記事に書いたように、これは容易なのだが、「生き方」を見直して「生き方を変えよう」というのは、具体的にどうすればいいのか、容易には思いつかないでいた。
小生は、65歳になった頃に、仕事は無理せず、楽しく毎日を過ごそうと、この“一日一楽日記”を付け始め、心身ともにストレスから解放された人生を送ってきたつもりであり、もう10年も前に「生き方を変えよう」を実践してきたつもりでいるのである。ここにきて、この10年とはまた違う形に「生き方を変えよう」としても、すでに実践済みなんだから…となってしまい、新たな質の異なる「生き方」はそうそう思いつくものではない。
ところで、「生活習慣」の見直しについては、「12.7「がんとの共生」のために生活習慣全般を見直そう」で具体的にあれこれ書いて、今、実行しつつある。
その最大のものは、来年1月からの薬屋稼業の休業日数増大である。7年前に女房が高齢者になったときに完全週休2日にしたのだが、もう1日増やして週休3日にすることにしたことだ。今までの日・月曜日に土曜日を加え、毎週「土・日・月曜日」の3連休にするというもの。
さて、1日増えて5割増しとなる休業日を何に使うか。
これをあれこれ思いめぐらせていたところ、“そうだ、毎月1泊2日で女房と湯治にでかけりゃいいんだ!”と思いついた。夫婦そろって温泉大好きであるゆえ。今までは年に4回ほどしか出かけられなかったが、これは、女房も慢性心不全という病を抱えているがゆえ、連休日に計画的に家事雑用をこなすも、1泊旅行で2日間つぶれてしまうと他の週に家事雑用がシワ寄せされ、体力的能力いっぱいいっぱいになってしまうゆえ、毎月はとても出かけられなかったのである。それが、週休3日となれば、家事雑用に余裕ができて、毎月湯治に出かけられるというものだ。
女房にそう話をしたら、“いいわね、出かけられるわ、楽し~い!”との返事がすぐに返ってきた。“さあ、どこへ行こうか。計画するだけでワクワクする!”
ここで思った。“楽し~い!ワクワクする!”ということが「生き方を変えよう」ということに直結するのではないか、と。今まで、そうそう“楽し~い!ワクワクする!”という出来事がなかったのだが、“楽し~い!ワクワクする!”ということが頻発すれば、それは「生き方を変えよう」ということになった証拠、と言えるのではないか。
こうして、「がんとの共生」のため「生き方を変えよう」 第1弾は「週休3日」の有効活用。まずは、これをオーバーに喜んで、“楽し~い!ワクワクする~!”と、子供のように大はしゃぎすることにしよう。
そして、なかなか思いつかないでいるが、“楽し~い!ワクワクする!”第2弾を、またゆっくり考えようじゃないか。
12.10「がんとの共生」をするために漢方薬と健康食品をしっかり飲もう
自分の体に見つかった前立腺がんとの「がんとの共生」をするために、以前からどれだけかは飲んでいる漢方薬と健康食品を、この際、全面的に見直しを行い、良いものをしっかり飲むこととした。
今まで、がんにいいものをあれこれ飲んでいれば、がんに罹ることはない、と勝手に思っていたのだが、そうは問屋が卸さなかった。
銀杏葉エキスは抗酸化作用が強いからがん抑制になる。マルチミネラル(特に亜鉛とセレン)は免疫強化になるからがん抑制になる。クルクミン(吸収効率のいいナノ粒子)は抗がん作用がある。各種文献でそのような臨床データが出ているようだ。
今まで、これらを別目的で飲んできた。自分の体にいいというよりは、お客様に当店推奨品として力を入れて売っているから、その手前、自分も飲まなきゃお客様に申し訳ない、といったことからである。しかし、小生はがんに罹患したのだから、抗酸化や免疫強化などはたいして当てにならないことを思い知らされた、といったところだ。
自分の体の欠陥としては、排尿障害(尿の出が悪い、頻尿)があり、これに関しては、八味地黄丸(これに2味を足した腎氣丸)とペポカボチャの種(食品:ナッツ)、そして間接的に効く鹿茸&紅参(腎の滋養)をしっかり飲んできた。この3つの組み合わせは、まあまあどれだけかは効く感がしていた。
ところで、当店のお客様で、もう10年ほど前のことであるが、前立腺がんを患い、リンパ節への転移もしていた80歳の方(5年生存率6割強)の息子さんから、医者が出す薬や手術などの治療なしで長生きできる方法はないかと相談があり、4点セットをお勧めした。
①がん患者はたいてい低体温になっているから、体を温める力が強いエゾウコギ(俗称:シベリア人参)製剤
②あらゆる健康の基本は腸内環境の改善(免疫適正化と腸内発酵による体温アップ)にあるから整腸剤(酪酸菌を含むもの)
③代謝アップと免疫力を高めるための総合ミネラル剤
④ストレスで大発生する活性酸素を消す銀杏葉エキス
4点ともなると、なかなか毎日ずっととは参らず、途中から第1に必要とする①エゾウコギ製剤のみになってしまったが、親父さんの体調がぐ~んと良くなったようで、3年後には、がんの心配はしなくてよくなり、もう何もいらない、と息子さんから連絡があり、その後の親父さんのがんの状態は分からなくなったが、低体温解消だけでけっこう効果があると感じた次第である。
その後、がん相談のお客様はそう多くはないが、第1に低体温解消を強くアドバイスしているところである。もっとも、「がんとの共生」さらには「がんの消滅」へと持っていくには、心の持ち方が最重要で、がんと戦うのではなく、がんと仲良くし、さらには「がんになって良かった」と感じる、これは「生き方を変えよう」がうまくいった結果ということになろうが、そうした心のケアに重点を置いてきたが。
さて、小生の前立腺がんであるが、このがんは他のがんに比べておとなしいがんである上に、小生の進行度は4段階の3番目であって、10年生存率は100%に近く、余命いくばくもない年(75歳)になっているんだから何も心配するものではない。
でも、薬屋という稼業を行っているのだから、あれこれ漢方薬と健康食品を使って、あわよくば「がんの消滅」ができないか、その臨床実験をするのも面白かろうと、しっかり漢方薬と健康食品を飲むこととしたところである。
まずは、がんのお客様にお勧めしている4点セット
①体を温める力が強いエゾウコギ(俗称:シベリア人参)製剤
加齢とともに低体温傾向になっているのは間違いなく、今までほとんど飲んだことがなかったが、しっかり目安量どおり(または5割増し)飲むこととした。
②整腸剤(酪酸菌を含むもの)
自家採取の野菜を毎日たっぷリ食べているから腸の調子はいいようだから、整腸剤は今まで飲んだことはないが、より腸内環境をよくするために毎日目安量どおり飲むことにした。
③代謝アップと免疫力を高めるための総合ミネラル剤
従前どおり毎日1回目安量を飲む。
④ストレスで大発生する活性酸素を消す銀杏葉エキス
従前どおり目安量の2倍を毎日、朝晩2回に分けて飲む。加えて、晩に飲むものには抗がん作用があるクルクミン(吸収効率のいいナノ粒子)も配合されている。
これらの他に、排尿障害(尿の出が悪い、頻尿)に関するものも見直しをした。
①八味地黄丸(これに2味を足した腎氣丸)
従前どおり満量を毎日3回飲む。
②ペポカボチャの種(食品:ナッツ)
夕飯時にけっこうな量を毎日を食べているが、満腹になりすぎるから、そのエキスに他の有効成分(体を温める等)を加えた健康食品に切り替えることにした。
③間接的に効く鹿茸&紅参(腎の滋養)
従前どおり毎日しっかり(満量の少なくとも半分)を飲む。
これに加えて、健康保持に飲んでいる漢方薬や健康食品の見直しをした。
①筋肉の保持と強化のための健康食品
これは百姓を続けるために飲んでいるもので、HMBCaを主成分とする筋肉強化のためのものと、筋肉・関節の原料となるコラーゲンを引き続き飲用。
②肝機能などの維持のための健康食品
田七人参(三七人参)を主成分とする漢方薬(扱いは健康食品)1日1包を毎日飲んでいたが、満量の2包に増量して飲用することに。
③体(特に細胞)の若返りのための漢方薬と健康食品
亀の甲羅、鹿の角などを配合した漢方薬(扱いは健康食品)を目安量どおり飲んでいるが、これを引き続き飲む。この他に、米発酵エキス、牡蠣エキスなど5成分を配合した、新たな健康食品を目安量の半量飲むことにした。
④高血糖抑制健康食品
ヤーコン茶を毎日少量飲んでいただけだが、ヤーコン葉+桑葉エキス粉末を1日1包(食事は夕食の1回しか取らないゆえ)飲むことにした。
さて、以上のもろもろに加えて、漢方で最高の高貴薬「牛黄」も飲むことにした。牛黄は滋養強壮薬の王様ともいえる生薬で、消炎効果も高く、がんの進行を食い止めてくれる効果も期待できようというもの。その牛黄は中国で需要が増大している上に投機対象になっており、価格は高騰を続けていて、メチャ高価なものとなってきているが、牛黄製剤(牛黄+人参)を、満量の半分(朝2カプセル)を飲むこととした。
これからは随分といっぱい飲むことになるが、全部の価格はしめていくら?となると、牛黄製剤だけで1か月分約6万円にもなる。これにはビックリさせられる。当店のお客様で牛黄製剤を疲労回復(即効的に効く)のためにときおり飲んでおられる方が2名いらっしゃるが、1か月3万円くらいのもの。もっとも、我が女房となると、慢性心不全を抱えているゆえ、心臓の苦しさから脱却するために1日3カプセルを飲んでいるが。
で、小生の場合、全部で1か月分いくらになるかというと、計算するのが怖い!
まあ10万円は軽く超えるということにはなろうが、牛黄製剤で体はきっと元気この上ないとなろうし、がんのほうも少なくとも現状維持で留まってくれると思う。そう考えれば10万円は高くない、と言えよう。同業者には、月20万円もお買い上げいただけるお客様もざらにいるというし、本人(経営者)でそのくらい飲んでおられる方も何人かいらっしゃる。それに比べれば、おやさしいもの。
牛黄製剤を飲み始めて2週間になるが、体が元気になったのを実感している今日この頃である。おおいに健康に投資しよう! 半分、破れかぶれだが。
(2024年)
1.17 「がんとの共生」のため「生き方を変えよう」 第2弾は「同級生と遊び惚けよう」
薬屋家業をするなかで、これまで20年以上、がんに関して幾冊かの本を読み、ネット情報を拾ったりするなかで、がんは無治療でいったほうがいいと感じている小生である。
つまり、がんは、外部からの侵入者・せん滅すべき対象では決してなく、自らの体の一部であって「がんとの共生」をすべきものであり、がんがこれ以上暴れることなく、おとなしくしてくれる、これを願ったほうがいいと思うようになったのである。そうすれば、場合によっては、がんが自然と縮小、消滅してくれることさえあるようだ。
そのためには、きっと今まで頑張りすぎてがんになったのであろうから、まずは自分を自分で褒めてあげようじゃないか、「今までよう頑張ってくれたな。ご苦労さん。褒めてつかわそう。ありがとう。」と。
そして、これからの人生は「生き方を変えよう」じゃないか、と過去を振り返って生活習慣全般を見直し、心身ともに無理がかからぬようにすることは当然のことながら、何か前向きな明るく楽しい人生の再スタートを切る、となるようにせねばいかんだろう。
早い話、「がんになってよかった。新たな生きがいのある人生が始められた。」となればいいのである。けっこう多くの方が、そうやって「がんとの共生」をされているようだ。
「生活習慣」の見直しについては、11月26日の記事に書いたように、これは容易なのだが、「生き方」を見直して「生き方を変えよう」というのは、具体的にどうすればいいのか、容易には思いつかないでいた。
小生は、65歳になった頃に、仕事は無理せず、楽しく毎日を過ごそうと、この“一日一楽日記”を付け始め、心身ともにストレスから解放された人生を送ってきたつもりであり、もう10年も前に「生き方を変えよう」を実践してきたつもりでいるのである。ここにきて、この10年とはまた違う形に「生き方を変えよう」としても、すでに実践済みなんだから…となってしまい、新たな質の異なる「生き方」はそうそう思いつくものではない。
ところで、「生活習慣」の見直しについては「12.7「がんとの共生」のために生活習慣全般を見直そう」で具体的にあれこれ書いて、今、実行しつつあるが、その最大のものは、今年1月からの薬屋稼業の休業日数増大である。7年前に女房が高齢者になったときに完全週休2日にしたのだが、もう1日増やして週休3日にすることにしたことだ。今までの日・月曜日に土曜日を加え、毎週「土・日・月曜日」の3連休にするというもの。
そこで、1日増えて5割増しとなる休業日を何に使うか、これをあれこれ思いめぐらせていたところ、“そうだ、毎月1泊2日で女房と湯治にでかけりゃいいんだ!”と思いついた。夫婦そろって温泉大好きであるゆえ。今までは年に4回ほどしか出かけられなかったが、これからは時間的余裕ができて、これが実現できそうだ。
女房にそう話をしたら、“いいわね、出かけられるわ、楽し~い!”との返事がすぐに返ってきた。“さあ、どこへ行こうか。計画するだけでワクワクする!”
ここで思った。“楽し~い!ワクワクする!”ということが「生き方を変えよう」ということに直結するのではないか、と。今まで、そうそう“楽し~い!ワクワクする!”という出来事がなかったのだが、“楽し~い!ワクワクする!”ということが頻発すれば、それは「生き方を変えよう」ということになった証拠、と言えるのではないか。
こうして、「がんとの共生」のため「生き方を変えよう」 第1弾は「週休3日」の有効活用。まずは、これをオーバーに喜んで、“楽し~い!ワクワクする~!”と、子供のように大はしゃぎすることにしよう、ということに相成った。
さて、なかなか思いつかないでいた“楽し~い!ワクワクする!”第2弾は、昨年12月に小学校の当地区在住の同級生と(わずか3人だけであるが)、急遽行った忘年会がほんと楽しかったことから、こうした会を頻繁に開催し、「同級生と遊び惚けよう」と思いついた。
そのきっかけは、昨年10月に小学校下の男だけでの飲み会(約10人)を行ったのだが、その会で「来年からは奇数月の第3日曜日の10時に小学校下の男だけ集まって喫茶店で懇談する」ことになったことだ。そのときは、年に6回も日曜日が半日も潰れ、百姓仕事に支障が出るからと、あまり乗り気ではなかったが、店の定休日を1日増やしたから、これは十分に対応できることになり、今では大乗り気と小生の心が変異した。
でも、これだけでは、いかにも少なすぎる。もっと行事を増やさなきゃ。
偶数月にも何か計画したほうがいい。10月の飲み会は料理好きなS君宅でバーベキューを行ったのだが、これは8月にやればいい。S君も了承済みだから。他の月は、例えば一部の者で麻雀を打ったり、魚釣りに出かけたり。これは奇数月の喫茶店での懇談のとき決めればいいじゃないか。
こうした“楽し~い!ワクワクする!”ことを大いに計画すると、“こりゃ面白い”となる。「がんになってよかった。新たな生きがいのある人生が始められた。」となるは必至。
以上は、地元小学校の「同級生と遊び惚けよう」であるが、同級生は他にもいる。大学時代の寮の同級生が首都圏に何人かいる。彼らと少なくとも年に1回は飲み会をやりたい。地方から参加するのは小生と京都在住のT君となろうが、幹事のN君に頼めば二つ返事で開催が決まるだろう。それと、しばらく中断している寮生同窓会の再開だ。これは幹事のO君から、先日、10月開催の案内が来たから、これも楽しみにしている。
同級生は皆、後期高齢者になったんだから、片足を棺桶に突っ込んだ輩ばかり。余生を大いに楽しもうじゃないか。これでいいのだ!
小生、生涯現役でファーマー・ファーマシー(百姓と稼業の薬屋)を貫徹するのが半分、後期高齢者として遊び惚けるのが半分、これでいいのだ!
ますますワクワクし、楽しくなった。
これって、きっと「生き方をかえよう」になっているんじゃないか。