太陽のような恒星は、チリとガスの雲の凝縮というシンプルなプロセスで生れます。
でも一方で、若い星が集まる活発な環境の中で生れる大質量星は、複雑なプロセスでできると考えられてきたんですねー
こうした生まれたての星のひとつが“G35”です。
“G35”は、“わし座”の方向8000光年彼方にある大質量星で、太陽の20倍も重い恒星です。
アメリカのフロリダ大学では、
NASAの成層圏赤外線天文台“SOFIA”に搭載された特殊な赤外線カメラで、
このまぶしい原始星“G35”のそばにある、かすかな領域をつぶさにとらえたんですねー
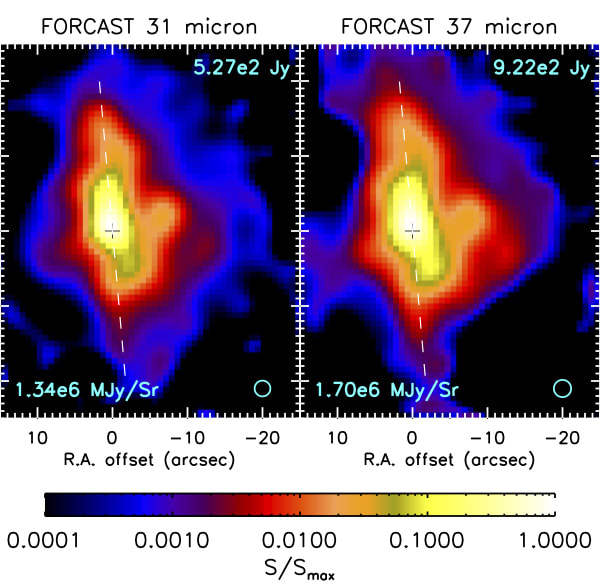
2種類の波長の中間赤外線で
とらえた“G35”
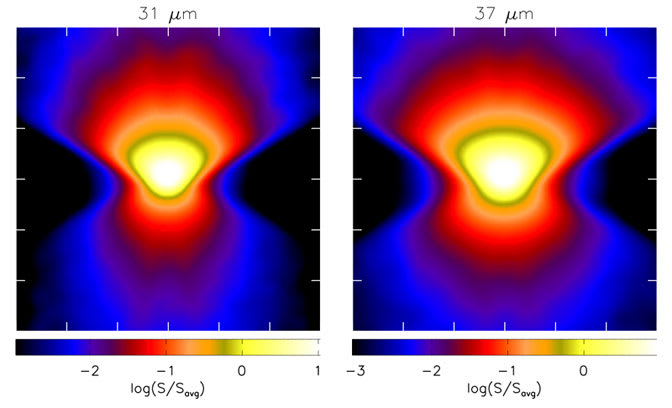
“G35”のコンピュータ・モデル
地球側に向いた上のジェットが
下のジェットより明るく見えている
画像1枚目は、“SOFIA”による中間赤外線像。
2枚目は、それを単純に模式化したコンピュータ・モデルです。
原始星が周囲の星間雲を内側から熱し、円錐形のガスのジェットを両極方向に放出する様子が分かります。
これらの観測で分かったことが、“G35”の構造は思ったよりもずっとシンプルだということです。
これほどの大質量星でも、太陽と同程度の星と同じようなプロセスで形成されるんですね。
でも一方で、若い星が集まる活発な環境の中で生れる大質量星は、複雑なプロセスでできると考えられてきたんですねー
こうした生まれたての星のひとつが“G35”です。
“G35”は、“わし座”の方向8000光年彼方にある大質量星で、太陽の20倍も重い恒星です。
アメリカのフロリダ大学では、
NASAの成層圏赤外線天文台“SOFIA”に搭載された特殊な赤外線カメラで、
このまぶしい原始星“G35”のそばにある、かすかな領域をつぶさにとらえたんですねー
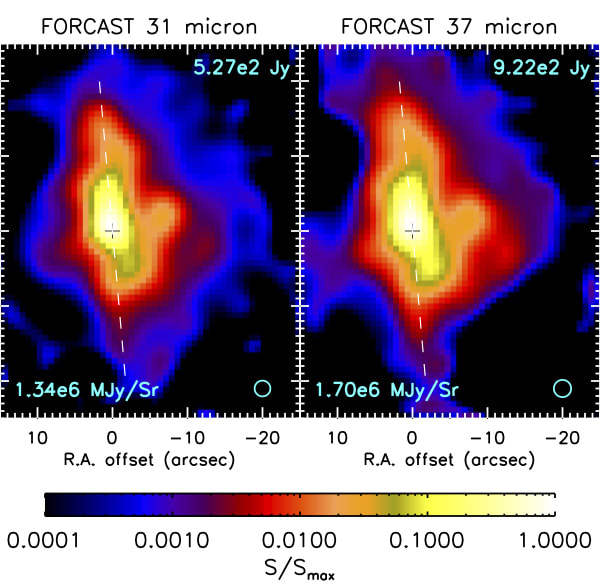
2種類の波長の中間赤外線で
とらえた“G35”
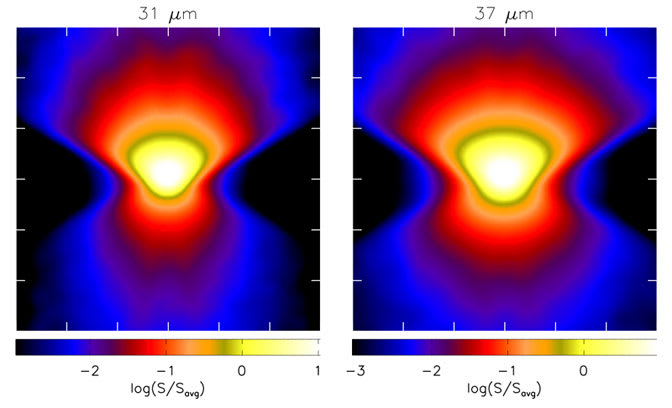
“G35”のコンピュータ・モデル
地球側に向いた上のジェットが
下のジェットより明るく見えている
画像1枚目は、“SOFIA”による中間赤外線像。
2枚目は、それを単純に模式化したコンピュータ・モデルです。
原始星が周囲の星間雲を内側から熱し、円錐形のガスのジェットを両極方向に放出する様子が分かります。
これらの観測で分かったことが、“G35”の構造は思ったよりもずっとシンプルだということです。
これほどの大質量星でも、太陽と同程度の星と同じようなプロセスで形成されるんですね。














