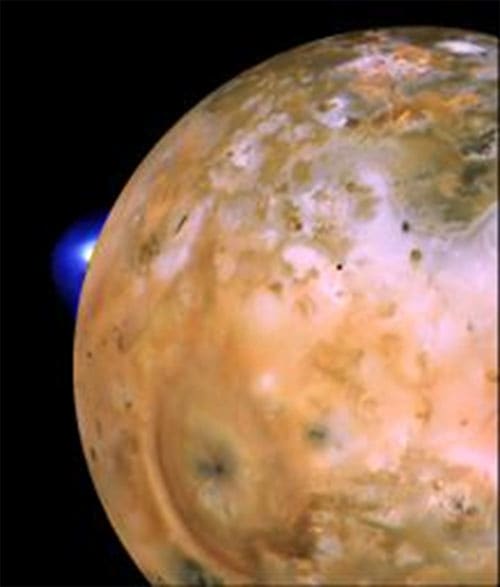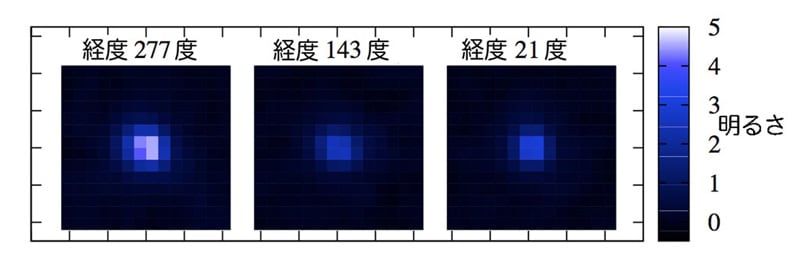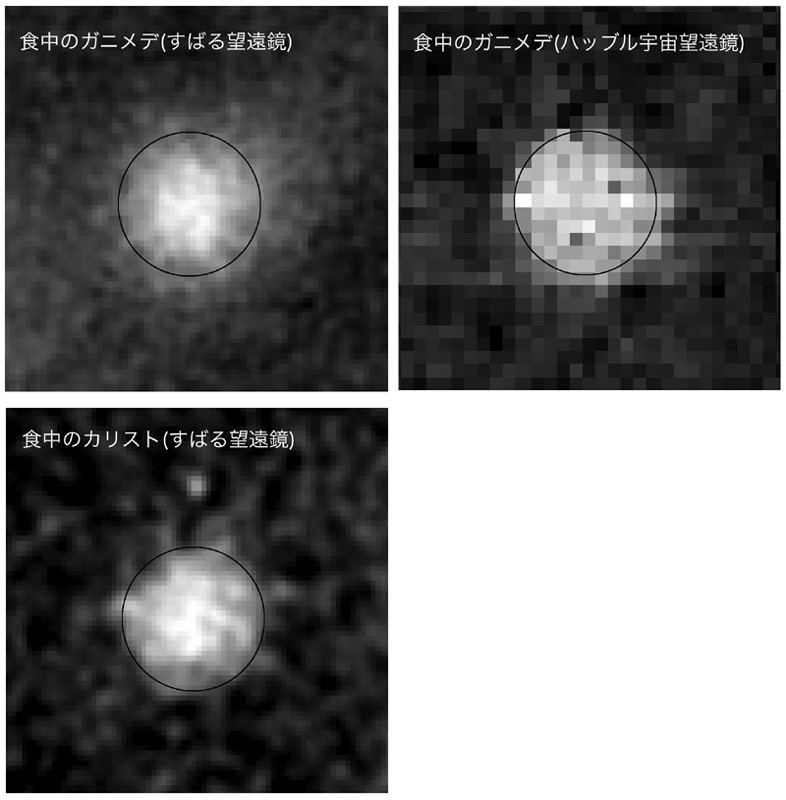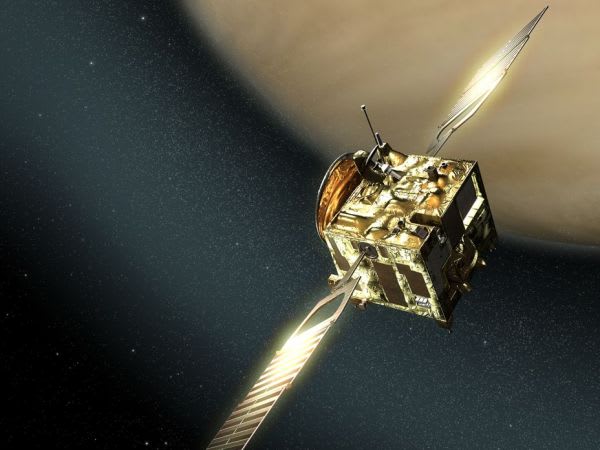|
| 土星の衛星タイタン |
土星の衛星タイタンにおける窒素同位体の存在比に着目した研究から、
タイタンの大気に存在する窒素の起源は、オールトの雲からやってくるような彗星が生まれる冷たい場所だと発表されました。
この発表によりタイタンは、
生まれたての土星の周りにあった、暖かい円盤中の物質で作られていないことになります。
 |
| 原始の太陽を取り囲むガス円盤“原始太陽系円盤”(イメージ図) |
今回の研究では、タイタンの元が太陽系の歴史上初期段階に、ガスやチリからなる冷たい円盤の中で作られたことを示すことになります。
研究チームでは、
タイタンの元になった構成要素は、現在のタイタン大気中にも残っていると考え、
その大気中に大量に含まれる窒素の同位体(窒素14と窒素15)の存在比が、
太陽系の歴史程度の時間では大きく変わらないことを示しました。
あまり変化しないので、他の天体と比較して窒素の起源を探ることができるんですねー
そして、土星探査機“カッシーニ”による探査で、
タイタンと彗星では同位体比が似ていることが明らかになることに…
また、かつてこの比の値は地球とも同じだと考えられていたのですが、
実際には異なっていることが示され、地球の窒素の主な起源は彗星ではないという説を裏付けるものとなりました。
タイタンにおける同位体比は、カイパーベルトからの彗星のものよりも、オールトの雲からの彗星のほうに似ていると考えられていて、今回の研究成果がヨーロッパ宇宙機関のロゼッタ・ミッションで支持されるかが重要になるんですねー
探査機“ロゼッタ”は、
今年の後半にカイパーベルト天体の1つである“チュリモフ・ゲラシメンコ彗星”を探査します。
なので、研究グループの説が正しければ、
同彗星ではタイタンよりも低い同位体比(メタン氷中の水素のもの)が検出されることになるようですよ。