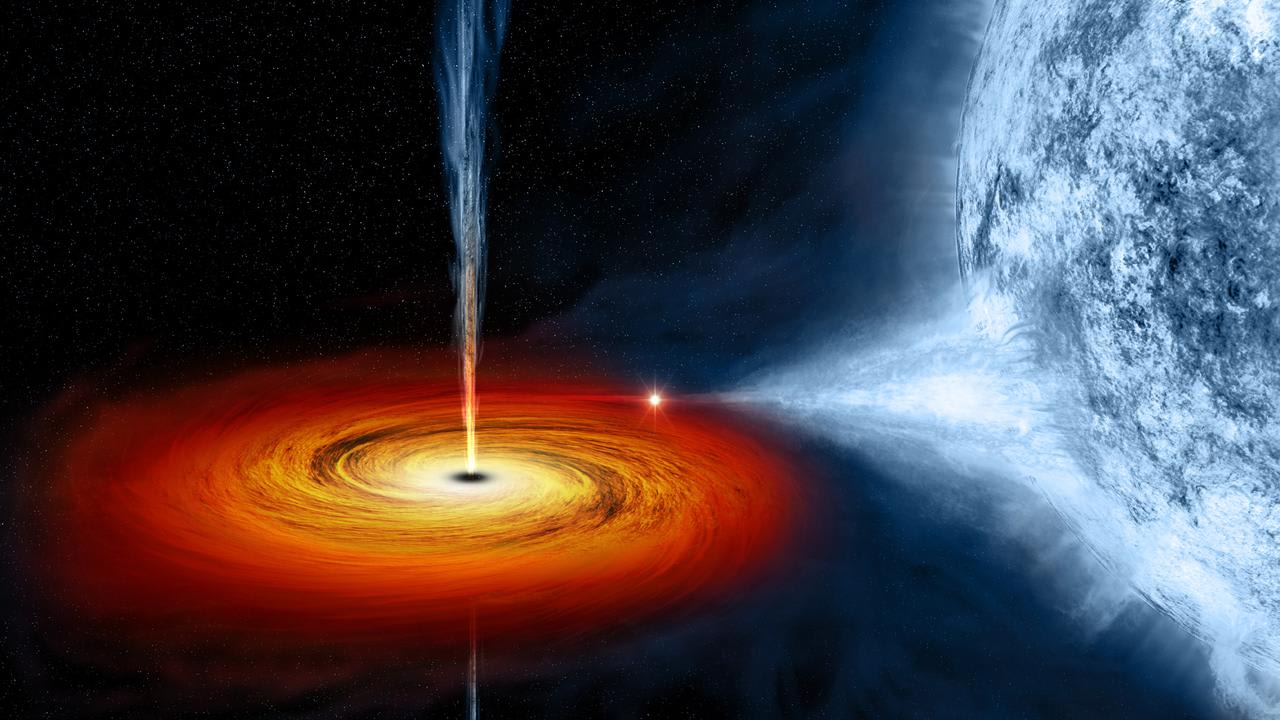X線連星“コンパス座X-1”の周りに4重のリングが見つかりました。
このリングは、X線を反射したエコーが見えているもので、
その大きさやX線が届く時間差から、
“コンパス座X-1”までの距離が明らかになるようです。
X線バーストが作り出す4種のリング
“コンパス座X-1”は中性子星と大質量星の連星系で、
X線を放射している天体です。
2013年の終わりのこと、
この中性子星で、巨大なアウトバーストが2か月にわたって起こり、
その間は非常に明るいX線源となっていました。
その後、NASAのX線天文衛星“チャンドラ”や、
ヨーロッパ宇宙機関のX線天文衛星“XMMニュートン”で観測してみると、
“コンパス座X-1”の周囲にX線で輝く4つの明るいリングが見つかったんですねー
この4種のリングは、
“コンパス座X-1”で起こったX線バーストからのエコー(こだま)のようでした。
電波観測では、“コンパス座X-1”にチリの雲が見つかっているので、
その雲の別々の場所で反射したX線が、リング状に見えているというわけです。
X線と電波で分かった距離
雲で反射したX線は、真っ直ぐに届くX線よりも長い距離を通ってきた分、
地球に届くのが遅くなります。
この数か月の遅れをX線で観測し、
電波観測で分かっている雲の形状と組み合わせることで、
“コンパス座X-1”が地球から3万700光年の距離に位置していることが、
明らかになります。
“コンパス座X-1”は銀河面の濃いチリに隠されているので、
可視光線での観測はできません。
でも、そうした天体までの距離が、
X線と電波の観測データから明らかにされるのは興味深いことですね。
こちらの記事もどうぞ ⇒ X線新星 “はくちょう座V404星”のブラックホール連星がアウトバースト
このリングは、X線を反射したエコーが見えているもので、
その大きさやX線が届く時間差から、
“コンパス座X-1”までの距離が明らかになるようです。
X線バーストが作り出す4種のリング
“コンパス座X-1”は中性子星と大質量星の連星系で、
X線を放射している天体です。
2013年の終わりのこと、
この中性子星で、巨大なアウトバーストが2か月にわたって起こり、
その間は非常に明るいX線源となっていました。
その後、NASAのX線天文衛星“チャンドラ”や、
ヨーロッパ宇宙機関のX線天文衛星“XMMニュートン”で観測してみると、
“コンパス座X-1”の周囲にX線で輝く4つの明るいリングが見つかったんですねー
 |
| NASAのX線天文衛星“チャンドラ”がとらえた“コンパス座X-1”のリング。 |
この4種のリングは、
“コンパス座X-1”で起こったX線バーストからのエコー(こだま)のようでした。
電波観測では、“コンパス座X-1”にチリの雲が見つかっているので、
その雲の別々の場所で反射したX線が、リング状に見えているというわけです。
 |  |
| NASAのX線天文衛星“チャンドラ” | X線天文衛星“XMMニュートン” |
X線と電波で分かった距離
雲で反射したX線は、真っ直ぐに届くX線よりも長い距離を通ってきた分、
地球に届くのが遅くなります。
この数か月の遅れをX線で観測し、
電波観測で分かっている雲の形状と組み合わせることで、
“コンパス座X-1”が地球から3万700光年の距離に位置していることが、
明らかになります。
“コンパス座X-1”は銀河面の濃いチリに隠されているので、
可視光線での観測はできません。
でも、そうした天体までの距離が、
X線と電波の観測データから明らかにされるのは興味深いことですね。
こちらの記事もどうぞ ⇒ X線新星 “はくちょう座V404星”のブラックホール連星がアウトバースト