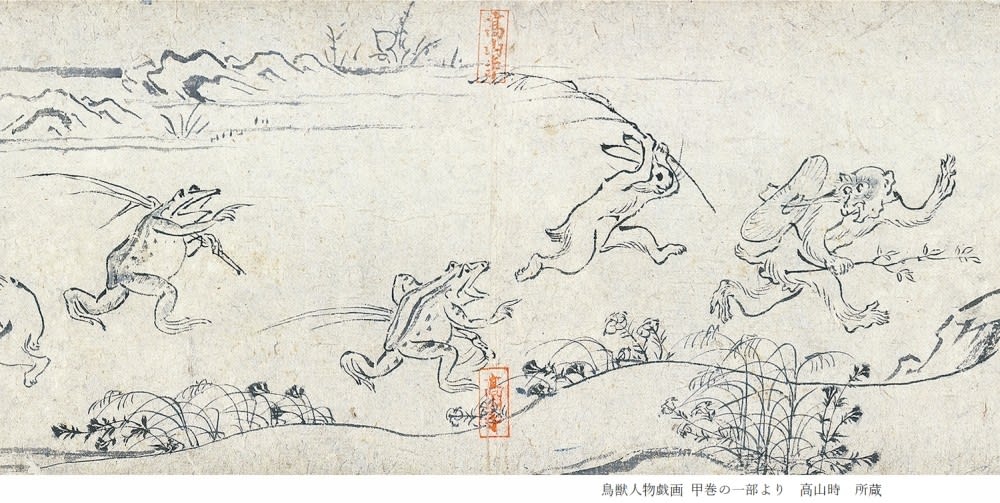淡路島のイングランドの丘に遊びに行った時のこと
飼育舎の中のペリカンを撮影していると 突然 大きなくちばしをカパッと開けました。
うわぁ~大きなあくび? 裂けそうに開かれたクチバシ!大迫力です。
ペリカンの下クチバシには大きなのど袋がついています。
じっくり観察するチャンス!ところが、予想外の姿に大変身!




まるで体内からエイリアンが正体を現したような??
撮影を続けながらも 驚きの連続でした。
のど袋が裏返って のどの奥や舌まで見えている状態?
のど袋は まるで蛇腹のように柔軟に伸びたり縮めたり出来るようですね?

大あくび? もしくは のどのストレッチを終えてスッキリ?
何事もなかったように 涼しい顔のペリカンさんでした。
ペリカンの大きなのど袋は獲物の魚をすくいとる網のような役目をします。
のど袋には14リットル (大パックの牛乳14本) もの水が入ります。

水といっしょに豪快に魚を捕らえ、水だけを排出して魚を丸飲みして食べるそうです。
このペリカンは 池で飼われている大きくて立派な鯉をのど袋にとらえてしまいました。

神戸花鳥園と呼ばれていたころ、この池に大きな鯉を何匹も飼っていました。
「神戸どうぶつ王国」としてリニューアルされてから鯉は屋外の池に移されたのですが
初期にはまだ池に残っていて ペリカンの狩りの標的になっていました。
この写真の鯉は無事に解放されたのですが、不運にも食べられてしまった鯉もいたかもしれませんね…

モモイロペリカンは鳥には珍しく集団で狩りをするそうです。
魚の群を見つけると、大きなくちばしを揺らして魚を追い立て輪になって囲い込み
だんだんと輪をせばめて魚を中心に集めたところで全員がクチバシですくいとるそうです。
この写真は群の連携で狩り、ではなく、一匹の魚をめぐる争奪戦でした。

背後から褐色の翼のペリカンに食いつかれて クチバシが二重になって見えます。
仲間割れの大騒動のおかげで、この鯉は無事にのど袋から脱出できました。


翼に褐色の羽が目立つペリカンは幼鳥や若鳥です。
この子たちもいまではすっかり白い羽に変わり立派な大人に成長しました。
※ 今回の魚争奪戦は2014年10月に撮影しました。

モモイロペリカン(Great White Pelican) 全長約160cm 体重10kg
ペリカン目 ペリカン科 ペリカン属
大きなオスだと全長170cm以上体重は15kgになるものもいるそうです。
▼日本平動物園 モモイロペリカンの詳しい解説が閲覧できます。
https://www.nhdzoo.jp/animals/naka.php?animal_uid=168
アメリカ合衆国ルイジアナ州の愛称は Pelican State(ペリカンの州)
ルイジアナ州 の旗と紋章にペリカンがデザインされています。

ルイジアナが「ペリカンの州」と呼ばれるようになったのは、
初代のルイジアナ総督のウィリアム・クレイボーン( William C.C. Claiborne)が、
周辺に生息するペリカンの親鳥が、飢えた自分の子のために自らの肉を裂いて
餌として与えているのを見て感動しシンボルとして採用したことによる、そうです。
州の鳥として愛されているのはカッショクペリカンとのことです。
アメリカンバスケットボールリーグ(NBA)のチーム ニューオーリンズ・ペリカンズも
ペリカンをチームの紋章やマスコットに採用しています。

参考:ルイジアナ州(Louisiana: LA)
アメリカ大陸30000km -アメリカ・カナダ・メキシコの地理とドライブ旅行情報
http://www.tt.em-net.ne.jp/~taihaku/geography/state/louisiana.html
最後まで見ていただきありがとうございました。