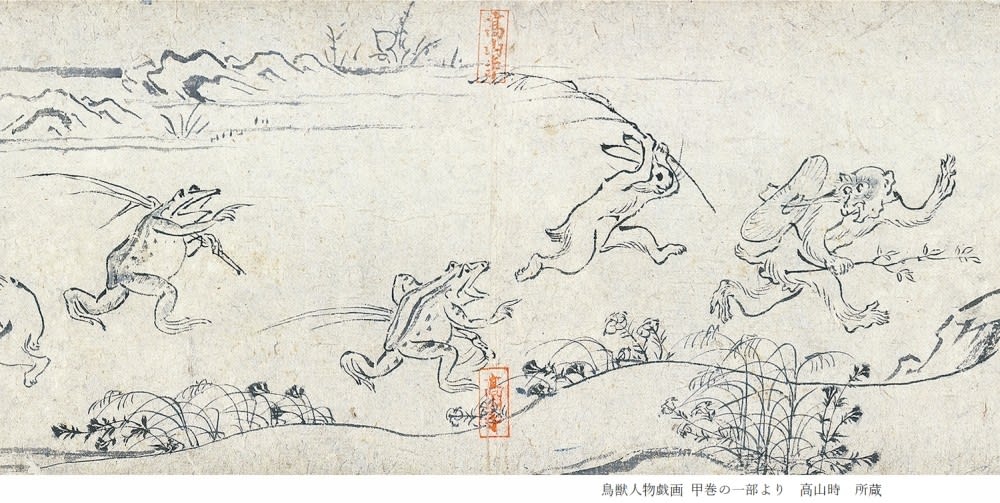薄曇りの日を選んで久しぶりに探鳥に出かけてみました。
今シーズン初のコサメビタキ うれしい出会いです。
ヒタキ類が三羽ほど 林の中を飛び交って虫を捕食していました。
餌場を巡ってジジジジ・・・!ジジジジ・・・!と鳴いてけん制しあっています。
地元のヒヨドリの癇に障ったのか ヒーヨ!ヒーヨ!と追い立てられてしまいました。
今シーズン初のコサメビタキ うれしい出会いです。
ヒタキ類が三羽ほど 林の中を飛び交って虫を捕食していました。
餌場を巡ってジジジジ・・・!ジジジジ・・・!と鳴いてけん制しあっています。
地元のヒヨドリの癇に障ったのか ヒーヨ!ヒーヨ!と追い立てられてしまいました。

公園のシジュウカラはあまり人を恐れません

ツーピ・ツーピ ツーピと鳴いて梢を移動していきました。

メジロたち

曇り空の逆光なのでプラス補正してようやく顔が見えました。
二羽のチョウゲンボウ若鳥
農業地帯の神社の杜をかすめて飛び交っていました。

今年生まれのきょうだいのように感じられました。
親鳥から独立後 二羽で支えあって暮らしているのかもしれません。
立ち寄った公園で観られた花たち
シュウメイギク (秋明菊)

咲き始めたばかり ほとんどがつぼみでした。
ケイトウ (鶏頭)

ビロードのような質感で艶やか ひときわ目を惹きました。
ナンバンギセル(南蛮煙管)

『万葉集』にも登場する一年草 寄生植物で日本では主にススキに寄生するそうです。
▼みんなの趣味の園芸
https://www.shuminoengei.jp/m-pc/a-page_p_detail/target_plant_code-564

シロバナサクラタデ(白花桜蓼)

池のほとりにひっそり咲いていました。
タマスダレ(玉簾)

きっぱりと白く 一輪だけ咲いていました。
ヤブラン(藪蘭)

やさしい薄紫色の小花が連なって
センニチコウ(千日紅)

長期間色あせないことから千日紅の名が。
丸くて白い花の中に 白化した小さな花蜘蛛・・・
クロガネモチ(黒鉄黐 )

冬になって真っ赤に色づいたら レンジャクたちが食べにやってくるでしょうか
この冬も渡って来てくれると嬉しい冬鳥です。
最後まで見ていただきありがとうございました。