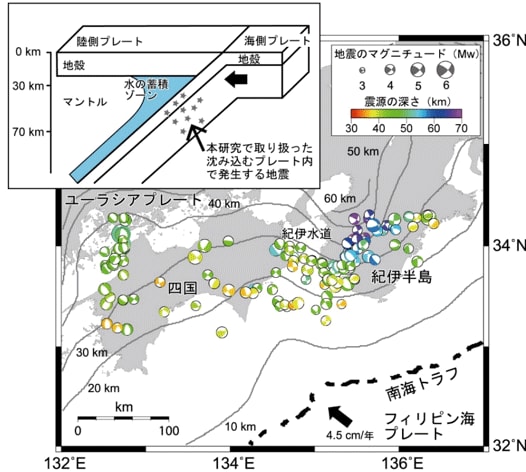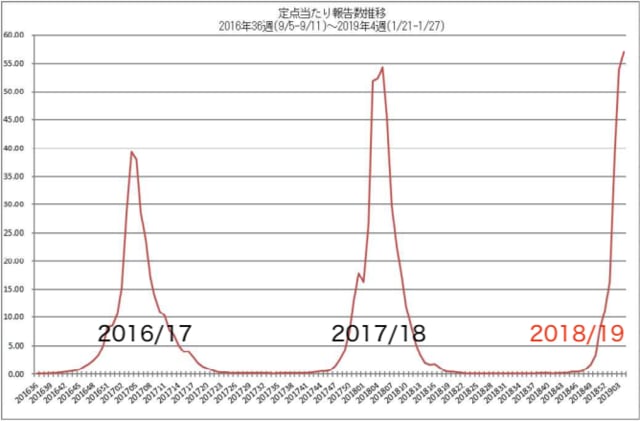(平成32(2020)年暦要項)

① ""平成32(2020)年暦要項の発表""
2019年2月 1日 |トピックス
国立天文台は、毎年2月の最初の官報で翌年の暦要項(れきようこう)を発表しています。暦要項には、国立天文台で推算した翌年の暦(国民の祝日、日曜表、二十四節気および雑節、朔弦望、東京の日出入、日食・月食など)を掲載しています。
今年も2月1日に「平成32(2020)年暦要項」を発表しました(注1)。以下は、主な内容です。
🌸平成32(2020)年の国民の祝日(注2)
元日 1月1日
成人の日 1月13日
建国記念の日 2月11日
天皇誕生日 2月23日
春分の日 3月20日
昭和の日 4月29日
憲法記念日 5月3日
みどりの日 5月4日
こどもの日 5月5日
海の日 7月23日
スポーツの日 7月24日
山の日 8月10日
敬老の日 9月21日
秋分の日 9月22日
文化の日 11月3日
勤労感謝の日 11月23日
•平成32(2020)年は閏(うるう)年です。
•2月24日、5月6日も休日となります(「国民の祝日に関する法律」による)。
•天皇の即位に伴い、平成32年から「天皇誕生日」は2月23日となります。
•「国民の祝日に関する法律」が改正され、平成32年から「体育の日」は「スポーツの日」となります。また、平成32年に限り、「海の日」は7月23日に、「スポーツの日」は7月24日に、「山の日」は8月10日となります。
•この年には日食が2回あります。
•6月21日には金環日食があり、日本では全国で部分食を見ることができます。
•12月14日から15日にかけて皆既日食がありますが、日本では見ることができません。
これらの現象の詳しい状況や予報については、国立天文台 天文情報センター 暦計算室ウェブサイトでも調べることができます。
(注1)暦要項では一貫して平成32年と表記していますが、必要に応じて読み替えてください 本文へ戻る
(注2)平成31(2019)年2月1日現在制定されている法令(未施行を含む)に基づく 本文へ戻る
🌸暦要項について
国立天文台では、国際的に採用されている基準暦に基づいて、太陽・月・惑星の視位置をはじめ諸暦象事項を推算し、「暦書」として「暦象年表」を発行しています。ここから主要な項目を抜粋したものが暦要項です。
昭和29(1954)年6月1日の官報に翌昭和30(1955)年の暦要項を掲載したのが最初で、昭和39(1964)年の暦要項からは現在のように前年2月の最初の官報に掲載するようになりました。
暦要項、暦象年表の内容は、暦計算室ウェブサイトでご覧いただけます。