
本を読んだ。
★ダウン・ツ・ヘヴン
著者:森博嗣
出版社: 中央公論新社
子どもはみんな、空を飛ぶ夢を見るのだ。
コクピットでは、思考が影を潜め、感性と肉体的反射により瞬間的に動作が繰り返される。
性の官能の程近いような状態となる。
パイロットと飛行機はまさに、一体化していく。
命を掲げて自由を堪能する、究極の世界がそこにはある。
(解説:エアーショーパイロット室谷義秀)
この浮遊感がたまらなく魅力である。
より軽く軽やかに飛ぶ。
たばこの煙のように。
(僕はタバコは吸わないが)

本を読んだ。
★ダウン・ツ・ヘヴン
著者:森博嗣
出版社: 中央公論新社
子どもはみんな、空を飛ぶ夢を見るのだ。
コクピットでは、思考が影を潜め、感性と肉体的反射により瞬間的に動作が繰り返される。
性の官能の程近いような状態となる。
パイロットと飛行機はまさに、一体化していく。
命を掲げて自由を堪能する、究極の世界がそこにはある。
(解説:エアーショーパイロット室谷義秀)
この浮遊感がたまらなく魅力である。
より軽く軽やかに飛ぶ。
たばこの煙のように。
(僕はタバコは吸わないが)

本を読んだ
★ナ・バ・テア
著者:森 博嗣
出版社: 中央公論新社
前作のイメージを引きずりながら本を読み始める。
「スカイ・クロラ」はバージン作らしいぎこちない固さが物語のテーマ「生きること」と絶妙なバランスを保ち、「抽象的な崇高性」を表現していた。そういう意味ではすばらしい作品だと思う。想像も出来なかったキャラクターを登場させ、読んだこともないようなストーリィで、とても魅力的だった。
2作目にあたる「ナ・バ・テア」は主人公をそのまま登場させ、「生き続けること」へのさらなる問いかけをしている。作家は状況説明をすることに集中し、さらに物語性を強めた。そしてストレートにメッセージを伝えるようにした。が、あのすばらしい詩的な抽象性が薄れたようにも感じる。
草薙水素は「女」だったのだ。物語は意外な方向に進んだ。作者である森さんは初めから物語が出来ていたのだろうか。それが不思議。ありえない未来SFなのに、ひとつひとつの具体物は現実的、というより、むしろノスタルジーさえ感じる。その絶妙なアンバランスがいい。
本を読みながら、「あっ、これは騙されている」と感じるが、読み続けなければ辿り着けない何かがあるとも思わせる。興味が尽きない。そこでWikipediaで調べてみると、この連作は時系列が発行順とは違うらしい。やれやれ。手の込んだ仕掛けである。騙され上手に読んでいこう。

本を読んだ。
★スカイ・クロラ
著者:森 博嗣
出版社:中央公論新社
森 博嗣さんの「スカイ・クロラ」を読む。
僕は戦闘機のパイロット。
飛行機に乗るのが日常、人を殺すのが仕事。
二人の人間を殺した手でボウリングもすれば、ハンバーガも食べる。
戦争がショーとして成立する世界に生み出された
大人にならない子供—戦争を仕事に永遠を生きる子供たちの寓話。
(「Book」データベースより)
一気に読んだ。
一人称で語られ、彼の視点で物語が展開するので、最後まで読まないと、状況設定が解らない。
最後になってはじめて「キルドレ」が語られ、自分自身の正体を明かす。
たばこの煙、青い澄んだ空、白い雲、墜落する煙。
激しい戦闘シーンなのにとても静か。
死と隣り合わせの生。
文章の隅々まで神経が行き届き、
散文詩を呼んでいるような感覚だった。

本を読んだ。
★京都の平熱――哲学者の都市案内(講談社学術文庫)
著者:鷲田清一
出版社:講談社
鷲田さんは京都生まれの、京大卒業の、そして哲学者。
これだけで、彼はどういう人か、大体は想像できるでしょう。
初めて、鷲田さんの文章を読みましたが、予想通りでした。
京都人らしく、ちょっと斜め視線も取り入れ、
青春の想い出を語りながら、リアルな京都案内です。
ほとんど全てにおいてオカシイくらい納得でした。
京都人はほとんど同じ空間に生きているんですね。
そこが一番オカシイところです。
京都は息苦いくらいほんとに狭い。
時々ですが、
その狭さが程よく心地よく感じることもあります。

本を読んだ。
★台湾とは何か
著者:野嶋 剛
出版社: 筑摩書房
僕が台湾について知っていたことは、
下関条約によって日本統治が始まった。
戦後、国民党が台湾に逃げ込み、
台湾=中華民国となった。
というくらいだけだった。
情けないことだがずっとそんな認識しかなかった。
僕が台湾への関心を強くしたのは、
映画《悲情城市》を観たことからはじまる。
以後、数本台湾映画を観た。
実際に台湾へ行ってみたく、普通の2泊3日の観光旅行に出かけた。
そして、念願の、映画の舞台となった九份へ行った。
基隆山を眺め、遠くに海を眺めた時、
もっともっと台湾のことを知りたいと思った。
以後、数本台湾映画を観た。
そして、2度めの台湾旅行をした。
少し勝手がわかっているので、あちこちぶらぶらした。
夜の台北もぶらぶらした。
すっかり台湾好きになってしまった。
また数本台湾映画を観た。
あの迷作バス旅の台湾編も見た。
またあの《麗しの島》へ行きたくなった。
できれば、南の方へ行ってみたい。

本を読んだ。
★人はなぜ〈上京〉するのか
著者:難波 功士
出版社: 日本経済新聞出版社
赤い帯の言葉は、
「東京は本当に幸せな選択肢?」
かってはヒエラルキーを上がるには、東京へ行くしかなかった。
では、いまは?
《姿三四郎》の上京青雲編から、現在の上京定住の頓挫編へと、近代現代の《上京史》から日本文化の足跡を辿るもの。小説家、画家、ミュジシャン、果ては自称文化人、ギョウカイんジンなど、地方から《花の東京》への進出もんの夢が、それぞれ時代背景を説明しながら語られています。サブカルチャー的要素溢れる読み物。
東京については殆ど知らなので、面白い指摘があって、なるほどね、と思う所もちらほら。僕の大好きな国木田独歩の書いた《武蔵野》は今でいうなら新宿辺りらしい。その後、この東京西地域は西日本上京組の定住地域として開発が進み、爆発的な人口増地域となる。そして《新宿や渋谷辺り》は《西日本出身者の東京憧れ組もしくは一旗上げたい組》の拠点となるという。それに対して、東日本出身者が上京したらまず足を踏み出す《上野》、そして人々が集う《浅草》が語られている。そのくだり興味深く《なるほど》である。
今後も《東京の肥大化》は進むんだろうが、それとともに《地方の散々たる姿》を心配する。地方に分散されたものは、ショッピングモールと原子力発電所の悪夢。そして地方には公務員しか仕事が無い、コンビニしか店がない、パチンコかスロットしかレジャーがない、、、という悪夢。これは将来の暗い話である。最後は少々嘆き節で終わっている。
せめて《東京のバックアプ都市計画を》と首都機能の関西移転を訴えるところは、関西知識人特有のちょっと斜めの余裕ある目線を感じ、京都を選択し此処に住み《上京者》ではなかった者としては、妙に共感しうるところでした。
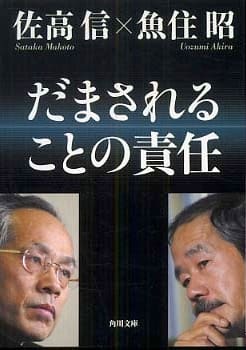
本を読んだ。
★だまされることの責任
佐高信と魚住昭
出版社:角川グループパブリッシング
佐高信さん。
いつも苦虫を噛み潰したような表情で、
権力に楯突く、吠える姿は、もはや「芸」の域である。
笑っていても心からの微笑みとも見えず、ニヒルである。
これだけ言いまくると、敵も多いだろうし、
「身に危険がせまる」なんてこともあるのではと思ってしまうが、
そこは、ジャーナリストであるが故の言いたい放題とそれなりに世間が認め、
本人も「自分の売りは吠える事」と決め込んでいるフシがある。
魚住昭さん。
共同通信の「沈黙のファイル」執筆チームの一人。
彼を有名にしたのは「野中広務ー差別と権力」である。
ボクは今なお時々この本を本屋で立ち読み続けている。
この二人の対談集「だまされることの責任」は、
はじめに、映画人である伊丹万作さんの「戦争責任者の問題」の文を掲載し、戦後60年を過ぎてもいまなお無責任体制に浸っているような日本人の精神構造を鋭く検証している。中でも「自己を溶かす日本人」の話は、組織の中で「私」を失いアリ地獄みたいに堕ちてゆく人間像が鮮やかに語られ、興味が尽きない。身の回りにもよくある光景である。
「権力にすり寄るジャーナリズム」の話で、魚住さんはこのように語る。
「要するに、みんな派閥記者。派閥の一員になることによって、情報を得る。仲間になれば情報は自然と入ってくるからその一部分を記事化することによって、、、、、、、、、、、、、だからお互いに得をする。日本の政治ジャーナリズムの主流は、そうした持ちつ持たれつの関係でなりたっているんです。」
どの世界、どの分野でも同じ事がいえるのではないか。
人はその派閥に入るために、
その仲間になるために「私」を溶かし続けているのではないかということ。
少し遠ざかってみると、
全体の構造が朧げながら見えてくる。
最近、
僕はテレビニュースはまともに受け止めなくなった。
新聞はほとんど読まなくなった。

本を読んだ。
★殿様の通信簿
著者:磯田道史
出版社:朝日新聞社
最近、よくお顔をテレビで拝見いたします。
人気なんですね。
本の帯には「平成の司馬遼太郎」の呼び声も高いと書いてあり
、司馬ファンとしては、これは一度読むより手はないでしょうと買ってしまった。
読んでみると、なるほど歯切れの良い文章リズムで、爽やかです。
司馬さんの書く物の中に、
「・・について書く」とか
「話がかわるが・・」
とかいった単刀直入の書き出しがよくあり、
ぐっと引きつけられるのですが、
磯田さんの文章にもそのような要素があります。
作家の磯田さんは年齢もまだお若いので、
今後どのような世界観を表現されるのか注目していきたいです。
最近、よくお顔をテレビで拝見いたします。
人気なんですね。
私には、「江戸時代、加賀100万石という大国が何故にたたきこわされずに残ったのか」という日本史上の疑問がずっとありました。この本には、さもその時代を見てきたように解説されています。お見事です。「武士の家計簿」も読んでみることにしました。

本を読んだ。
★テロリストのパラソル
著者:藤原伊織
出版社: 角川書店
発表された当時はかなり気になってはいたが、いつのまにか忘れた。
今回、たまたまいつもの本屋で文庫本を手に取ってしまった。
立ち読みしたあとがきの文章が気に入り即購入。
それなりのハードボイルタッチで、一気読み。
話の筋はある程度知っていたが(何で知ってるんだろうか?自分でも覚えていない)
小説を読むと、《これはいい》と唸りながら。
熱烈なファンがたくさんいるというのも頷ける。
登場人物のキャラが《凛として際立つ》。
となると、読んでいて気持ちがいい。
うじうじしたのが出てこないというか、
犯人のテロリストがどうもすっきりしない男というのがちょっと惜しいくらい。
男《これが宿命なんだよ。これがあの闘争を闘ったぼくらの世代の宿命だったんだ》
に対して、主人公島村は、
《私たちは世代で生きてきたんじゃない。個人で生きてきたんだ》
この物語は、個人で生きてきた男の孤立無縁の戦いを描いた作品である。
ちょっと格好良すぎではないかと思うが、実にすがすがしい気分。

本を読んだ。
★ヘンな日本美術史
著者:山口晃
出版社: 祥伝社
●第1章 日本の古い絵ー絵と絵師の幸せな関係(鳥獣戯画、白描画、一遍聖絵(絹本)、伊勢物語絵巻、伝源頼朝像)
●第2章 こけつまろびつの画聖誕生ー雪舟の冒険(こけつまろびつ描いた雪舟/なぜ雪舟は邪道を選んだのかー「破墨山水図」ほか)
●第3章 絵の空間に入り込むー「洛中洛外図」(単なる地図ではない、不思議な絵/とっつきやすさの「舟木本」 ほか)
●第4章 日本のヘンな絵ーデッサンなんかクソくらえ(松姫物語絵巻、彦根屏風、岩佐又兵衛、円山応挙と伊藤若冲、光明本尊と六道絵-信仰パワーの凄さ)
●第5章 やがてかなしき明治画壇ー美術史なんかクソくらえ(「日本美術」の誕生、「一人オールジャパン」の巨人ー河鍋暁斎、写実と浮世絵との両立-月岡芳年、西洋画の破壊者-川村清雄)
僕は、山口さんの実作品を観たことはない。
何度も見る機会はおとずれていたが、どういうわけか観ていない。
ところが、テレビに出演した山口さんはどういうわけかよく見ている。
ひょうひょうとした語り口は、ある意味この本の魅力ともなっている。
そのうちに作品を観る機会はやってくるだろう。
楽しみに。

本を読んだ。
★堕落論 (新潮文庫)
著者:坂口安吾
出版社: 新潮社
久しぶりに坂口安吾を読んだ。
ほんとに好き勝手に思ったことをズバリズバリ痛快に書いている。
好き勝手と書いたが、彼自身は強い意志と明晰な分析力で、自分の思いを表明している。
大勢の反発を覚悟で書いていると思われる。
敗戦直後《半年後ではあるが》の時代の空気の中で書いているので、
堕落ではなく、ある意味上段の構えである。
《そこまで気張ることはないだろう》と気後れしてしまうが、
戦時中も命がけだが、戦後も命がけである。
《堕落論》と銘打っているが、今日的には《極めて健全》である。
《堕ちよ》のデカダンス言葉は、当時の人々にとって至極魅惑的言葉であり、意識が少し変わり始めた瞬間である。
21世紀の今読んでも、刺激的である。
ひょっとしたら、我々日本人の精神構造は、安吾の生きた時代とはあまり大きな変化がないのかもしれない。
人を発熱させるメッセージを発するのは、これアーチスト。
生きろ、生きろと喚いているようだ。

★西洋の伝統色
著者:西洋の色を愛でる会
出版社: 大和書房(2017/01/10)
西洋で長く親しまれてきた、美しき186色を紹介しています。
色の由来に触れて、186の物語。
今まで、何気なく、気の向くまま使ってきた
青、赤、オレンジ、ピンク、黄、緑、紫、茶、そして、黒、白。
手元において、気ままにページをめくる。

本を読んだ。
★疲れすぎて眠れぬ夜のために (角川文庫)
著者:内田樹
出版社: 角川書店 (角川文庫)
この本は2回目です。
僕が特になるほどなぁと唸るのは
《女性嫌悪の国アメリカが生んだサクセスモデル》というところ
ここでの彼の話は非常に興味深い。
西部劇は鎮魂のための物語であり、
アメリカ文学は今なお《傷つけられた男の癒し》という大テーマに取り憑かれているという主張。
ものすごく納得しました。
彼の主張を読みながら
《そぉーか、ギャツビーの物語はまさに男の鎮魂の為の小説》だと納得。
興味ある方は、是非、どうぞ。
結構好き勝手にしゃべったものを本にしたという気楽さが滲み出ていますが、
息抜きにはちょうどいい。
余分な力みがすっと抜けます。
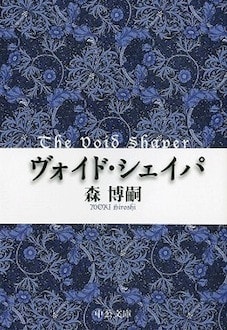

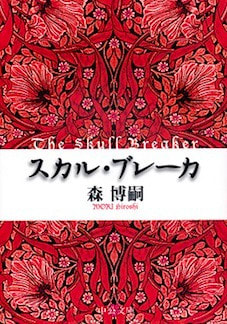


本を読んだ。
★《ヴォイド・シェイパ 》シリーズ
著者:森博嗣
出版社: 中央公論新社
1巻:ヴォイド・シェイパ The Void Shaper
2巻:ブラッド・スクーパ The Blood Scooper
3巻:スカル・ブレーカ The Skull Breaker:
4巻:フォグ・ハイダ The Fog Hider
5巻:マインド・クァンチャ The Mind Quencher
一言でいえば森博嗣の《剣と思索の旅物語》である。
主人公ゼンは、山から降りて人社会と交わり
それなりの知識と生きる知恵がついた。
はじめは、見るもの触るもの全てに新鮮な驚きがあったが、
しだいに人との共同作業から
ゼンなりの人生観、
そして、そこからたどり着く《剣の道》が語れれる。
全てが主人公ゼンの視線で描写される一直線な感覚。
RPGゲームの主人公と一緒に旅をする感覚でした。
生きるとは負け続けること、
死ぬとはもう負けぬこと。
まさしく禅問答。

本を読んだ。
★新装版 限りなく透明に近いブルー
著者:村上龍
出版社: 講談社:新装版 (2009/4/15)
1976年の村上龍の作品。
当時、衝撃的に扱われたので、単行本を買って読みました。
いまだ、僕の本棚に残っているところをみると、
やはり何処か気になっていたのかもしれない。
(僕は時々、本棚の大掃除をします。ほぼ処分します)
で、
今回読んだのは、本屋さんに新装版となって並んでいた文庫本です。
40年前に読んだ時の気分が少し残っているので
現在はどんな気分になるかなぁと。
エログロ、ドラッグ、繰り返される吐き気の光景。
登場人物たちが吐き気をくりかしている文章は読んでいて心地よくはありません。
しかも作者、村上龍はしつこく無機質に容赦なく描写する。
こっちだって吐きたくなるくらいです。
やっぱり今回も
全体のトーンは《限りなく無機質なグレー》を感じてしまいました。
70年代のひとつの青春物語。
大きな物語に夢を語れない青春群像。
それからの時代は、さらに刹那的に、そして限りなく欲望を求めてゆく時代。
そういう意味では、
70年代の記念碑的作品でしょうか。