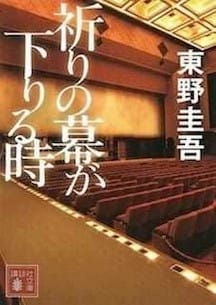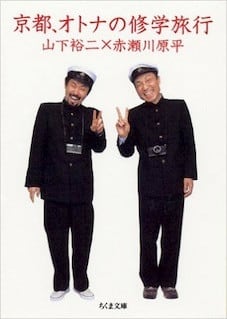本を読んだ。
★完全なる首長竜の日
著者:乾緑朗
出版社: 宝島社
文庫本の帯に《映画化》と。
ならば読んでみよう、一気読み。
時空間の歪んだ語り口に初めはだいぶ悩まされました。
此れはいったい何を語っているのか?読みながらシュールな映像を思い浮かべます。
サスペンスの高まりに少しホラーが加わります。
しかし、一貫して、語り手である《私の視覚のぶれ》ですので、しだいにその感覚世界に慣れてゆき、そしてついにその謎が解けます。
物語はいわゆる《胡蝶の夢》がテーマ。
そのテーマを《いかに手際良く描ききるか》ということに作者は細心の注意を払いながら進行させます。
しかしその謎?に気づいた瞬間に、この物語への興味は薄れました。
ラスト、ちょっと衝撃でしたが、これも《イメージの増幅》の手段でしょう。
尽きることのない《現実と夢》の追いかけっこ。