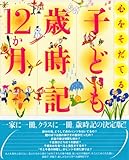「現代児童文学者の経済学」という記事(カテゴリーは評論)で、児童文学の作家や評論家が、それだけで生活していくことがいかに困難かを分析しました。
その中で、将来的には中間搾取層(出版社、取次ぎ、書店など)がなく印税が高い電子書籍に期待したいことを述べました。
その時、頭の中にあったのは、すでにベストセラー作家を生みだしているアメリカでのKDP(キンドル・ダイレクト・パブリッシング)のことでした。
そのKDPの日本語版が、2012年末にスタートしました。
ためしに、将来の日本の児童文学者たち(純文学の作家たちも)を、KDPが経済的に救済できるかを検討してみました。
結論からいうと、まだ一般的な児童文学者たち(当然のことですが、彼らは基本的に文系で英語も苦手な人が多いです)には、KDPは参入障壁が高いことがわかりました。
KDPは自己出版(自分で編集作業や印税の経理処理をする)なので、いわゆる自費出版(百万円以上かかることが多いです)や協力出版(著者が自己負担金を出します)と違って、費用はいっさいかかりません。
印税は35%(特定の要件を満たせば70%)と、期待通りに高いです。
紙の本の印税は普通は10%ですが、児童文学の場合は絵描きさんの分があるので高学年で8%、グレードが下がるにつれて下がり、4%とか3%といったアマゾンのアフィリエイト広告(ブログなどに載せる広告)の手数料より割が悪くなる場合もあります(短編のアンソロジーの場合はそれを頭割りしますので、ゴミみたいなパーセンテージになってしまいます)。
しかし、KDPには以下のような参入障壁があって、一般的な児童文学者にはすぐには手が出ないと思われます。
1.印税の支払いがアメリカにあるアマゾンの関連会社からなので、アメリカの源泉徴収(30%)を避ける手続きが必要。
2.送金は円建て(1000円以上たまったら自動的に送金される)で、向こうの銀行の手数料はアマゾン負担ですが、日本の受け取り銀行でリフティング・チャージ(一件につき数千円)がかかることが多く、少額の送金だと赤字になってしまう(銀行によっては無料のところもあるようです)。
3.本の原稿ファイルを、キンドル本の仕様に変換しなければならない。
以上の障壁は、手間暇かければ回避する方法はあります。
それに、1と2は最初だけですし、3も二回目からは慣れるのでそんなに時間はかからなくなるでしょう(画像がなく原稿をワードで書いている人はそれほど難しくありません)。
ただ、私が調べた限りでは、日本アマゾンのKDPに対するサポート体制が非常に悪い(英語の情報が多い。日本語の情報は自動翻訳のせいか誤訳だらけ。日本アマゾンにKDPを詳しい人がいない。電話でのサポートが受けられない)ので、一般的な児童文学者にはなかなか大変でしょう。
キンドル上にはKDPのノウハウ本があふれていますが、どうも「釣り」っぽい感じがしますので、価格は安いですが手は出さない方がいいと思います。
日本アマゾンの公式情報やネット上に無料の日本語情報(今までの私の経験では無料の方が信用がおける(お金目的ではないので)ことが多いですし、取捨選択が自分でできます)も、だんだんに出てきています
しかし、私が本質的な障壁と考えているのは、KDPの最低価格です。
35%の印税の場合の最低価格は99セント(日本では99円です)です。
安いように感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、短編を99円で売るのは困難です(私の感覚では紙の本換算で1ページ1円以下にしないと売れないでしょう)。
また、70%の印税を得るための最低価格は2ドル99セント(日本では250円です)です。
薄い文庫本のキンドル版は、300円から400円で購入できるので、有名でない作家の本を250円で購入する人はほとんどいないでしょう。
第一、キンドルをはじめとした電子書籍リーダーも、いまだに日本では十分に普及していません(ただし、アイフォンやアンドロイド用の無料の対応アプリがあるので、スマホやタブレットで読むことは可能です)。
以上のように、現状では児童文学作家のKDPへの参入は難しいでしょうが、他の記事でも書いたように五年後ぐらいには、これらの障壁も緩和されることを期待しています。
これは、ひとえにアマゾンの日本マーケットに対するマーケット戦略にかかっていると思われます。
私は外資系の電子機器メーカーの新規ビジネスの開拓に長年かかわってきたので、彼らが冷徹でビジネスライクな考え方で決定するのはよく理解しているつもりです。
でも、私がKDPのマーケティング担当者ならば、日本語のキンドル本の増加のために、日本でのKDPのサポートにもっとお金をかけるでしょう。
それが、日本でのキンドル本体の販売の増加につながり、そうするとアマゾンにとってのビジネスの本線である一般のキンドル本の売り上げも伸びるという、正のスパイラル効果が期待できるからです。
また、楽天やソニーの電子書籍ビジネスとの差別化にもなるでしょう。
はっきりいって、今の日本アマゾンでKDPに関わっている人たちはビジネス的に素人なので(もしかするとアウトソーシングされているかもしれません)、現状ではまったく期待できません。
要は、米国アマゾンが日本での電子書籍マーケットに対してどういう戦略をとるかです。
最悪は、電子書籍ビジネスの日本からの撤退でしょう。
その時は、楽天のコボなどで、KDPと同様のサービスを展開してくれるとありがたいのですが。