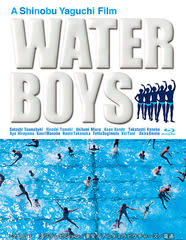(原題:A torinoi lo)あまりにも図式的な展開で、愉快ならざる気分になってくる。19世紀末の哲学者ニーチェによる“神は死んだ”という名台詞を元にして、聖書にある“七日間に渡る天地創造”を逆パターンにして綴っただけの話。さらにニーチェが正気を失う切っ掛けとなったといわれる“疲弊した馬車馬”というモチーフを、そのまま映像として引用している。いわば、思い付いた素材を漫然と積み上げているに過ぎず、そこには何の工夫も見当たらない。
烈風吹きすさぶ荒野の一軒家に住む初老の男(デルジ・ヤーノシュ)とその娘(ボーク・エリカ)。男は右腕が不自由で、娘の手助けがないと着替えも出来ない。男は馬車に乗って町へ通うのを日課にしていたが、ある日馬が言うことをきかなくなる。やがて馬はエサも食べなくなり、二人の生活は困窮する。
家には男の知人や町からやってきた一団などが尋ねてくるが、二人の運命に関与するわけでもない。そして世界は終末に向かって進んで行く・・・・とかいった筋書きだ。

時代設定がいつなのかは分からないが、とにかく現代ではない(ニーチェが生きた19世紀を想定しているようにも思える)。二人がどうやって生計を立てているのか、それは分からない。どうして男が町に行っていたのか、そのことも不明。映画は“一日目、二日目”といった具合に日毎のチャプターに分かれている。日が進むにつれて二人は追いつめられ“六日目”を最後にしてエンドマークを迎える。
もちろんこれは、神は天地創造に六日かかって七日目は休んだという話を裏返したもので、六日で世界は終わってしまうので七日目は存在しないというシニカルな筋立てである。
終末論をテーマにした映画は他にもいくつかあるが、アンドレイ・タルコフスキー監督の傑作「サクリファイス」を思い出す映画ファンは多いだろう。しかし本作は「サクリファイス」の足元にも及ばないヴォルテージの低さを露呈させている。あの映画で綴られた作者の切迫した想いと究極的な“祈り”といった観客を揺り動かすパッションは、この映画のどこにもない。自己満足的な画面が冗長に流れていくだけだ。
J・G・バラードのSF小説「狂風世界」を思わせるような荒天の描写や、熱気をはらんだ馬体の映し方、長回しを基調としたカメラワーク、モノクロ撮影によるストイックな画像などヴィジュアル面では見るべきところはあるが、本編自体が低調なので、ただの“珍奇なエクステリア”としての存在価値しかない。
監督はハンガリーの名匠と言われるタル・ベーラだが、私は彼の作品を今まで観たことがない。ただ、本作のようなタッチがどの映画にも踏襲されているのならば、観る気は起きない。
烈風吹きすさぶ荒野の一軒家に住む初老の男(デルジ・ヤーノシュ)とその娘(ボーク・エリカ)。男は右腕が不自由で、娘の手助けがないと着替えも出来ない。男は馬車に乗って町へ通うのを日課にしていたが、ある日馬が言うことをきかなくなる。やがて馬はエサも食べなくなり、二人の生活は困窮する。
家には男の知人や町からやってきた一団などが尋ねてくるが、二人の運命に関与するわけでもない。そして世界は終末に向かって進んで行く・・・・とかいった筋書きだ。

時代設定がいつなのかは分からないが、とにかく現代ではない(ニーチェが生きた19世紀を想定しているようにも思える)。二人がどうやって生計を立てているのか、それは分からない。どうして男が町に行っていたのか、そのことも不明。映画は“一日目、二日目”といった具合に日毎のチャプターに分かれている。日が進むにつれて二人は追いつめられ“六日目”を最後にしてエンドマークを迎える。
もちろんこれは、神は天地創造に六日かかって七日目は休んだという話を裏返したもので、六日で世界は終わってしまうので七日目は存在しないというシニカルな筋立てである。
終末論をテーマにした映画は他にもいくつかあるが、アンドレイ・タルコフスキー監督の傑作「サクリファイス」を思い出す映画ファンは多いだろう。しかし本作は「サクリファイス」の足元にも及ばないヴォルテージの低さを露呈させている。あの映画で綴られた作者の切迫した想いと究極的な“祈り”といった観客を揺り動かすパッションは、この映画のどこにもない。自己満足的な画面が冗長に流れていくだけだ。
J・G・バラードのSF小説「狂風世界」を思わせるような荒天の描写や、熱気をはらんだ馬体の映し方、長回しを基調としたカメラワーク、モノクロ撮影によるストイックな画像などヴィジュアル面では見るべきところはあるが、本編自体が低調なので、ただの“珍奇なエクステリア”としての存在価値しかない。
監督はハンガリーの名匠と言われるタル・ベーラだが、私は彼の作品を今まで観たことがない。ただ、本作のようなタッチがどの映画にも踏襲されているのならば、観る気は起きない。