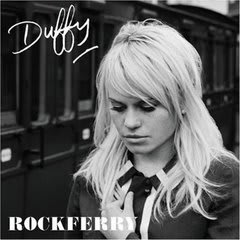(原題:12)ロシア映画の力作だが、作為的な演出にはどうも愉快になれない。元ネタになったシドニー・ルメット監督の、往年の米映画「十二人の怒れる男」は私は観ていないので、それと比べてどうのこうのとは言えないが、少なくともこういった法廷ドラマでは理詰めの展開が必要なはずだ。しかし本作はそのあたりが弱い。
冒頭、12人の陪審員の中で一人だけ被告の少年の無罪を唱える者が現れるが、その理由が“若い被告を安易に有罪にしてはいけない”というのは噴飯ものだ。心情的なことはひとまず脇に置いて、具体的な反証から入らないと何のために陪審員席に座っているのか分からない。そもそも彼らは、それまで公判のいったい何を聞いていたのか。
犯行のあったアパートに住む老人の供述内容が物理的に考えておかしいとか、目撃者の女性の証言が突っ込みどころ満載だとか、そんなことは冷静に陳述を聞いていれば誰でも気が付くことではないのか。特に被告の少年と同郷であり、被告の行動様式を容易に推察できるはずのメンバーがこの時点に至るまで漫然と“有罪”の表明をしていたというのは、不自然極まりない。
さらに違和感を持ったのは、12人のプロフィールが必要以上に長い時間を割いて紹介されていること。確かに切々とした話ばかりなのだが、それがこの法廷ドラマにふさわしいのかどうかは疑問だ。コンパクトな“暗示”で終わらせてスピーディーに作劇を進めれば、160分もの長い上映時間は不要だったはずである。また会場に迷い込んできたスズメとか、小学校の体育館を急ごしらえの議論の場に選んだ事による小道具の過剰な羅列とか、余計なモチーフが多すぎる。
製作や脚本を兼ねるニキータ・ミハルコフ監督は、被告をチェチェン出身者に設定することにより、現代ロシアの深刻な社会問題をクローズアップさせたかったのは明白だ。しかし、それがここでは空回りしているとは言えないか。内戦の描写はシビアだが、何度も同じ場面を繰り返すなど冗長な展開が目立つ。
舞台劇を意識したような意匠、大仰な身振り手振りで怒鳴り合う登場人物達は、劇映画としての枠組みを不用意な形で乱しているように思える。冤罪を晴らすだけでは解決しないという状況に、社会主義時代とは違った意味の抑圧が漂うロシアの国情を憂えていることは大いに分かるのだが、もう少し別のアプローチがあったはずだ。
セルゲイ・マコヴェツキーやヴァレンティン・ガフト、アレクセイ・ペトレンコら我が国では無名ながら本国では手練れの演技者と思われる俳優を揃え、そしてミハルコフ自身も顔を出す渋いキャスティング。エドゥアルド・アルテミエフの重厚な音楽、ヴラディスラフ・オペリヤンツのカメラによる清冽な色調の画面形成など、観客を引き込む仕掛けは出来ている。ただ、前述のような作品コンセプトの練り上げ不足が、アカデミー外国語映画賞をはじめ各種アワードで注目されていながら、大賞を射止めていない原因かと思われる。