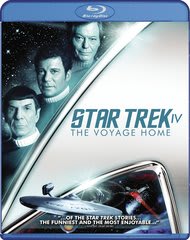去る3月28日から30日にかけて、福岡市博多区石城にある福岡国際会議場で開催された「九州ハイエンドオーディオフェア」に行ってきたのでリポートしたい。今年(2014年)の目玉企画は、マーク・レビンソンの講演である。彼は米国の伝説的なエンジニアで、同名のブランドの創始者だ。70年代前半に彼が立ち上げたこの会社は、ハイエンド・オーディオという新しいジャンルを確立したと言われる。
講演は3月28日の金曜日に行われた。いくら始まるのは夕刻とはいえ、平日だ。数日前から長時間の残業をして仕事を前倒しで片付け、当日は午後から有給休暇を取り(とはいっても、実際は職場を出るのが遅れ、会場にたどり着いたのは開始ギリギリの時間だったが ^^;)、何とか入場することが出来た(苦笑)。

主宰者側の事前の情報から、講演の主な内容は彼が新たに立ち上げたブランドであるDANIEL HERTZのアンプやスピーカーのデモンストレーションだと思っていたのだが、実際は違った。何と今回のレクチャーの主眼は、MASTER CLASSと命名された同ブランドの音楽ソフトウェアだったのだ。
音楽ソフトとはいっても、iTunesのような単なるプレーヤー兼ファイル管理用アプリケーションではない。これはイコライザーである。あらゆる種類の音楽ファイルのトーン・バランスを補正することが可能で、いわば聴感上の帯域を自分好みにカスタマイズ出来るというシロモノだ。しかも、補正したファイルはそのまま保存が出来るという。
私は技術的なことに関しては疎いのでハッキリしたことは言えないが、早い話が、とても良く仕上げられた(アプリケーション上の)トーン・コントロールらしい。80年代にレビンソンは“透明なトーン・コントロール”という触れ込みのチェロ・オーディオ・パレットという規格を発表したことがあったが、今回のMASTER CLASSはそれをデジタル領域で実現したということだろう。

このソフトウェアの機能が実際どの程度の威力を発揮するのか、あるいはどういった局面で使うのがベストなのか、それは現時点では未知数である(まだ市販されていない)。ただ印象的だったのが、この製品を開発するに当たって基準にしたのは、かつてのレコードやアナログ・テープが主流だった頃のオーディオの楽しさであるということだ。
つまりはCDの出現以来デジタル・アイテムがオーディオ界を席巻してきた中で、自分で工夫しながら好みの音を追求していた昔ながらのアナログ・オーディオの醍醐味を、アプリケーション上で再現しようというコンセプトを持っているらしい。やはりオーディオの(方法論としての)メイン・ストリームはアナログであると、レビンソン自身も認知しているのだろう。
なお、本ソフトはマッキントッシュ専用。ウインドウズ用をリリースする予定は無いらしい。
会場ではフラッグシップ機のスピーカーであるM1が鳴らされていた。これは価格が一千万円を優に超える。確かに物理特性が高く練り上げられ、かつウェルバランスで聴きやすい音なのだが、これが果たして一千万円以上の価値があるかどうかは意見が分かれることだろう。ともあれ超ハイエンドオーディオ機器の値段設定は、私の理解の外にある(爆)。
(この項つづく)
講演は3月28日の金曜日に行われた。いくら始まるのは夕刻とはいえ、平日だ。数日前から長時間の残業をして仕事を前倒しで片付け、当日は午後から有給休暇を取り(とはいっても、実際は職場を出るのが遅れ、会場にたどり着いたのは開始ギリギリの時間だったが ^^;)、何とか入場することが出来た(苦笑)。

主宰者側の事前の情報から、講演の主な内容は彼が新たに立ち上げたブランドであるDANIEL HERTZのアンプやスピーカーのデモンストレーションだと思っていたのだが、実際は違った。何と今回のレクチャーの主眼は、MASTER CLASSと命名された同ブランドの音楽ソフトウェアだったのだ。
音楽ソフトとはいっても、iTunesのような単なるプレーヤー兼ファイル管理用アプリケーションではない。これはイコライザーである。あらゆる種類の音楽ファイルのトーン・バランスを補正することが可能で、いわば聴感上の帯域を自分好みにカスタマイズ出来るというシロモノだ。しかも、補正したファイルはそのまま保存が出来るという。
私は技術的なことに関しては疎いのでハッキリしたことは言えないが、早い話が、とても良く仕上げられた(アプリケーション上の)トーン・コントロールらしい。80年代にレビンソンは“透明なトーン・コントロール”という触れ込みのチェロ・オーディオ・パレットという規格を発表したことがあったが、今回のMASTER CLASSはそれをデジタル領域で実現したということだろう。

このソフトウェアの機能が実際どの程度の威力を発揮するのか、あるいはどういった局面で使うのがベストなのか、それは現時点では未知数である(まだ市販されていない)。ただ印象的だったのが、この製品を開発するに当たって基準にしたのは、かつてのレコードやアナログ・テープが主流だった頃のオーディオの楽しさであるということだ。
つまりはCDの出現以来デジタル・アイテムがオーディオ界を席巻してきた中で、自分で工夫しながら好みの音を追求していた昔ながらのアナログ・オーディオの醍醐味を、アプリケーション上で再現しようというコンセプトを持っているらしい。やはりオーディオの(方法論としての)メイン・ストリームはアナログであると、レビンソン自身も認知しているのだろう。
なお、本ソフトはマッキントッシュ専用。ウインドウズ用をリリースする予定は無いらしい。
会場ではフラッグシップ機のスピーカーであるM1が鳴らされていた。これは価格が一千万円を優に超える。確かに物理特性が高く練り上げられ、かつウェルバランスで聴きやすい音なのだが、これが果たして一千万円以上の価値があるかどうかは意見が分かれることだろう。ともあれ超ハイエンドオーディオ機器の値段設定は、私の理解の外にある(爆)。
(この項つづく)