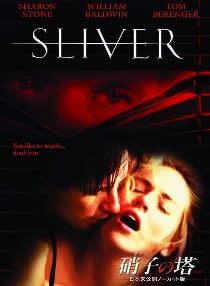(英題:THE WIND WILL CARRY US)99年イラン作品。数々の傑作・秀作をモノにした巨匠アッバス・キアロスタミ監督の、唯一の凡作である。題材に目新しさは無く、キャストの扱い方も平板。ストーリーは面白くも何ともない。キアロスタミ得意のドキュメンタリー的手法も、段取りを間違えると空振りに終わる。
TVディレクターのベーザード率いるロケ隊は、テヘランの北700キロにある山村にやってくる。目的は、そこで行われる珍しい葬儀の取材である。ところが、亡くなるはずだったおばあさんが回復。一行は予定の日程を終えるまで、村でやることも無く過ごす羽目になる。そんな中、知り合いになった穴掘り人夫が生き埋めになるという事故が発生。偶然に現場に居合わせたベーザードは、村人達に助けを求める。
人の生死が俎上にのせられているのは、前作「桜桃の味」(97年)の繰り返しで新味に乏しい。しかも、今回はエピソードにひねりが足りない分、間延びした印象しか受けない。特に前半の、起伏のまるでない展開は、観客に居眠りしろと言わんばかりの芸のなさ。
ベーザードの元には幾度となく上司からの問い合わせの電話が入るのだが、電波の入りが良くないため、そのたびに村で一番高い墓のある丘まで行かなければならない。一応はギャグのつもりなのだろうが、繰り出すタイミングが悪くて少しも笑えない。終盤になってようやくドラマが動き出すという感じだが、それまでの持って行き方に工夫が無いので“時すでに遅し”である。
ただし、映像は冴え冴えと美しい。ベーザードが亀やフンコロガシの行動を観察するシーンも面白い。またイラン映画特有の“子供の扱い方”には、やっぱり感心してしまう。その意味では“観る価値は全然なし”とは言えない。だが、これがキアロスタミの映画かと思うと、採点が辛くなるのは仕方がないだろう。
主演のベーザード・ドーラニーは本来は撮影スタッフであり、プロの俳優ではない。だが、この“素人起用”も不発だ。誰がやってもいい役だし、そもそもディレクターと撮影係では立場も役割も違うわけで、本人性を前面に出しても効果は上がらない。なお、なぜか同年のヴェネツィア国際映画祭で審査員特別賞を獲得。その事実も納得できない(笑)。