一見よくあるパラレルワールドを扱ったSF小説のように思えるが、娯楽性は極めて薄く、読後の印象は実に苦い。この本にファンタジー的な御膳立ての作品にありがちなドンデン返しやカタルシスを求めても、無駄なことだ。ならば面白くないのかというと、そうではない。少しでも“本を読んで考えさせられる”ことを求めているのならば、本書は価値があるといえよう。
金沢市に住む高校生の主人公は、鬱屈した日々を送っていた。両親の仲は冷え切っており、兄は交通事故で植物状態、しかも付き合っていた彼女が不慮の事故でこの世を去ってしまう。捨て鉢な気分で足を運んだ東尋坊で、彼は断崖から転落。ところが死んだはずの彼は、気が付くと街中にいるではないか。
腑に落ちぬまま自宅に帰ると、そこには見知らぬ“姉”がいて、自分自身は存在していないことになっている。どうやら“自分が生まれていなかった世界”に迷い込んでしまったらしい。彼は自らが不在であった世界の有様を見聞きするうちに、自分自身の存在価値は何なのかを自問自答していく。
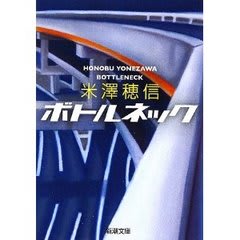
正直言ってこの作者の文体はさほど達者ではなく、歯切れが悪い。特に中盤まではストーリー展開が遅いせいもあり、読むのが苦痛に感じた。ところが終盤近くになると、エンタテインメントに振られたような設定とは裏腹な厳しいテーマ設定が明らかになり、けっこう引き込まれてしまう。
自分は何のために生まれてきたのか、この世界にとっての“ボトルネック”とは何なのか、その回答が引き出されるラストはかなり辛い。特に最後に届くメールの一文など、ここまでやるかと思わせるほどの辛辣さだ。
しかし、何があろうと、それでも人生は続いていくのである。本作の救いは、主人公がまだ若いということだ。これが中年以上の人間の身に降りかかったとしたら、シャレにならないだろう。まさに地獄に向かって一直線だ(まあ、それも小説としては面白くなるかもしれないが ^^;)。
米澤は映画化された「インシテミル」(私は未読)の作者でもあるが、本作を読む限り目の付け所が通常とは半歩ずれたようなオフビートな妙味があると思った。また機会があれば著作をチェックしてみたい。
金沢市に住む高校生の主人公は、鬱屈した日々を送っていた。両親の仲は冷え切っており、兄は交通事故で植物状態、しかも付き合っていた彼女が不慮の事故でこの世を去ってしまう。捨て鉢な気分で足を運んだ東尋坊で、彼は断崖から転落。ところが死んだはずの彼は、気が付くと街中にいるではないか。
腑に落ちぬまま自宅に帰ると、そこには見知らぬ“姉”がいて、自分自身は存在していないことになっている。どうやら“自分が生まれていなかった世界”に迷い込んでしまったらしい。彼は自らが不在であった世界の有様を見聞きするうちに、自分自身の存在価値は何なのかを自問自答していく。
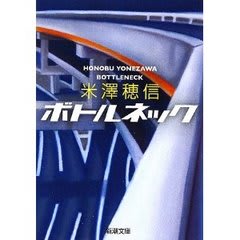
正直言ってこの作者の文体はさほど達者ではなく、歯切れが悪い。特に中盤まではストーリー展開が遅いせいもあり、読むのが苦痛に感じた。ところが終盤近くになると、エンタテインメントに振られたような設定とは裏腹な厳しいテーマ設定が明らかになり、けっこう引き込まれてしまう。
自分は何のために生まれてきたのか、この世界にとっての“ボトルネック”とは何なのか、その回答が引き出されるラストはかなり辛い。特に最後に届くメールの一文など、ここまでやるかと思わせるほどの辛辣さだ。
しかし、何があろうと、それでも人生は続いていくのである。本作の救いは、主人公がまだ若いということだ。これが中年以上の人間の身に降りかかったとしたら、シャレにならないだろう。まさに地獄に向かって一直線だ(まあ、それも小説としては面白くなるかもしれないが ^^;)。
米澤は映画化された「インシテミル」(私は未読)の作者でもあるが、本作を読む限り目の付け所が通常とは半歩ずれたようなオフビートな妙味があると思った。また機会があれば著作をチェックしてみたい。


































