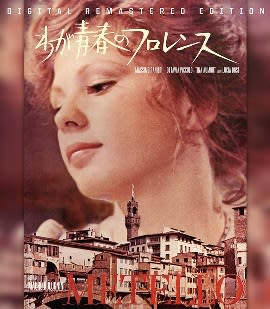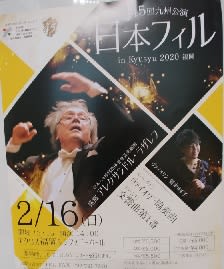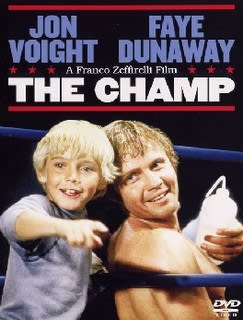御都合主義的なモチーフや無理筋の展開が目立つが、それでもこの映画を評価したい。斬新な主題と、キャスト(特に主演)の目を見張る働きにより、大きな求心力を獲得している。また、これが長編第一作になる新鋭監督の素質と将来性をも感じさせる。第69回ベルリン国際映画祭にて、パノラマ部門の観客賞及び国際アートシアター連盟賞を受賞。
23歳の貴田ユマは、生まれた時に37秒間呼吸が止まっていたことが原因で脳性まひになり、車椅子生活を送っている。両親は離婚しており、母親との二人暮らしだ。母親の恭子は熱心にユマの面倒を見ているのだが、明らかに過保護で娘に自由な行動をさせない。
ユマは漫画家である友人のSAYAKAのアシスタント(という名のゴーストライター)をしてわずかな収入を得ているが、そんな境遇に満足できず、ある日自作の漫画を出版社に持ち込む。だが、編集長は“いい作品を手掛けるには、人生経験(主に異性関係)を積まないとダメだ”と一蹴。そこでユマは、初めて母親の庇護から離れて自分の思い通りに振る舞うことを決意する。
ユマの父親はどうして出て行ったのか分からず、また主人公が性格の悪そうなSAYAKAの下働きに甘んじている理由も不明。ユマは歓楽街で舞という頼りになる年上の女と出会うのだが、その経緯が不自然。さらに後半は自らの家族の秘密を探るために、ユマは長い旅に出るのだが、唐突な展開であることは否めない。
しかしながら、主演女優の存在感はそれらの欠点を忘れさせるほど大きい。ユマに扮する佳山明はこれが映画初出演だが、彼女は本物の身障者だ。その、自らをさらけ出したような捨て身の熱演には圧倒させる。序盤の、母親と入浴するシーンには驚かされたが、続く歓楽街に単身乗り込むシークエンスや、不自由な身体をものともせずに遠くへ旅に出かけるくだりには感心するしかない。
そして、本作は“ハンデを持った女性の性欲”を正面から取り上げた初めての作品かもしれない。今までベン・リューイン監督の「セッションズ」(2012年)や松本准平監督の「パーフェクト・レボリューション」(2017年)のように“身障者の男性の性欲”にスポットを当てた作品は存在したが、女性は珍しい。しかも本作ではセンセーショナルに扱わず、セックスを主人公が外界に接する媒体として機能させている。脚本も担当したHIKARI監督も女流であることも大きいと思うが、これは慧眼と言えよう。
母親に扮する神野三鈴と舞を演じる渡辺真起子のパフォーマンスも素晴らしく、ドラマを絵空事にさせないことに貢献している。板谷由夏や大東駿介、萩原みのり、芋生悠といった脇のキャストも万全だ。感動的なラストも含めて、観た後の満足感は大きい。江崎朋生とスティーヴン・ブラハットによる撮影、アスカ・マツミヤの音楽も及第点だが、CHAIによる挿入曲が最高だ。