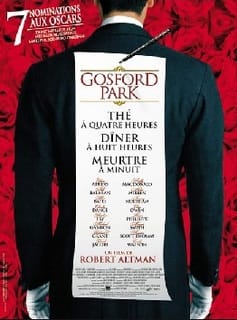(原題:AUS DEM NICHTS)第90回アカデミー賞の外国語映画賞ドイツ代表作品ということだが、どうにもパッとしない内容。とにかく、主人公にまったく感情移入出来ないことが致命的で、鑑賞中はシラけた空気だけが周囲に充満する。また物語の背景が説明不十分であり、これでは高得点を付けるわけにはいかない。
ハンブルクに住むカティヤは、麻薬売買で服役していたトルコからの移民であるヌーリと、彼の出所後に結婚。やがて息子が生まれて平穏な日々を送っていた。しかしある日、夫が働く事務所の前で爆弾が爆発し、ヌーリと愛息ロッコが死亡する。警察の捜査の結果、移民を狙ったテロであることが判明。容疑者は早々に逮捕され、裁判は有罪確実かと思われていた。しかし、わずかな証拠の不備により、被告は無罪になってしまう。悲しみに暮れるカティヤは、憎悪と絶望のあまり、ある重大な決断をする。

確かに、カティヤの身に降りかかる災難は理不尽極まりない。しかし、全面的に同情出来るかというと、断じてそうではない。まず、いくら足を洗っているとはいえ、夫ヌーリは前科者だ。もちろん、そんな言い方は差別であるとの誹りを受けるだろうが、主人公の配偶者が一般人よりも“狙われやすい”対象であるのは事実だ。
さらに極めつけは、彼女は麻薬常習者であること。しかも、あろうことか公判期間中に担当弁護士から麻薬を分けてもらっている。ドイツではどうだか知らないが、日本ならば即逮捕だ。身体中に意味ありげなタトゥーを彫り、なぜか場違いな理系のスキルを持っていて爆弾を簡単に製造したりする。そんな怪しげな女が悲劇のヒロインとしてスクリーンの真ん中に居座っても、観ているこちらは困惑するしかない。

裁判そのものも噴飯物で、誰がどう見ても被告を有罪に持ち込む証拠は揃っている。百歩譲って第一審が不本意な結果になっても、控訴審では容易にひっくり返せる案件だろう。そのことを無視するかのように勝手な“決断”に突き進むヒロインの姿勢には、違和感しか覚えない。
テロを行ったのはネオナチのグループであることが示されるが、見た目はカタギの者達がどうして狂信的な思想にハマり込んでいるのか、その具体的な理由を示す描写は無い。ひょっとしたらドイツでは説明不要な自明の理であるのかもしれないが、ヨソの国の人間としては“関係の無い”話だと片付けられよう。
ファティ・アキンの演出はメリハリに欠け、ドラマティックな話であるにも関わらず盛り上がらない。主演のダイアン・クルーガーは熱演だが、前述のようにキャラクターの設定に難があるので、諸手を挙げての高評価は差し控える。
ハンブルクに住むカティヤは、麻薬売買で服役していたトルコからの移民であるヌーリと、彼の出所後に結婚。やがて息子が生まれて平穏な日々を送っていた。しかしある日、夫が働く事務所の前で爆弾が爆発し、ヌーリと愛息ロッコが死亡する。警察の捜査の結果、移民を狙ったテロであることが判明。容疑者は早々に逮捕され、裁判は有罪確実かと思われていた。しかし、わずかな証拠の不備により、被告は無罪になってしまう。悲しみに暮れるカティヤは、憎悪と絶望のあまり、ある重大な決断をする。

確かに、カティヤの身に降りかかる災難は理不尽極まりない。しかし、全面的に同情出来るかというと、断じてそうではない。まず、いくら足を洗っているとはいえ、夫ヌーリは前科者だ。もちろん、そんな言い方は差別であるとの誹りを受けるだろうが、主人公の配偶者が一般人よりも“狙われやすい”対象であるのは事実だ。
さらに極めつけは、彼女は麻薬常習者であること。しかも、あろうことか公判期間中に担当弁護士から麻薬を分けてもらっている。ドイツではどうだか知らないが、日本ならば即逮捕だ。身体中に意味ありげなタトゥーを彫り、なぜか場違いな理系のスキルを持っていて爆弾を簡単に製造したりする。そんな怪しげな女が悲劇のヒロインとしてスクリーンの真ん中に居座っても、観ているこちらは困惑するしかない。

裁判そのものも噴飯物で、誰がどう見ても被告を有罪に持ち込む証拠は揃っている。百歩譲って第一審が不本意な結果になっても、控訴審では容易にひっくり返せる案件だろう。そのことを無視するかのように勝手な“決断”に突き進むヒロインの姿勢には、違和感しか覚えない。
テロを行ったのはネオナチのグループであることが示されるが、見た目はカタギの者達がどうして狂信的な思想にハマり込んでいるのか、その具体的な理由を示す描写は無い。ひょっとしたらドイツでは説明不要な自明の理であるのかもしれないが、ヨソの国の人間としては“関係の無い”話だと片付けられよう。
ファティ・アキンの演出はメリハリに欠け、ドラマティックな話であるにも関わらず盛り上がらない。主演のダイアン・クルーガーは熱演だが、前述のようにキャラクターの設定に難があるので、諸手を挙げての高評価は差し控える。