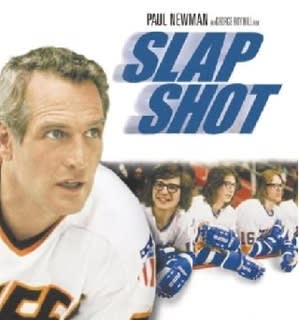(原題:SHE SAID)本作を観て思い出したのが、アラン・J・パクラ監督の「大統領の陰謀」(76年)だ。新聞社を舞台に、2人の記者が社会問題に挑む実録映画という形式は共通している。もっとも、あの映画の題材はウォーターゲート事件で、対して本編で扱っているのは有名映画プロデューサーのセクハラ案件だ。だからネタとしては軽量級かと思われるかもしれない。しかし、社会的影響度に関しては大統領の政治スキャンダルに勝るとも劣らない。映画のクォリティもアカデミー賞候補になったパクラ作品に肉薄している。
ニューヨーク・タイムズ紙の記者ミーガン・トゥーイーとジョディ・カンターは、大手映画会社“ミラマックス”の設立者であり、敏腕プロデューサーとしても知られたハーヴェイ・ワインスタインが女優や女性スタッフなどに対して性的暴行をはたらいているという話を聞きつけ、独自に取材を開始する。すると、ワインスタインの悪行は常態化しており、彼はこれまで何度もマスコミの記事をもみ消してきたことを知る。今回もニューヨーク・タイムズ紙は妨害を受けるが、2人はこのヤマを逃すことを潔しとせず、果敢に対象にアタックする。トゥーイーとカンターによるルポルタージュの映画化だ。

主人公2人は家庭を持っており、決して仕事一辺倒のジャーナリストではない。特にトゥーイーは劇中で子供を持つことになる。決して独りよがりにもヒステリックにもならず、上司や同僚たちとの関係も良好に保ちつつ、粛々とミッションを遂行する。彼女たちの境遇に比べると、ハリウッドの有様には言葉を失うしかない。
よく“芸能界は一般世間の常識が通用しない場所だ”というような物言いをする向きを見掛けるが、だからといって“ギョーカイでは何でもあり”という結論に何の疑問もなく行き着いてしまうのは、思考停止でしかない。昔はそれが通用していたというのも、言い訳にもならないのだ。
マリア・シュラーダーの演出は余計なケレンを配した正攻法のもの。真正面から問題に取り組む覚悟が窺える。トゥーイーに扮するキャリー・マリガンのパフォーマンスには、初めて感心した。役柄を選べば、真価を発揮する俳優だ。カンター役のゾーイ・カザンの抑制の効いた演技も申し分ない。
パトリシア・クラークソンにアンドレ・ブラウアー、ジェニファー・イーリーといった他のキャストも良好だが、アシュレイ・ジャッドが本人役で出ているのはインパクトが大きい。それだけ事は重大であり、いわゆる#MeToo運動の嚆矢になった出来事は、断じて芸能ネタで終わらせてはならないという作者の気迫が感じられる。ナターシャ・ブライエによる撮影、ニコラス・ブリテルの音楽、共に及第点である。
ニューヨーク・タイムズ紙の記者ミーガン・トゥーイーとジョディ・カンターは、大手映画会社“ミラマックス”の設立者であり、敏腕プロデューサーとしても知られたハーヴェイ・ワインスタインが女優や女性スタッフなどに対して性的暴行をはたらいているという話を聞きつけ、独自に取材を開始する。すると、ワインスタインの悪行は常態化しており、彼はこれまで何度もマスコミの記事をもみ消してきたことを知る。今回もニューヨーク・タイムズ紙は妨害を受けるが、2人はこのヤマを逃すことを潔しとせず、果敢に対象にアタックする。トゥーイーとカンターによるルポルタージュの映画化だ。

主人公2人は家庭を持っており、決して仕事一辺倒のジャーナリストではない。特にトゥーイーは劇中で子供を持つことになる。決して独りよがりにもヒステリックにもならず、上司や同僚たちとの関係も良好に保ちつつ、粛々とミッションを遂行する。彼女たちの境遇に比べると、ハリウッドの有様には言葉を失うしかない。
よく“芸能界は一般世間の常識が通用しない場所だ”というような物言いをする向きを見掛けるが、だからといって“ギョーカイでは何でもあり”という結論に何の疑問もなく行き着いてしまうのは、思考停止でしかない。昔はそれが通用していたというのも、言い訳にもならないのだ。
マリア・シュラーダーの演出は余計なケレンを配した正攻法のもの。真正面から問題に取り組む覚悟が窺える。トゥーイーに扮するキャリー・マリガンのパフォーマンスには、初めて感心した。役柄を選べば、真価を発揮する俳優だ。カンター役のゾーイ・カザンの抑制の効いた演技も申し分ない。
パトリシア・クラークソンにアンドレ・ブラウアー、ジェニファー・イーリーといった他のキャストも良好だが、アシュレイ・ジャッドが本人役で出ているのはインパクトが大きい。それだけ事は重大であり、いわゆる#MeToo運動の嚆矢になった出来事は、断じて芸能ネタで終わらせてはならないという作者の気迫が感じられる。ナターシャ・ブライエによる撮影、ニコラス・ブリテルの音楽、共に及第点である。