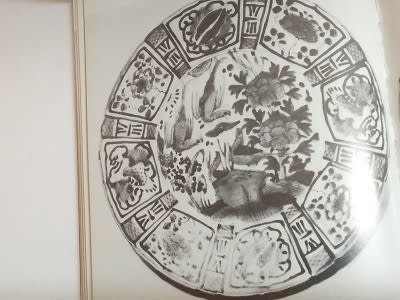今回は、「染付 芙蓉手 兜形大皿」の紹介です。
ところで、ここのところ、連続して古伊万里を紹介していましたが、ここにきて、所蔵品の殆どを紹介してしまい、紹介すべき在庫が枯渇してしまいました(><)
また、最近、骨董市や古美術品交換会で古伊万里を手に入れることも困難になってきてしまいましたので、紹介する古伊万里の補充も出来なくなってしまいました。そこで、やむを得ず、インターネットを利用して手に入れることを思いたち、この「染付 芙蓉手 兜形大皿」を手に入れたという次第です。
そんなことで、この大皿は、先日の12月3日に、徳島県のほうから、はるばるとやってきたものです(^_^)
そのような事情ですので、これからは、古伊万里の紹介は 入手してからとなりますので、たまにの紹介となってしまいますことをご承知ください(~_~;)
前置きが長くなりました。それでは、さっそく、この「染付 芙蓉手 兜形大皿」の紹介に入ります。

表面
ちょっと焼が甘かったようで、全面甘手という感じです。
また、比較的に薄造りで、手取りは軽く感じられます。

上半分の拡大写真

右半分の拡大写真

下半分の拡大写真

左半分の拡大写真

中央部の拡大写真

側面

底面を斜め上から見た面

底面
オランダ東インド会社は、中国産の磁器を買い付け、それをヨーロッパに輸出していたわけですが、中国が遷界令を出したため、それが出来なくなりました。そこで、オランダ東インド会社は、そのピンチヒッターとして有田に目を付けるようになり、大量の注文を有田にしてきました。万治2年(1659)のことでした。
その注文品には、それまで中国で作られていた、このような芙蓉手と言われた大皿も含まれていたようです。
有田では、万治2年(1659)には、このオランダ東インド会社からの注文に応じたヨーロッパ向け輸出焼造体制を本格化させ、万治に続く、寛文・延宝時代には盛んに輸出したようです。
この「染付 芙蓉手 兜形大皿」は、そのような寛文・延宝時代に作られたものではないかと思われます。
なお、この大皿は尺3寸あるんですが、意外と手取りが軽いようです。江戸後期の大皿は、ずしりとした重さで、気合いを入れて持ち上げなければならないところですが、それに比べますと拍子抜けするほどに軽く感じられます。
生 産 地 : 肥前・有田
製作年代: 江戸時代前期(寛文・延宝時代)
サ イ ズ : 口径;38.8cm 高さ;7.2cm 底径;17.1cm
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
追 記(令和3年12月24日)
この記事を読まれた故玩館館主の遅生さんが、この芙蓉手大皿に似た大皿について書かれた文献を探し出してくれ、それを教えてくれました。
遅生さん、ありがとうございました(^-^*)
その文献というものは、次のようなものです(写真のみを転載)。
なお、この文献によりますと、伊万里芙蓉手大皿は、古染付芙蓉手大皿の写しだったとのことです。確かに、両者は良く似ていますね。
「蕾コレクションシリーズNo.12『臨時増刊 小さな蕾 古染付と呉須』(1982年刊)の86頁の写真を転載」
伊万里染付芙蓉手花鳥図皿(左、31.5㎝)と古染付芙蓉手花鳥図皿(右、30.7㎝)

上記写真の内の伊万里染付芙蓉手花鳥図皿のみの写真
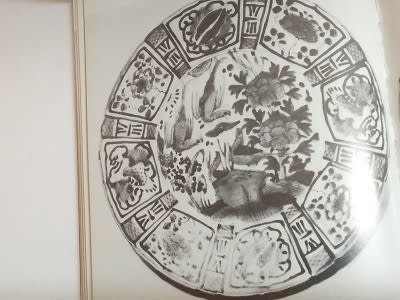
上記の写真の内の古染付芙蓉手花鳥図皿のみの写真

また、「 世界をときめかした 伊万里焼 」(矢部良明著 角川書店 平成12年初版発行)には、
「 3 古染付を手本とした伊万里草創期
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この天神森七号窯の出土陶片は、古染付の丸写しのほか、早くも古染付以外の中国絵画を原図とした作例が多くを占めていたことも指摘しておきたい。その染付の呈発はすこぶる良好で、染付の描写力や筆法も的確であり、天狗谷窯のややぼやけた染付を見てきた者にとっては、いかにも力のこもった陶工たちの熱気が伝わってきて、草創期ならではの勢いを感じずにはいられないものがあった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (P.13)」
とありますので、この文献によりますと、この芙蓉手大皿は、伊万里の草創期の頃に焼かれたと言っても過言ではなさそうです(^-^*)