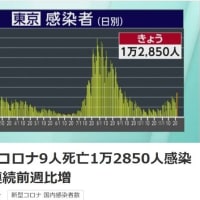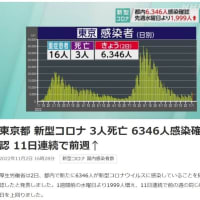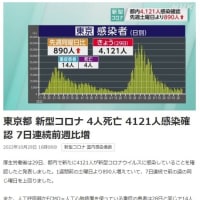「業務断れず限界まで」「眠るのが怖い」20代教員に心の病増加…過重業務で適応障害、自殺も
2022/10/24 05:00
(読売新聞)
心の病を抱える若い教員が増えている。2020年度までの5年間で、精神疾患で休んだ20代教員の在職者に占める割合は1・5倍へと増えた。仕事を苦に自殺を図る20代教員の割合も、ほかの年代の教員と比べて高い傾向がみられる。文部科学省は来年度、公立学校の教員のメンタル対策に本格的に乗り出す。(佐々木伶)
「業務を断れず、限界までがんばってしまった」
2017年、当時29歳だった大阪府立高校教諭の男性(34)の心身に異変が表れた。
学級担任や部活動に加え、生徒のオーストラリアへの海外研修の調整や引率を任された。連日深夜まで働き、休みは部活動のない定期テストの期間中だけだった。
海外研修の直前、頭痛や胸の痛みを覚えた。受診すると、医師から「1か月は就労不可」と言われた。だが、代わりに引率できる教員がおらず、診断書を病院に返還した。「自分がやらなければ、困るのは生徒だと思った」からだ。
その後、適応障害と診断され、休職を繰り返した。現在は復帰しているが、薬と通院は欠かせない。男性は「業務量を減らせないなら、教員を増やすしかないのでは」と訴える。
福井県美浜町の団体職員の男性(62)は数年前、教員になりたての長男(享年27歳)を自殺で失った。残された日記には、仕事での苦悩がつづられていた。
長男は福井県内の中学校の正規教員となった1年目、学級担任や社会科、野球部の副顧問に加え、専門外の体育を担当。指導困難な生徒の保護者にも対応した。「過労死ライン」とされる月の残業80時間を最大90時間超えていた。
長男の日記には、仕事に追われる様子が記されていた。「授業の準備が追いつかず、眠るのが怖い」「(保護者に)どう話しても烈火のごとく反撃がくる」「終わりを感じ、涙が出そうになる時がある」――。
男性は17年2月、学校側に安全配慮義務違反があったとして県と町を相手に約1億円を求めて提訴。福井地裁は19年7月、業務と自殺の因果関係を認め、県と町に約6540万円の賠償を命じた。
判決では、「過重労働は明らかだったのに、(管理職が)業務を変更するなどの義務を怠った」と指摘。長男が自殺前に精神疾患を発症していたことも認定した。
日記には「新しい方法での1年生の授業では、分かりやすかったと感想をもらえた」との手応えもあった。男性は「息子は子どもたちのために弱音も吐かず、一生懸命に仕事をしていたのに」とつぶやいた。
ベテラン大量退職、相談機会少なく
文科省によると、20年度に心の病が原因で1か月以上休んだ公立学校教員は9452人に上った。20代の教員に占める割合は1・43%(2140人)で、16年度の0・91%(1286人)から1・5倍へと増えている。
警察庁のデータを基に厚生労働省がまとめた資料によると、21年までの5年間に自殺した20代教員61人のうち、「勤務問題」が理由に含まれていたのは49%と半数を占めた。ほかの年代では、30代が32%、40代が35%、50代は44%だった。
背景には、教員不足や団塊世代の大量退職で若い教員の業務負担が増えていることがあるとみられる。
担当外の教科を教えることが増えたほか、新任教員もすぐに学級を担任し、保護者対応をするようになった。ある中学校長は「若手に多くの業務が集中する一方、ベテランの不在で相談する機会が減っている。管理職も忙しく、若手をケアする余裕もない」と漏らす。
文科省は来年度予算の概算要求で、教員のメンタルヘルス対策の調査研究事業に9000万円を新規に計上した。自治体に委託し、病気休職の原因分析や対策の効果を検証する。成果のあったモデル事業を新たな施策として全国に広げたい考えだ。担当者は「教員不足のなか、若手休職者の増加は学校現場をさらに窮迫させる」と危機感をもつ。
教員の働き方に詳しい小川正人・東京大名誉教授は「多くの業務を抱え、経験の少ない若手教員は自分を追い詰めるような働き方になりがちだ。管理職は業務量や労働時間を把握し、適切に配分するよう努め、相談しやすい雰囲気を作ることが必要だろう」と話している。