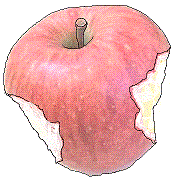
宇野重規の『トクヴィル 平等と不平等の理論家』(講談社選書メチエ)を読み進む速度が、第2章をすぎてから落ちたままで、なかなか進まない。
それは、第2章の終わりに「個人主義」という言葉が出てきてからである。私は、「個人主義」というものを真面目に考えたことがなかった。
きょう、つぎのウィキペディアの言葉を読んで、この呪縛から解放された
〈「個人主義」は、多義的な言葉であって、個々の言説が意味するところは一様ではない。もともとは啓蒙主義に対する非難を意味する言葉であった。〉
そうなんだ。定義はどうでも良い。宇野が「個人主義」をどう捉えているかだ。自分は宇野に同意しなくて良いのだ。
宇野は、『トクヴィル』の2章3節に、つぎのように書く。
〈したがって、「個人主義」という言葉が、「反動」の思想家とされるメーストルらによって用いられ、その後、「社会主義」の思想家であるサン=シモン派によって普及することになったという事実は、きわめて象徴的である。〉
宇野は、「個人主義」という言葉が、超保守主義者と社会主義者からの、ののしり言葉として、歴史的に生まれたと言っているのだ。みずから、個人主義と名乗ったのではなく、まわりから、非難されることで自然に生まれてきた言葉で、政治的思想的立場によって意味が異なる。
そして、宇野は、あきらかに、無定義語の「個人主義」を擁護しており、無難なものにみせようとしている。だから、「利己主義」と「個人主義」とを区別するトクヴィルの言葉を、宇野は引用したのだ。
〈利己主義は熱烈で度を越した自己愛であり、何ごとも自分だけにひきつけ、すべてを措いて自己を選ぶ態度に人を導くものである。個人主義は静穏な思慮ある感情であって、個々の市民を同胞の群れから引き離し、家族と友人との別世界に引きこもらせる〉
これは、たんに宇野やトクヴィルが慎重(私は臆病というが)であるからで、「個人主義」の説明として不適切である。とくに、「家族と友人との別世界に引きこもらせる」は個人主義の規定としては承諾できない。
「個人」というものを強く打ち出している思想家に、『自由からの逃走』を書いたエーリッヒ・フロムがいる。彼は、「自由(freedom)」と「個人(individual)」とを結びつけている。彼の主張の1つは「個人」がなければ「自由」の要求がないということである。
「自由」「個人」「平等化」「デモクラシー」は、近代の思想を形作る一連の概念なのだ。
個人主義とは、アナキーにつながる思想なのである。トクヴィルがアメリカで見出したのは、徳や節制や規制がなくても、社会が自立的に機能するということである。これは、まさに、アナキーの主張である。
安倍晋三も菅義偉も、総理大臣だから、偉いのではない。行政府が国民へのサービス機関として運営されているかの監督をゆだねられているだけで、私たちを統治してくださいと頼んだ覚えはない。
宇野がトクヴィルを愛するのは彼の勝手であるが、つぎの言葉も適切でない。
〈この個人はすべてを自分で判断したいと思う。しかしながら、トクヴィルに言わせれば、すべてを自分で1から考え直すことなど、人間には不可能である。人は自覚的に・無自覚的に、つねに一定の事柄を前提に、その権威に頼ってものを考えているからである。〉
個人は自分以外に権威を認める必要はない。自然科学に関わる者は、「すべてを自分で1から考え直す」べきである、と思う。
2018年にノーベル賞をもらった本庶佑は、つぎのように言う。
〈教科書に書いてあることが全部正しいと思ったら、それでおしまいだ。教科書は嘘だと思う人は見込みがある。丸暗記して、良い答案を書こうと思う人は学者には向かない。『こんなことが書いてあるけど、おかしい』という学生は見どころがある。疑って、自分の頭で納得できるかどうかが大切だ〉
人間は愚かな生き物である。先人も愚か者である。集団の意見も愚かである。あらゆる権威を否定し、自分で考え直すのが当然である。
宇野はつぎのように書く。
〈トクヴィルはやがて懐疑を近代的人間の1つの本質であると考えるようになる。しかしながら、懐疑は人にたしかな血を与えてくれるよりはむしろ、不安、苦しみ、孤独へと導くものであった。〉
懐疑は、不安、苦しみとして捉えるより、個人として生きることの一部と考えれば、自分は自分であるという喜びに通じる。孤独は居心地のよいものである。












