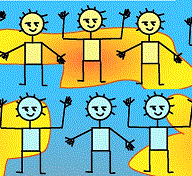きょうの朝日新聞のオピニオン面は、東京大学マーケットデザインセンター長の小島武仁へのインタビュー、『社会変えるマッチング』であった。ヨイショ記事であったので、老婆心から言いがかりのような感想を述べたい。
マーケットデザインセンター(UTMD)は東京大学大学院経済学研究科・経済学部に敷設された研究センターの1つである。他につぎがある。
日本経済国際共同研究センター(CIRJE)
金融教育研究センター(CARF)
経営教育研究センター(MERC)
政策評価研究教育センター(CREPE)
不動産イノベーション研究センター(CREI)
驚くべきことに、すべて実用的な研究センターである。いま、「実用的な」といったが、「実業界のため」といったほうが適切である。どうも、卒業生のポストを作るために、自民党政権下の文科省の賛同を得やすい研究センターを粗製乱造したとしか、思えない。
私の学生時代の大学院経済学研究科は、緑色のヘルメットをかぶった構造改革派フロントの拠点であった。マルクス経済学の教授も多かった。そのころのマルクス経済学は、線形計画経済学とかいって実質的にはマクロ経済学が多かったように覚えている。そこが、いつの間にか、実業界(経営者の集まり)にうける研究をする人間たちが東大の実権をにぎるようになったようだ。
小島のいっていることは100年前からあることだ。東大は、アメリカで名声を得ると雇用したがるところがある。アメリカでの名声とは、反共産主義であって、実業界に有用な人間であることだ。
ただ、不思議なことに、私の学生時代には、アメリカの大学には教養主義的な雰囲気があって、学問が時の権力から独立しているところがあった。当時、アメリカの研究者たちから、日本は自由な研究の伝統を壊す、と苦情を言われることが、たびたび、あった。それらは、主として、企業の研究所の精神的風土のことをさしていた。
いま、私が気になるのは、どうも、日本の大学の研究者の精神的風土も変質したのではないか、ということである。教養主義や学問の自由が大学から消えうせているのではないか。
J・K・ガルブレイスは『ゆたかな社会 決定版』(岩波現代文庫)で、実業界(大企業の重役)に沿う形で、経済学の通念がゆがめられていると、第9章、第10章、第11章、第12章で論じている。
第1の歪みは、「ものの生産の優位」である。必要だから生産するのではなく、生産するために生産するのである。国民総生産(GNP)の増加が政治で重視され、何が生産され、国民がどのように幸せになったかの議論がなされない。
第2の歪みは、「消費を煽るための宣伝と販売術」である。消費需要が生産限界を決めるというケインズの指摘が受け入れられると、消費欲望を煽るための宣伝と販売術が重視されるようになった。それまでは、競争相手に打ち勝つために、いち早く消費動向を知ることであったが、消費欲望を生産者側の大企業がつくるようになったのである。ガルブレイスは『ゆたかな社会』につぎのように書く。
《(近代的な)宣伝と販売術の目的は欲望をつくりだすこと》
《近代企業の戦術においては、ある製品の製造費よりもその需要をつくりだすための費用の方が重要である。》
私が外資系IT会社に務めたとき、電通や博文堂の人間が同じことを言っていた。また、トヨタから、宣伝費にお金をかけた方がよいか、それとも、販売店の報奨金を増やしたほうがよいかのために、効果の見積もり依頼が、コンサルタント会社にあった。
60年前のガルブレイスの時代より、歪みは、現在、より激しくなっている。ネット上のビッグデータで個人の消費動向がさぐれるようになると、押し込み販売というアイディアが生まれた。その1つが、マッチングデザインである。
小島は、「マッチング理論」の価値を売り込むために、待機児童の問題を取り上げている。
《いまは、希望する認可保育園に子どもが入れない親がいる一方で、定員割れする園もあります。多くの自治体は、家庭の状況をポイント化した点数を基に決めています》
《決定方法には、各園ごとにその園を第1希望にした人から点数の高い順に選ぶ方法と、全申し込み者の中から点数の高い人をまず選び、次にその人の希望園を見る方法の2種類があります。マッチング理論で考えると、前者は不公平で、後者の方が公平といえます》
問題は、認可保育園の定員絶対数が少なすぎるということと、認可保育園に人気のありなしがあるということではないか。あるべき解決策は、全体の定員数を増やすこと、また、人気の差を分析し、保育園側に問題があるのか、希望者側に問題があるのか、に応じて、当事者に改善を勧告すべきである。人気がない理由が、保育士が園児を虐待するのなら保育園側に改善してもらうしかない。通う近さの問題なら、近い人を優先する制度にすればよい。
私の人生経験からすると、マーケティング理論を唱える人もマッチング理論を唱える人も詐欺師にすぎない。自分を売り込むために次々と流行のキーワードをつくりだすのである。現代の政治家や実業人はこの詐欺師たちが好きである。