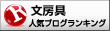BULOVAのゼンマイ切れ修理
BULOVAはチェコからの移民がアメリカで立ち上げた宝石店で、1911年から時計製造業に参入しアメリカで有数の時計メーカーになりました。
ゼンマイ巻上げが空回りして、動きません。おそらくゼンマイ切れだと思われます。香箱を開けてチェックします。

たぶん1920年代のスモールセコンドです。文字盤は汚れていますが、ステンレスのケースに入っていて、比較的良い状態です。針に腐蝕は全く見られません。

香箱を取り出すため香箱の受板と、ガンギ車と2番、3番、4番の受板も外しました。香箱の受板だけでは取り出せませんでした。輪列の組直しは、特にガンギ車も一緒に組み直すのは厄介なので、本当は外したくなかったんだけど・・・


香箱を取り出しました。上の写真、左の小さい歯車(丸穴車)は、リュウズの巻上げを右の香箱に直結している歯車(角穴車)に伝えるもので、止めネジは逆ネジです。ついつい忘れて外す時、緩めているつもりで左回しして締め上げてしまう・・・


香箱を開けて、軸と一緒にゼンマイを取り出します。

ゼンマイの幅を、ノギスで測ります。1.3mmです。
マイクログラインダーで、それぞれ交互に上下から切れ目を入れて差し込んで繋げることもできそうですが、その場合、強度が問題です。さてどうしますか・・・
ゼンマイ切れは私の経験では、すべて写真のように香箱の軸の近くで起こっています。香箱周辺部や途中で切れたものは、見たことがありません。曲げの曲率が大きいためでしょう。

ご覧のように4番車が香箱にかかっているのですが、そのまま香箱を取り出せたので、輪列を先に組み上げました。香箱のゼンマイを修復して、横からスライドしてはめ込めるでしょう。
輪列の組み上げは、特に受板が2番、3番、4番車とガンギ車が一緒になっているときは、なかなか入りません。0.3mmのステンレスワイヤーで自作したピンではめ込みます。5~6分程の時間を要します。
上手く軸穴に入っていないのに無理に受板のネジを締めつけると、歯車の軸を破損してしまいます。歯車の回り具合を確認しながら受板を取り付けます。
L字に曲げたピンの先端で、未だ軸穴に入っていない受板の下のガンギ車を動かして軸穴にはめ込みます。2番、3番、4番車は、比較的簡単に入ります。その段階で軽く受板をビス止めして、最後にL型ピンでガンギ車をはめ込みます。
切れたゼンマイは在庫はないのですが、ジャンクの部品取りなどで修理することも考えられます。
検討中・・・です。
~~~~~~~~~~~~ 

 ~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~








 ~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~