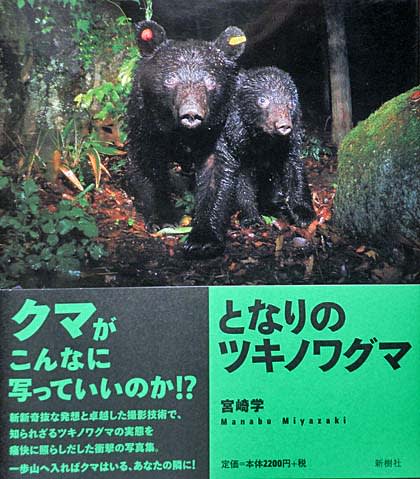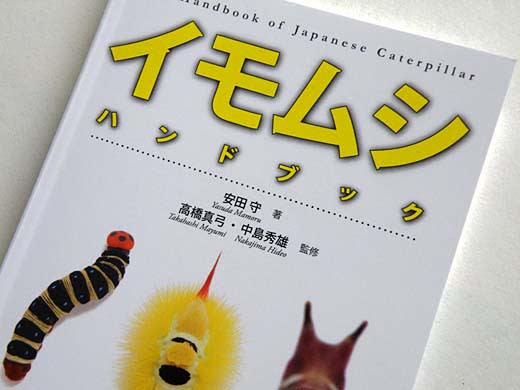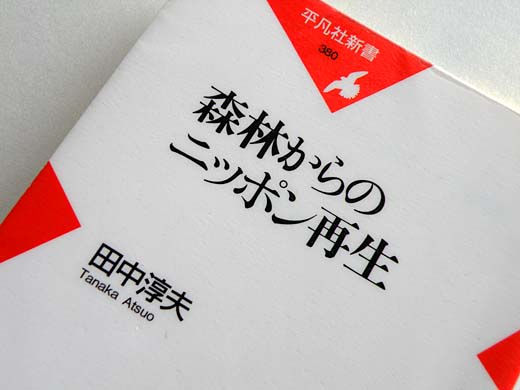昨日の記事に関連しますが、私が人前で発表をするときに参考にしている本を紹介します
理系のための口頭発表術 ~聴衆を魅了する20の原則~ 講談社ブルーバックス

話の組み立て方、スライドの作り方、話し方。とても参考になる本です。
書いてある通りに実践できるかどうかは別にして・・・(^^;)
理系のための口頭発表術 ~聴衆を魅了する20の原則~
序章 どんなにすばらしい研究もダメ発表がダメ研究にする
第1章 いかに準備すべきか
第2章 「面白い話」の構造
第3章 視覚素材はこう使え(使うな)
第4章 「話し方」の技術




今日は立春。
前橋の最高気温12.5℃。3月中旬並みの陽気でした。
ハクモクレン

さて、春と言えば桜。
すでにウェザーマップ社と日本気象協会は今年のさくらの開花予想を発表しており、前橋の開花は平年並みということです。待ち遠しいですね(^^)

ウェザーマップ『さくら開花予想2011』
日本気象協会 桜開花予想
理系のための口頭発表術 ~聴衆を魅了する20の原則~ 講談社ブルーバックス

話の組み立て方、スライドの作り方、話し方。とても参考になる本です。
書いてある通りに実践できるかどうかは別にして・・・(^^;)
理系のための口頭発表術 ~聴衆を魅了する20の原則~
序章 どんなにすばらしい研究もダメ発表がダメ研究にする
第1章 いかに準備すべきか
第2章 「面白い話」の構造
第3章 視覚素材はこう使え(使うな)
第4章 「話し方」の技術




今日は立春。
前橋の最高気温12.5℃。3月中旬並みの陽気でした。
ハクモクレン

さて、春と言えば桜。
すでにウェザーマップ社と日本気象協会は今年のさくらの開花予想を発表しており、前橋の開花は平年並みということです。待ち遠しいですね(^^)

ウェザーマップ『さくら開花予想2011』
日本気象協会 桜開花予想