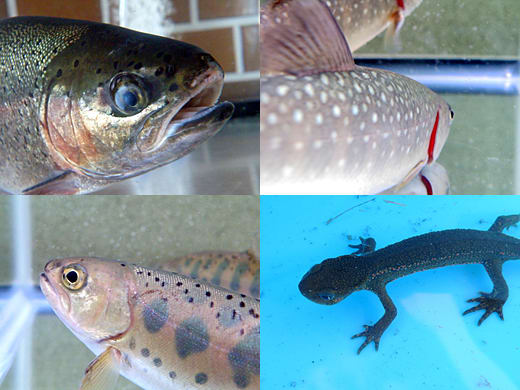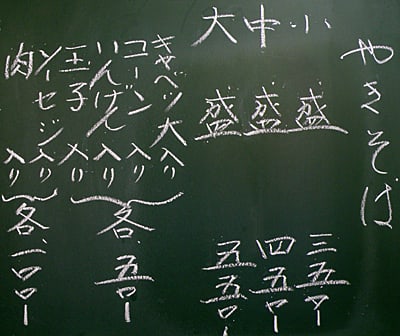10月26日(日)に南橘の自然観察と環境を守る会主催の自然観察会が橘山であったので、参加させて頂きました。
橘山は前橋市田口町と渋川市北橘町にまたがる標高228mの小山です。
約40万年前に火山活動によって誕生した赤城山は標高2,500mもありましが、約20万年前の大噴火で山頂部が吹き飛び、標高が1,500m程になってしまいました。
このときに発生した岩屑雪崩が赤城の斜面を利根川まで流れ下り堆積し、橘山、箱田山、十二山などを形成しました。
橘山はこのようにしてできた流れ山地形の一つです。赤城山の子供とも言えますね。
シロダモ 雄株

シロダモは宮城・山形以南に分布する常緑の中高木。クスノキ科シロダモ属。葉の裏側が白く見えます。
シロダモ 雌株

秋に花が咲き、翌年の秋に熟します。
アラカシ

橘山西斜面にはアラカシ林があり、この地域の原植生とされる貴重な群落です。
どんぐり クヌギ(上)とコナラ(下)

クヌギとコナラはどちらもシイタケ栽培の原木になります。
ところで、シイタケ栽培に革命的進歩をもたらした純粋培養菌種駒法を発明し、“きのこの慈父”とも呼ばれる森喜作氏(ドクターモリ)は群馬県桐生市出身。
詳しくは→森産業HP
ヒノキ

ヒノキの葉の裏をよく見ると Y Y Y Y Y Y Y・・・・・・・・・・・・・
白いYがたくさん見えます。
トキリマメ

別名オオバタンキリマメ
赤いサヤが割れると中から黒い豆が顔を出します。

ヒヨドリジョウゴの実

ヒヨドリジョウゴはナス科の多年生ツル植物。
実は赤くて美味しそうに見えますが、口に入れてはいけません。ソラニンを含んでいるの中毒を起こす危険があります。
コカマキリ

鎌の内側に目立つ模様があるのが特徴です。
オオカマキリの卵鞘

卵鞘のなかに卵が200~300個入っています。
カマキリの卵鞘は種類によって形や大きさが異なります。
橘山の南斜面には、昨年11月、地元の方々により100本の山桜の苗木が植えられました。
将来、橘山は桜の名所になることでしょう。楽しみです(^^)
橘山は前橋市田口町と渋川市北橘町にまたがる標高228mの小山です。
約40万年前に火山活動によって誕生した赤城山は標高2,500mもありましが、約20万年前の大噴火で山頂部が吹き飛び、標高が1,500m程になってしまいました。
このときに発生した岩屑雪崩が赤城の斜面を利根川まで流れ下り堆積し、橘山、箱田山、十二山などを形成しました。
橘山はこのようにしてできた流れ山地形の一つです。赤城山の子供とも言えますね。
シロダモ 雄株

シロダモは宮城・山形以南に分布する常緑の中高木。クスノキ科シロダモ属。葉の裏側が白く見えます。
シロダモ 雌株

秋に花が咲き、翌年の秋に熟します。
アラカシ

橘山西斜面にはアラカシ林があり、この地域の原植生とされる貴重な群落です。
どんぐり クヌギ(上)とコナラ(下)

クヌギとコナラはどちらもシイタケ栽培の原木になります。
ところで、シイタケ栽培に革命的進歩をもたらした純粋培養菌種駒法を発明し、“きのこの慈父”とも呼ばれる森喜作氏(ドクターモリ)は群馬県桐生市出身。
詳しくは→森産業HP
ヒノキ

ヒノキの葉の裏をよく見ると Y Y Y Y Y Y Y・・・・・・・・・・・・・
白いYがたくさん見えます。
トキリマメ

別名オオバタンキリマメ
赤いサヤが割れると中から黒い豆が顔を出します。

ヒヨドリジョウゴの実

ヒヨドリジョウゴはナス科の多年生ツル植物。
実は赤くて美味しそうに見えますが、口に入れてはいけません。ソラニンを含んでいるの中毒を起こす危険があります。
コカマキリ

鎌の内側に目立つ模様があるのが特徴です。
オオカマキリの卵鞘

卵鞘のなかに卵が200~300個入っています。
カマキリの卵鞘は種類によって形や大きさが異なります。
橘山の南斜面には、昨年11月、地元の方々により100本の山桜の苗木が植えられました。
将来、橘山は桜の名所になることでしょう。楽しみです(^^)