セザール・フランクの室内楽作品全集を買いました。

演奏はマリブラン四重奏団、デイヴィッド・ライヴリー(P)、他
フランクはハイドン先生と並んで最も好きな作曲家です。
全集といってもCD4枚組で、ほとんどは既に持っている曲なのですが、
私がフランクを聴き始めた学生時代(20年以上前)はヴァイオリン・ソナタ以外では
ピアノ五重奏曲、弦楽四重奏曲が1、2種類あるかどうか・・・といった程度だったので、
全集発売には感慨深いものがあります。
そんなフランク初心者時代に見つけて"衝撃"を受けたのが「ピアノ三重奏曲嬰へ短調」です。
フランクが20歳くらいの時の作品で「作品番号1」と付けられています。
(3曲セットで「3つの協奏的ピアノ三重奏曲」(作品1-1~1-3)などと呼ばれます)
作品自体の出来はとても"名曲"と呼べるようなものではありませんし、
ベートーヴェンやロマン派の作曲家(ブラームス、ドヴォルザーク他)の有名曲と
同様のものを期待して聴くとガッカリするでしょう。
ピアノの単調な音型で始まり、続くチェロ、ヴァイオリンの旋律にも魅力はありません。
その後、ピアノやヴァイオリンの音型が変化したり楽器が移ったりしていきますが、
それも変奏曲と呼べるほどではありません。
私自身フランクが好きでなかったら、第1楽章冒頭で聴くのをやめたかもしれません。
フランクはいわゆる"大器晩成型"の作曲家とされ、
オルガン曲以外の主要曲はだいたい60歳前後から書かれていますが、
それらを"傑作"たらしめている特徴が「循環形式」です。
「循環形式」とは、
多楽章曲中の2つ以上の楽章で、共通の主題、旋律、或いはその他の主題的要素を
登場させることにより楽曲全体の統一を図る手法(物識り"ウィキ"さんより)
というものです。
そして、作品番号1と付されたこの「ピアノ三重奏曲嬰へ短調」にも
まさにこの「循環形式」が採用されています。
晩年の特徴だとばかり思っていたので、これにはビックリしました。
のちの読んだ、吉田秀和の「主題と変奏」という評論集に、
「セザール・フランクの勝利」と題された章がありました。
フランクについて書かれた評論があったのがとても意外でしたが、
その中で氏はこの「ピアノ三重奏曲嬰へ短調」について次のように書いています。
・・・彼の処女作である作品一の三曲のピアノとヴァイオリンとチェロのためのトリオ、
ことにその第一番嬰へ短調トリオは立派な作品である。
といっても、それは、作曲家たるべき以上、誰もが習得していなければならぬ基本的なものを、
この十九歳の音楽院の学生が、すでに立派に身につけていた、という意味で立派なのである。
(中略)
フランクのこの作品は、全然ありふれた語彙しかもっていない点で、まず僕らを驚かす。
(中略)
ただ曲の構成には非常な特徴があって、三楽章からなるこの曲の、
最初の楽章に使用された材料が後の二楽章を通じて重要な働きをするようにできている。
これは循環形式と呼ばれ、前例もなくはないが、
フランクの後年の傑作を一貫する独創の最大のメルクマールになっている。
ベートーヴェンやショスタコーヴィチが、
「作品1において、すでにベートーヴェン(ショスタコーヴィチ)だった」
と言われるのと同様に(もしくはそれ以上に?)
フランクも「作品1において、すでにフランクだった」のです。
このことを知ったとき(初めて嬰へ短調トリオを聴いたとき)の驚きと興奮は、
作品の出来不出来などを吹き飛ばすものでした。
当時聴いたCDはミュンヘン・ピアノトリオの演奏です。

循環形式に限らず、前楽章で出てきた素材(旋律)が別の楽章で再現される場合、
(楽譜の指定もあるでしょうが)"オリジナル"と同じテンポで再現されるのが好きです。
妙にテンポを遅くしてみたりニュアンスを変えたりすると、"再現"の意味が失われます。
ミュンヘン・ピアノトリオはその点、奇を衒わず素直な(且つしっかりとした)演奏です。
でもそれは、フランクの作品の魅力を引き出すための基本だと思います。
この演奏で聴いたからこそ、この曲の魅力を理解できたのかもしれません。
今なお愛聴盤です。

演奏はマリブラン四重奏団、デイヴィッド・ライヴリー(P)、他
フランクはハイドン先生と並んで最も好きな作曲家です。
全集といってもCD4枚組で、ほとんどは既に持っている曲なのですが、
私がフランクを聴き始めた学生時代(20年以上前)はヴァイオリン・ソナタ以外では
ピアノ五重奏曲、弦楽四重奏曲が1、2種類あるかどうか・・・といった程度だったので、
全集発売には感慨深いものがあります。
そんなフランク初心者時代に見つけて"衝撃"を受けたのが「ピアノ三重奏曲嬰へ短調」です。
フランクが20歳くらいの時の作品で「作品番号1」と付けられています。
(3曲セットで「3つの協奏的ピアノ三重奏曲」(作品1-1~1-3)などと呼ばれます)
作品自体の出来はとても"名曲"と呼べるようなものではありませんし、
ベートーヴェンやロマン派の作曲家(ブラームス、ドヴォルザーク他)の有名曲と
同様のものを期待して聴くとガッカリするでしょう。
ピアノの単調な音型で始まり、続くチェロ、ヴァイオリンの旋律にも魅力はありません。
その後、ピアノやヴァイオリンの音型が変化したり楽器が移ったりしていきますが、
それも変奏曲と呼べるほどではありません。
私自身フランクが好きでなかったら、第1楽章冒頭で聴くのをやめたかもしれません。
フランクはいわゆる"大器晩成型"の作曲家とされ、
オルガン曲以外の主要曲はだいたい60歳前後から書かれていますが、
それらを"傑作"たらしめている特徴が「循環形式」です。
「循環形式」とは、
多楽章曲中の2つ以上の楽章で、共通の主題、旋律、或いはその他の主題的要素を
登場させることにより楽曲全体の統一を図る手法(物識り"ウィキ"さんより)
というものです。
そして、作品番号1と付されたこの「ピアノ三重奏曲嬰へ短調」にも
まさにこの「循環形式」が採用されています。
晩年の特徴だとばかり思っていたので、これにはビックリしました。
のちの読んだ、吉田秀和の「主題と変奏」という評論集に、
「セザール・フランクの勝利」と題された章がありました。
フランクについて書かれた評論があったのがとても意外でしたが、
その中で氏はこの「ピアノ三重奏曲嬰へ短調」について次のように書いています。
・・・彼の処女作である作品一の三曲のピアノとヴァイオリンとチェロのためのトリオ、
ことにその第一番嬰へ短調トリオは立派な作品である。
といっても、それは、作曲家たるべき以上、誰もが習得していなければならぬ基本的なものを、
この十九歳の音楽院の学生が、すでに立派に身につけていた、という意味で立派なのである。
(中略)
フランクのこの作品は、全然ありふれた語彙しかもっていない点で、まず僕らを驚かす。
(中略)
ただ曲の構成には非常な特徴があって、三楽章からなるこの曲の、
最初の楽章に使用された材料が後の二楽章を通じて重要な働きをするようにできている。
これは循環形式と呼ばれ、前例もなくはないが、
フランクの後年の傑作を一貫する独創の最大のメルクマールになっている。
ベートーヴェンやショスタコーヴィチが、
「作品1において、すでにベートーヴェン(ショスタコーヴィチ)だった」
と言われるのと同様に(もしくはそれ以上に?)
フランクも「作品1において、すでにフランクだった」のです。
このことを知ったとき(初めて嬰へ短調トリオを聴いたとき)の驚きと興奮は、
作品の出来不出来などを吹き飛ばすものでした。
当時聴いたCDはミュンヘン・ピアノトリオの演奏です。

循環形式に限らず、前楽章で出てきた素材(旋律)が別の楽章で再現される場合、
(楽譜の指定もあるでしょうが)"オリジナル"と同じテンポで再現されるのが好きです。
妙にテンポを遅くしてみたりニュアンスを変えたりすると、"再現"の意味が失われます。
ミュンヘン・ピアノトリオはその点、奇を衒わず素直な(且つしっかりとした)演奏です。
でもそれは、フランクの作品の魅力を引き出すための基本だと思います。
この演奏で聴いたからこそ、この曲の魅力を理解できたのかもしれません。
今なお愛聴盤です。










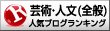

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます