Sさんのトイレ帰りを待つこと10分、いよいよ入館。こういうところはたいがいJAFの優待割引が効くので確認すると案の定10%引いてくれた。博物館のロビーが全面ガラス張りで陽の光が降り注ぎ、たいへん心地よい気分で拝観をスタートした。実はここでもSさんの念の効果が発揮されるのだった。
大社境内を横から抜けて博物館へ向かう。

まずは出雲大社境内遺跡で出土したスギの大木。

発掘時の状況。(歴博のサイトから拝借しました)

以下、歴博のサイトより引用です。
平成12年から13年にかけて、出雲大社境内遺跡からスギの大木3本を1組にし、直径が約3mにもなる巨大な柱が3カ所で発見されました。これは、そのうちの棟をささえる柱すなわち棟持柱(むなもちばしら)で、古くから宇豆柱(うづばしら)と呼ばれてきたものです。境内地下を流れる豊富な地下水のおかげで奇跡的に当時の姿をとどめて出土しました。
直径が最大で約6mもある柱穴には、人の頭の大きさかそれ以上の大きな石がぎっしりと積み込まれ、世界に例のない掘立柱の地下構造も明らかになりました。柱の配置や構造は、出雲大社宮司の千家国造家(こくそうけ)に伝わる、いにしえの巨大な本殿の設計図とされる「金輪御造営差図」(かなわのごぞうえいさしず)に描かれたものと類似していました。
その後、柱材の科学分析調査や、考古資料・絵画、文献記録などの調査などから、この柱は、鎌倉時代前半の宝治2年(1248年)に造営された本殿を支えていた柱である可能性が極めて高くなりました。
古事記・日本書紀・出雲国風土記の三点セット。
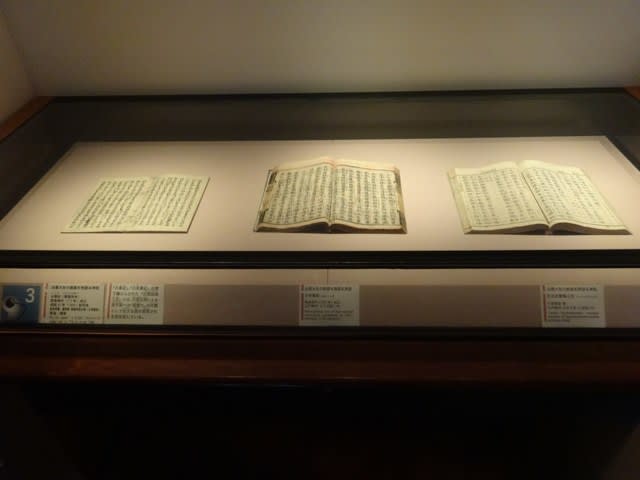
このあと、出雲大社にまつわるビデオをみて大社本殿の復元模型を見ているとき、Sさんが女性の職員から何やら注意を受けている。どうやら館内飲食禁止であるにも関わらずのど飴を舐めていることを咎められたらしい。飴くらい問題ないだろうとSさんはおばちゃん職員に少々不快な気分にさせられたようだ。
荒神谷遺跡の銅剣358本。

圧倒的な迫力を感じる。剣の持つ威力か。
加茂岩倉遺跡の39個の銅鐸。

こちらは「美」を感じる。
銅剣を1本1本つぶさに見て「×」の刻印を確認。よく観察しないとわからないくらい小さな刻印だった。この刻印は358本のうち344本の茎(なかご)に刻まれており、同じ印が加茂岩倉の銅鐸にも見られる。このことから両遺跡の関連性、すなわちこれらの青銅器を埋納した集団の関連性が推測される。
この銅鐸を見ているときに突然女性がすり寄ってきて私に話しかけてきた。「この横になっている銅鐸、修理された痕があるんです」と。「いきなり何やねん、失礼やな」と思ったものの、横になった銅鐸の修理痕を探す自分がいた。よーく見るとたしかにあった。手前の上の面のあたりに色が少し薄くなっている部分がある。その女性はさらに続ける。「普通なら紋様の線は少し盛り上がったようになるのに、その部分だけは何かで刻んだようにへこんだ線になっているでしょ」「たしかに」「鋳型に流し込むときにこの部分だけ銅がまわらずに穴が開いたようになってしまったので、あとで修復して線を刻んだのです」「はあー、なるほど!」
この女性、ただ者ではないな。そのあとも我々の横について鏡や剣の説明もしてくれた。ここの職員だったのだ。しかし、よく見るとあなた、さっきSさんに飴を注意していた人ではないか。もしや、出雲大社のコーナーからずっと後をつけてきたのか? Sさんの念のすさまじさを感じずにはおれなかった。
銅剣と銅鐸、両方まとめて。

これが神原神社古墳から出た三角縁神獣鏡。

たしかに「景初三年」の文字が見える。
これだけ本物を並べられるとぐうの音も出ない。しかも出土した出雲の地で見れることに意味を感じた。2日間で見て回った遺跡や神社とあわせて出雲には大きな勢力が実在したんだと実感できたからだ。東京上野にある東京国立博物館でも国宝の数々の実物を見ることができるが、なんだかアートを鑑賞しているような感覚になってしまうのが残念だ。もちろん、各地の貴重な遺物をまとめて見れることのメリットはあるのだが。
さて、これで3日間にわたる丹後王国、出雲王国を巡る実地踏査ツアーは終了だ。このあとは神門通りでお土産を買って、最後に稲佐の浜で夕陽を拝んで帰ろう。
大社境内を横から抜けて博物館へ向かう。

まずは出雲大社境内遺跡で出土したスギの大木。

発掘時の状況。(歴博のサイトから拝借しました)

以下、歴博のサイトより引用です。
平成12年から13年にかけて、出雲大社境内遺跡からスギの大木3本を1組にし、直径が約3mにもなる巨大な柱が3カ所で発見されました。これは、そのうちの棟をささえる柱すなわち棟持柱(むなもちばしら)で、古くから宇豆柱(うづばしら)と呼ばれてきたものです。境内地下を流れる豊富な地下水のおかげで奇跡的に当時の姿をとどめて出土しました。
直径が最大で約6mもある柱穴には、人の頭の大きさかそれ以上の大きな石がぎっしりと積み込まれ、世界に例のない掘立柱の地下構造も明らかになりました。柱の配置や構造は、出雲大社宮司の千家国造家(こくそうけ)に伝わる、いにしえの巨大な本殿の設計図とされる「金輪御造営差図」(かなわのごぞうえいさしず)に描かれたものと類似していました。
その後、柱材の科学分析調査や、考古資料・絵画、文献記録などの調査などから、この柱は、鎌倉時代前半の宝治2年(1248年)に造営された本殿を支えていた柱である可能性が極めて高くなりました。
古事記・日本書紀・出雲国風土記の三点セット。
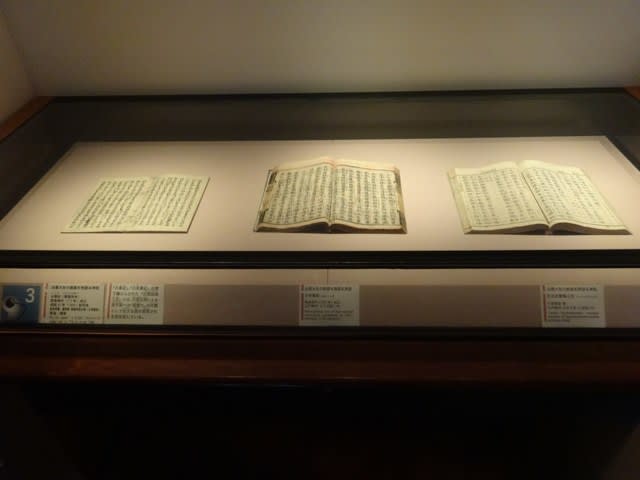
このあと、出雲大社にまつわるビデオをみて大社本殿の復元模型を見ているとき、Sさんが女性の職員から何やら注意を受けている。どうやら館内飲食禁止であるにも関わらずのど飴を舐めていることを咎められたらしい。飴くらい問題ないだろうとSさんはおばちゃん職員に少々不快な気分にさせられたようだ。
荒神谷遺跡の銅剣358本。

圧倒的な迫力を感じる。剣の持つ威力か。
加茂岩倉遺跡の39個の銅鐸。

こちらは「美」を感じる。
銅剣を1本1本つぶさに見て「×」の刻印を確認。よく観察しないとわからないくらい小さな刻印だった。この刻印は358本のうち344本の茎(なかご)に刻まれており、同じ印が加茂岩倉の銅鐸にも見られる。このことから両遺跡の関連性、すなわちこれらの青銅器を埋納した集団の関連性が推測される。
この銅鐸を見ているときに突然女性がすり寄ってきて私に話しかけてきた。「この横になっている銅鐸、修理された痕があるんです」と。「いきなり何やねん、失礼やな」と思ったものの、横になった銅鐸の修理痕を探す自分がいた。よーく見るとたしかにあった。手前の上の面のあたりに色が少し薄くなっている部分がある。その女性はさらに続ける。「普通なら紋様の線は少し盛り上がったようになるのに、その部分だけは何かで刻んだようにへこんだ線になっているでしょ」「たしかに」「鋳型に流し込むときにこの部分だけ銅がまわらずに穴が開いたようになってしまったので、あとで修復して線を刻んだのです」「はあー、なるほど!」
この女性、ただ者ではないな。そのあとも我々の横について鏡や剣の説明もしてくれた。ここの職員だったのだ。しかし、よく見るとあなた、さっきSさんに飴を注意していた人ではないか。もしや、出雲大社のコーナーからずっと後をつけてきたのか? Sさんの念のすさまじさを感じずにはおれなかった。
銅剣と銅鐸、両方まとめて。

これが神原神社古墳から出た三角縁神獣鏡。

たしかに「景初三年」の文字が見える。
これだけ本物を並べられるとぐうの音も出ない。しかも出土した出雲の地で見れることに意味を感じた。2日間で見て回った遺跡や神社とあわせて出雲には大きな勢力が実在したんだと実感できたからだ。東京上野にある東京国立博物館でも国宝の数々の実物を見ることができるが、なんだかアートを鑑賞しているような感覚になってしまうのが残念だ。もちろん、各地の貴重な遺物をまとめて見れることのメリットはあるのだが。
さて、これで3日間にわたる丹後王国、出雲王国を巡る実地踏査ツアーは終了だ。このあとは神門通りでお土産を買って、最後に稲佐の浜で夕陽を拝んで帰ろう。






















