それでは昨日の続きで、A=1.0mm(全画面均一ピント位置)で実写です。
M1 , ISO800_2X60s + ISO400_2X60s = 240sec Total

M81,M82 , ISO1600_4X60 = 240sec Total

確かに周辺まで点像に近くなってはいますが、
光量ムラがありすぎて画像処理が大変です。ここまで到達するのにも
時間がかかっています。労多くして実り少なし・・・本末転倒ですね。
処理をやっていても、画像自体がこんなレベルですから気合も入りません。
縮小コリメート撮影で画像処理負荷が重いなんてナンセンスです。
コンポジットもせいぜい4枚まで。出来れば1カット完結としたいですね。
ましてフラット画像まで撮る気力は湧いて来ません。
この辺りは個人差があると思われますが、私はやはりこっちの方が好きです。
↓
M106 , ISO1600_4X60 = 240sec Total ( A=3.8mm 全画面均一光量位置)

これは殆ど画像処理らしきことをやっていませんし、シェーディング補正も無しです。
何よりも撮影現場で均一フラットな画像がポンポン撮れるので精神衛生上も良いです。
ハンドリングの良さも最高で、縮小コリメート撮影法ここに極まれり!
って感じです。
全画面点像位置の場合、合成F1.4の光学系の難しさが顕著に現れます。
少しでもカメラが傾いていれば星像が伸びますし、中央集光スポットが右へ左へ
動き回って精神衛生上宜しくありません。”スケアリング”なんて単語が
頭をよぎります。ちっともお気楽ではありませんでした。
こんな撮影は、もうやらないでしょうね。
もうやらないだろうから、記念にM82をズームして気合撮り(爆)。
M82 , 11.8mmF2.0 , 合成F=3.33 , 合成焦点距離666mm , ISO1600_4X125s = 500sec Total

ぴんたんさんのFlatAideを使わせて頂きました。
元画像はコレ↓ですから・・・

まあ、これはコレで凄いっちゃースゴイ。
LX7で合成焦点距離666mmと言うことは、35mm換算で4.55倍で3030mmと言うことです。
焦点距離3030mmF3.33相当の光学系を90s赤道儀でノータッチトラッキングですよ。
でも、たぶん、もうやりません。
ここ数日で思ったことは、やはり空が暗い所へ出掛けて行って☆を見たい!
と言うことです。M106を20cmで見ると結構大きいのでビックリしますが、
悲しいかな、この夜空では感動ってもんがありません。
いつもは冷却CCDで気合撮り遠征ばかりですが、これは☆を楽しんでいると
言うより、機材やデータの仕上がり具合を楽しんでいる感じですね。
だから、
縮小コリメート撮影法やPanasonic DMC-LX7と言ったお気楽ツールが魅力的に
思えた訳です。LX7は、ハッキリ言って☆がスゲー写るコンデジです。
手の平に載ります。アイピースにチョン付け出来ます。
赤いのも結構写ります。250秒も露光でき、ダークも勝手に減算してくれます。
でも、
ここまでの道のりは長かったなあ~!
そろそろまとめましょうかね、縮小コリメート撮影法。
<共通データ>
撮影日時:2014/04/01~02 , 21:18:16~01:59:32
撮影場所:飯能市郊外の林道
シーイング:5/5
鏡筒:VC200L
アイピース:PHOTON32mm + LPS-P2
カメラ:Panasonic DMC-LX7 , 4.7mmF1.4開放端で使用
赤道儀:90sノータッチ・トラッキング
M1 , ISO800_2X60s + ISO400_2X60s = 240sec Total

M81,M82 , ISO1600_4X60 = 240sec Total

確かに周辺まで点像に近くなってはいますが、
光量ムラがありすぎて画像処理が大変です。ここまで到達するのにも
時間がかかっています。労多くして実り少なし・・・本末転倒ですね。
処理をやっていても、画像自体がこんなレベルですから気合も入りません。
縮小コリメート撮影で画像処理負荷が重いなんてナンセンスです。
コンポジットもせいぜい4枚まで。出来れば1カット完結としたいですね。
ましてフラット画像まで撮る気力は湧いて来ません。
この辺りは個人差があると思われますが、私はやはりこっちの方が好きです。
↓
M106 , ISO1600_4X60 = 240sec Total ( A=3.8mm 全画面均一光量位置)

これは殆ど画像処理らしきことをやっていませんし、シェーディング補正も無しです。
何よりも撮影現場で均一フラットな画像がポンポン撮れるので精神衛生上も良いです。
ハンドリングの良さも最高で、縮小コリメート撮影法ここに極まれり!
って感じです。
全画面点像位置の場合、合成F1.4の光学系の難しさが顕著に現れます。
少しでもカメラが傾いていれば星像が伸びますし、中央集光スポットが右へ左へ
動き回って精神衛生上宜しくありません。”スケアリング”なんて単語が
頭をよぎります。ちっともお気楽ではありませんでした。
こんな撮影は、もうやらないでしょうね。
もうやらないだろうから、記念にM82をズームして気合撮り(爆)。
M82 , 11.8mmF2.0 , 合成F=3.33 , 合成焦点距離666mm , ISO1600_4X125s = 500sec Total

ぴんたんさんのFlatAideを使わせて頂きました。
元画像はコレ↓ですから・・・

まあ、これはコレで凄いっちゃースゴイ。
LX7で合成焦点距離666mmと言うことは、35mm換算で4.55倍で3030mmと言うことです。
焦点距離3030mmF3.33相当の光学系を90s赤道儀でノータッチトラッキングですよ。
でも、たぶん、もうやりません。
ここ数日で思ったことは、やはり空が暗い所へ出掛けて行って☆を見たい!
と言うことです。M106を20cmで見ると結構大きいのでビックリしますが、
悲しいかな、この夜空では感動ってもんがありません。
いつもは冷却CCDで気合撮り遠征ばかりですが、これは☆を楽しんでいると
言うより、機材やデータの仕上がり具合を楽しんでいる感じですね。
だから、
縮小コリメート撮影法やPanasonic DMC-LX7と言ったお気楽ツールが魅力的に
思えた訳です。LX7は、ハッキリ言って☆がスゲー写るコンデジです。
手の平に載ります。アイピースにチョン付け出来ます。
赤いのも結構写ります。250秒も露光でき、ダークも勝手に減算してくれます。
でも、
ここまでの道のりは長かったなあ~!
そろそろまとめましょうかね、縮小コリメート撮影法。
<共通データ>
撮影日時:2014/04/01~02 , 21:18:16~01:59:32
撮影場所:飯能市郊外の林道
シーイング:5/5
鏡筒:VC200L
アイピース:PHOTON32mm + LPS-P2
カメラ:Panasonic DMC-LX7 , 4.7mmF1.4開放端で使用
赤道儀:90sノータッチ・トラッキング













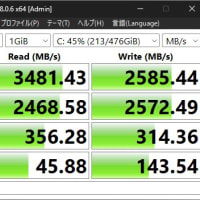
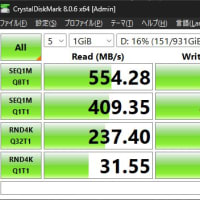












しかし晴れないですねー。早く天気が回復してほしいものです。
そうです。縮小コリメート法の特徴は”お手軽さ”です。
しかしながら、良くよく考えてみれば手強いものです。
それは、
・合成F=1.4などの超絶明るい光学系のため、光軸に敏感。
・各社コンデジの”クセ”は使ってみなければ解らない。
・望遠鏡光学系とアイピースの特性が系統だってまとめられていない。
縮小コリメート法の場合、これにコンデジのレンズ特性が加わるため、
デジイチ直焦点撮影のような予測がつかない。
・縮小コリメート撮影専用のアダプターが存在しない。
専用は作れたとしても、コンデジが変わってしまうと使えなくなる。
できれば汎用で使い回しのできるモノが欲しい。
といった難しさがあります。
ケンタウルス座A共々低空の天体を見事に捕らえましたね!
長時間露光で撮っていると直ぐにいなくなってしまうので、1カット1分×4
で撮れるのは縮小コリメート法の威力ですね。
私は最近、無理に広写野点像を目指さなくても良いかな?
と思い始めています。C-8ならば視野50°のアイピースが最適だと言うことも
解りました。VC200Lは広写野でも結構イケますが、解像度はC-8の方があるように
思います。
ドブとLX7で縮小コリを狙いましたが、良いアイピースなく探しています。
今のところ笠井の2インチSV30を候補にしてますが、使ってみないと何とも分からず
分からないものに無闇に投資するリスクを減らせないか?と考えています。
何かアドバイスいただけば幸いです。
30年ぶりの天文少年を復活中の 猫の飼い主(男)です。
ようこそお越し下さいました! 宜しくお願い致します。m(__)m
我が家も猫だらけでして、現在3匹飼っています。
常に3~4匹おります。毎朝4時に起こされます。
さて、縮小コリメート法で笠井のSV30mmはお勧めできません。(周辺像がイカンです)
SV32mmであれば結構使えます。私は2本とも購入して使いました。
この辺りの情報は当ブログの記事カテゴリーを”縮小コリメート法”で絞り、
その1からお読みになるとイロイロ実験記事が書いてありますよ。
沢山の記事がありますが、同じ轍を踏まぬようご一読下されば幸いです。
短焦点のドブであれば、PENTAXのXW20mmが一番良いと思います。
アストロアーツのギャラリーにも投稿されています。
”縮小コリメート法”で検索してみて下さい。
私の友人がXW20mmと25cmF5.6ニュートンで素晴らしい成果を出されています。
少し工夫をすればLX7で使えるようになります。
今後何かと問題にぶつかるでしょうから、私の分かる範囲であれば
何でもお手伝いできます。
頑張って下さい!
素晴らしい!網状星雲・M33
ここまで取れれば凄いですね。
ところで一昨日入笠山に初めて行ってきたばかりでした。
笠井SV32ならSV30より安くて良いですね。
LX7との接続は笠井でM42T2/M37用意されてるみたいですが
ペンタXW20 と LX7フィルタ37 の接続は どうされてますか?
PENTAX XW20mmとLX7を接続して主点調節を行うには下記のようにします。
この方法は友人H氏が実際に作ってアストロアーツに投稿している
やり方です。
XW20mmは見口のカバーがネジでスライドします。
ここに47mmのネジが切ってあるので、外装のラバーを取っ払って、
八仙堂で出している47-49mmのステップアップリングねじ込み、
そこに52-58mmのステップアップリングをエポキシで逆づけ接着。
これで52mmのLA-52LX7が取り付けられます。可動範囲は12mmです。
|
+->当ブログ、縮小コリメート法(その19)をご参照ください。
http://sky.ap.teacup.com/eti_forest/367.html
ピント合わせは4倍または6倍の小望遠鏡をつけますが、
これも取り付け部は52mmですのでOK。
眼視では富士フィルムから出ている視度補正レンズ
DPC-1を取り付けます。これまた52mmにしてあります。
望遠鏡を小望遠鏡で∞に合わせ、カメラのピントも出して
おけば、あとはこの補正レンズをつけて観望を楽しみ、
気が向いたらカメラと取り替えて撮影します。
その1から41?まで通読させていただきました。
頭が下がる思いです。
ついでに質問でーす
XW20 より XW14 の方が拡大率上がりますね
XW20より XW30の方が 視野が広くなりそうですが
XW14または30について 何か情報をお持ちでないでしょうか?
駄文ご拝読有り難うございます。
XW30は生産中止で入手困難だと思います。
買えなかったので適性は不明です。
XW14mmでは縮小率が小さいために私のC-8
では試していません。
LX7のF1.4を活かしてこそだと思っています。