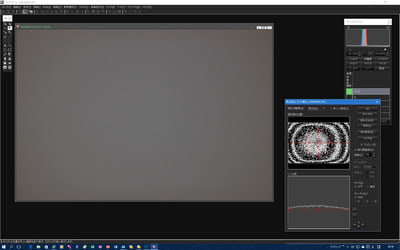K-1のRAW現像は純正のPDCU5、CameraRAW、SI7の三種類を使える
環境にありますが、多くはSI7で行っています。
と言っても、SI7がK-1のRAWに対応したのが最近ですから、
実際にはこれからRAWで処理して行こうという段階です。
今回はPDCU5(Ver,5.6.1)、CameraRAW(Ver,9.6.1)を使ってFlat画像を
現像してみました。
PDCU5・・・使いにくいですねえ((+_+)) しかも、何故にこんなに遅い?
PC環境:Core i7_2600K , 16GB Memory , 256GB_SSD(C_drive)
撮像環境:ZWO-CN15F4 + MPCCⅢ + LPS-P2 + K-1
Flat条件:部屋中でコピー用紙を筒先に張り、白タオル3枚掛け、
カメラアイキャップ、鏡筒全体を布にて遮光
白い壁に向けて撮像。
画像はニュートラルグレーに調整。
ISO:800 , 1600 , 3200 各30秒
尚、PEFをPDCU5で現像、DNGをCameraRAWで現像しています。
<PEF>
ISO 800 , 30sec

ISO 1600 , 30sec

ISO 3200 , 30sec

<DNG>
ISO 800 , 30sec

ISO 1600 , 30sec

ISO 3200 , 30sec

やはり普通のRAW現像環境としてはCameraRAWが秀逸で使いやすいです。
PDCU5はこんなに遅かったかなあ?と思うくらい引っ掛かります。
思考が中断されてしまう。
しかも、ニュートラルグレーにしたいがヒストグラム三色同時出しは
出来ないのか? 調べる気も起きない・・・
天文用はSI7一択ですが、一般用はやはりCameraRAWを使いたい。
RRSの時だけPDCU5ですかね。(-。-)y-゜゜゜
追記 2016/09/09
あまぶんさんからISO800_600secのダーク画像で緑色帯が出ないか検証
して欲しいとのご要望を頂きましたのでやってみました。
ダーク画像は今朝方奥秩父で撮影したダーク1枚画で、気温17℃です。
特に何も出ませんでした。
以前のダーク画像もイロイロ確認しましたが、特に妙な帯は出ていません。
ただPDCU5のノイズ処理を掛けると、処理がゆっくりと(-。-)y-゜゜゜
進行するため、場合によっては下記のような”それらしい”状態には
なります。PCかPDCU5に問題があって処理が途中で終わってしまうなどが
起これば、あるいは緑帯が残ってしまうこともあるかもしれませんね。

環境にありますが、多くはSI7で行っています。
と言っても、SI7がK-1のRAWに対応したのが最近ですから、
実際にはこれからRAWで処理して行こうという段階です。
今回はPDCU5(Ver,5.6.1)、CameraRAW(Ver,9.6.1)を使ってFlat画像を
現像してみました。
PDCU5・・・使いにくいですねえ((+_+)) しかも、何故にこんなに遅い?
PC環境:Core i7_2600K , 16GB Memory , 256GB_SSD(C_drive)
撮像環境:ZWO-CN15F4 + MPCCⅢ + LPS-P2 + K-1
Flat条件:部屋中でコピー用紙を筒先に張り、白タオル3枚掛け、
カメラアイキャップ、鏡筒全体を布にて遮光
白い壁に向けて撮像。
画像はニュートラルグレーに調整。
ISO:800 , 1600 , 3200 各30秒
尚、PEFをPDCU5で現像、DNGをCameraRAWで現像しています。
<PEF>
ISO 800 , 30sec

ISO 1600 , 30sec

ISO 3200 , 30sec

<DNG>
ISO 800 , 30sec

ISO 1600 , 30sec

ISO 3200 , 30sec

やはり普通のRAW現像環境としてはCameraRAWが秀逸で使いやすいです。
PDCU5はこんなに遅かったかなあ?と思うくらい引っ掛かります。
思考が中断されてしまう。
しかも、ニュートラルグレーにしたいがヒストグラム三色同時出しは
出来ないのか? 調べる気も起きない・・・
天文用はSI7一択ですが、一般用はやはりCameraRAWを使いたい。
RRSの時だけPDCU5ですかね。(-。-)y-゜゜゜
追記 2016/09/09
あまぶんさんからISO800_600secのダーク画像で緑色帯が出ないか検証
して欲しいとのご要望を頂きましたのでやってみました。
ダーク画像は今朝方奥秩父で撮影したダーク1枚画で、気温17℃です。
特に何も出ませんでした。
以前のダーク画像もイロイロ確認しましたが、特に妙な帯は出ていません。
ただPDCU5のノイズ処理を掛けると、処理がゆっくりと(-。-)y-゜゜゜
進行するため、場合によっては下記のような”それらしい”状態には
なります。PCかPDCU5に問題があって処理が途中で終わってしまうなどが
起これば、あるいは緑帯が残ってしまうこともあるかもしれませんね。