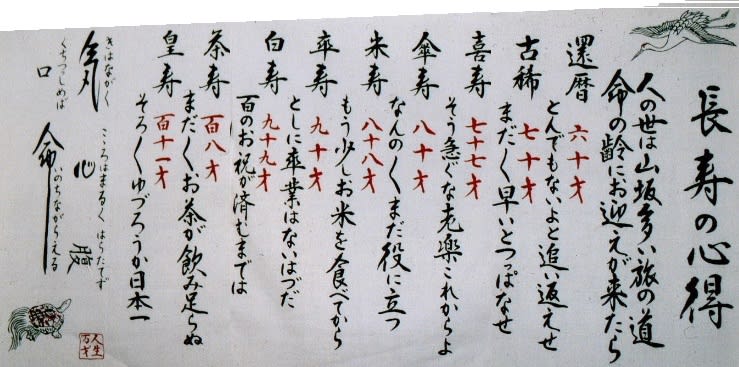
敬老の日が近いので、「長寿の心得」を採り上げてみた。
この心得を奈良の勝手神社で気にいり、その暖簾を両親に贈ったことがある。
いまは、ひろまったらしくこの心得を時々見かける。
古希、喜寿、傘寿から 茶寿までの意味は、コチラ ・・・ 数の物語
数の物語
茶寿108歳の上には、皇寿111歳があり、その根拠は次のとおり。
皇寿・・・「皇」の字を分解すると「白 (=99)、一、十、一」と分解でき、その総てを足すと「99+1+10+1」から111歳。
また、111 が 「川」 と読めるため 川寿 ともいう。
この年齢の上にも、こんな寿な歳がある。
昔寿120歳、「昔」の字を分解すると 「廿 (=20) + 百」=120
縁起の善い歳は、まだあるかしら ("^ω^)・・・。


この心得を奈良の勝手神社で気にいり、その暖簾を両親に贈ったことがある。
いまは、ひろまったらしくこの心得を時々見かける。
古希、喜寿、傘寿から 茶寿までの意味は、コチラ ・・・
 数の物語
数の物語 茶寿108歳の上には、皇寿111歳があり、その根拠は次のとおり。
皇寿・・・「皇」の字を分解すると「白 (=99)、一、十、一」と分解でき、その総てを足すと「99+1+10+1」から111歳。
また、111 が 「川」 と読めるため 川寿 ともいう。
この年齢の上にも、こんな寿な歳がある。
昔寿120歳、「昔」の字を分解すると 「廿 (=20) + 百」=120
縁起の善い歳は、まだあるかしら ("^ω^)・・・。


















喜寿から傘寿、茶寿、米寿、皇寿等々は歳を加工して巧く考えていますね。
昔寿(せきじゅ)というめでたい歳があります。120歳だそうです。
草を薙ぎ払ったのですから、これからは草薙の菜園と名づけるといいですね。
http://blog.goo.ne.jp/iinna/e/e0b1585e6a0297846222fd36a3eec764
>親より若く亡くなると親不孝です。
そのように申しますが、長寿家系は親より長生きするのは大変です。健康に長生きをしてください。
90歳で亡くなると若死にで、
80歳で亡くなると「若い時に良くない事をしたんだ」と言われ
親より若く亡くなると親不孝です。
若いころは、呑み屋を仲間とよく「はしご」してました。
楽母さんは、病院を「はしご」するほど 元気?でした。("^ω^)・・・
そういえば、独身のときに上司が部下の結婚式を「はしご」したことを思い出しました。
いまなら、結婚式と葬式を「はしご」する事態になりかねません。(^_^;)
やはり、梯子酒するくらいが丁度いいです。せいぜい、お店までの足の梯子を外されぬよう気をつけまする。
元の呼び名は、源氏の名刀・髭切(ひげきり)と申しました。
http://blog.goo.ne.jp/iinna/e/46d6e49d16c97d7e552a934f17722456
>西暦1907年-明治40年生れでしたが、103歳で亡くなりましたが 前日まで、駄洒落を言っていました
(wasada49)さんは長寿の家系ですから、長生きできますょ。
噺家
http://blog.goo.ne.jp/iinna/e/db8b65088972e76d2fb74e74a3b36e77
60歳を過ぎた頃から
「石を噛んでも長生きをするから、
入れ歯になってからは、砂を噛んでも」と、口癖のように言っていました
せめて、21世紀をこの目で高めたいから、21世紀になったら100歳になり、
友達、友人がいないので、寂しいと
西暦1907年-明治40年生れでしたが、103歳で亡くなりましたが
前日まで、駄洒落を言っていました・
「長寿の心得」のうち、「気は長く、心は丸く、腹たてず、口つつしめば、命長らえる」の細工した文字を、とくに気に入っています。
ゆっくりご静養ください。
イタチは鳥獣法の対象外で追放だけの「所払い」の処分でした。 ・・・
>「長寿の心得」 ・・・ お迎えが来たら、これを思い出して追い返します。それまで健康でいられるように日々努力します。
「長寿の心得」のうち、「気は長く、心は丸く、腹たてず、口つつしめば、命長らえる」の細工した文字を、とくに気に入っています。
な~るほど と納得しました。
お迎えが来たら、これを思い出して追い返します。
それまで健康でいられるように日々努力します。
>断崖絶壁に荒波が行く手を阻み、波打ち際を進む際に親は子を忘れ、子は親を顧みる暇がなかったことから「親知らず・子知らず」と呼ばれたお話しではなかったですね
普通に親不知と言えば北陸の断崖絶壁のことですよね。
今回は敢えて歯の親知らずを取り上げました。