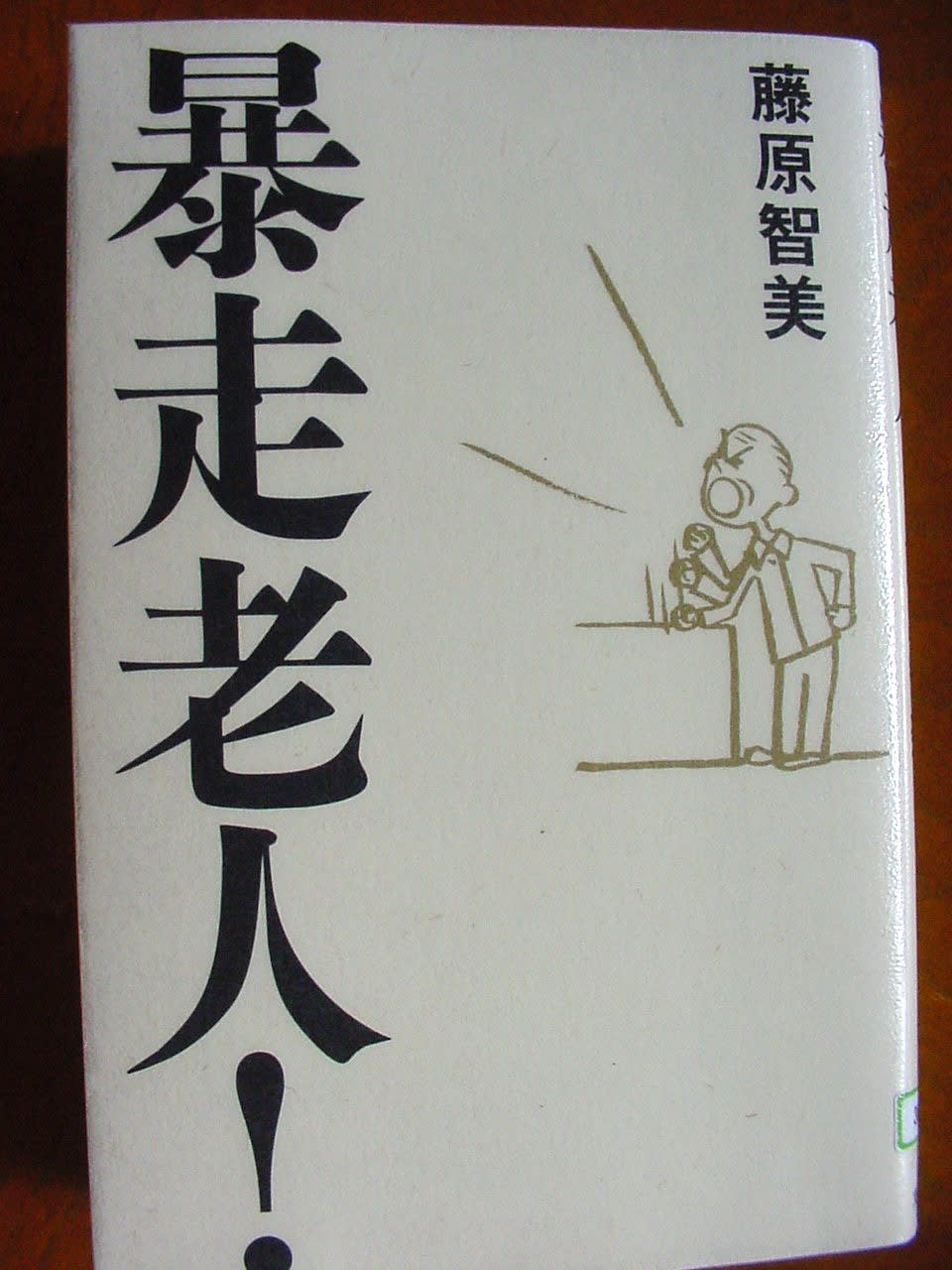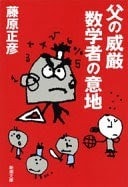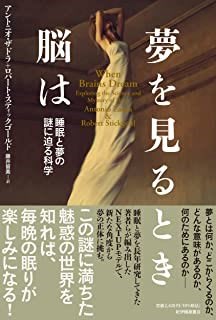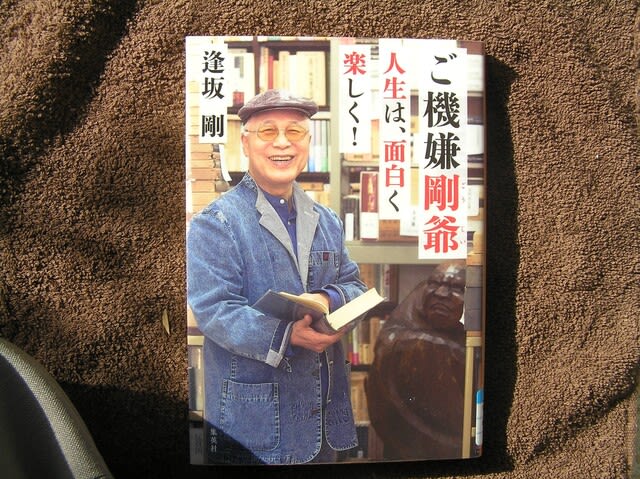ガソリン価格の高騰が止まりません。スマホに某石油会社のアプリをダウンロードして最安値で給油していますが、それでも現在1リットルあたり「185円」です。こうなると対抗策を講じないといけません・・、それには走行距離を減らすしかないです。
筆者のクルマの燃費から計算すると、ランニングコストが1kmあたり「12円」になります。で、図書館まで往復が40kmなので1回行くたびに480円かかっている計算になります、行くのを6回節約すると「ジョニ黒」が購入できる・・、とまあ、年金生活者はみみっちい計算をしていますぞ(笑)。
で、このところ図書館行きは2週に1回のペースにしているので、面白い本に出会う確率も確実に減っています。そういう中で、たまたま出会ったのがこの本です。
とても面白いタイトルなのでつい手に取ってみました。著者は女性で「京都大学大学院課程修了」のインテリさんです。ぶっちゃけると、大学院のゼミで討議した内容がそっくり網羅されているそうです。
誰しも経験があると思いますが、古今の名作とされているものを読んだけど、いまいちピンとこなかった、はてさて自分の読解力が拙かったのか、それとも相性が悪かったのか・・。
なにしろ「名作」なんですから何代にもわたる風雪に耐えてきた歴史と権威を持っていますので、読み手が悪いに決まってます(笑)。
そういうときのアドバイスとして活用するのに向いている本ですね。
168頁に著者の読書論がありましたのでご紹介しましょう。
「私は小説を読むという行為は自分の中の多重人格性を癒す作業だと思う。人間は本来、誰しもさまざまな年齢の、さまざまな立場の自分を心の中に飼っている。だけど与えられた立場や外面によって、その外面に合った自分を外に出さざるをえない。
ほんとうはさまざまな立場の自分が自分を見ているのだけど、さまざまな立場の自分を外に出す機会はたいてい与えられていない。
だけど、小説を読むことで、というか広く言えば物語を読むことで、さまざまな立場の自分を外に出してやって呼吸させてやることができる。
「ライ麦畑で捕まえて」(サリンジャー)のホールデンの台詞を読めば16歳の自分が呼吸する。「門」(漱石)を読めば55歳の自分がふっと起き上がる。「老人と海」(ヘミングウェイ)を読めば男の自分が息を吐く。
いろんな人格が自分の中にいることを確認できる。フィクションの中だと呼吸ができる。だから私たちは自分とまったく異なる人格の物語を読むと何だか癒されるんだと思う。」
といった調子です。
本書では、以下のような名作小説を取り上げ、それぞれに適した読み方のアプローチが紹介されています.。
たとえば・・、
『若草物語』:違和感から読んでいく
『カラマーゾフの兄弟』:あらすじを先に読んでおく
『金閣寺』:タイトルに問いかける
『老人と海』:自然を楽しむ
『吾輩は猫である』:前提を楽しむ
『キャッチャー・イン・ザ・ライ』:多重人格になってみる
ほかにも、有名な小説がいくつも紹介されています。
で、もっと具体的に掘り下げてみましょう。
たとえば、とてつもない長編の「カラマーゾフの兄弟」です。これ正直言ってなかなか難解で、とっつきにくい小説の最たるものですが、本書によると「大まかなあらすじを先に理解しておく」とサクサク読めるそうですよ。
「父親と仲の悪い放蕩息子の長男ミーチャがいて、インテリで合理主義の次男イワン、修道院にいて純粋な美青年の三男アリョーシャがいる。そして、女性問題、遺産問題も絡み、父子の仲がどんどん悪くなるので父親も含めて四人で話合おうとするものの、その やさき に父親が殺されてしまう。しかし犯人は分からない」というのが大筋だそうです。
最後に、著者の「三宅香帆」さんですが、つい先日のテレビ番組「プレバト」に出演されていましたね。ほら「俳句」の優劣を競う人気番組です。高学歴者大会と銘打ってましたが、堂々と優勝されていました! 才媛です。
どうやら「天は二物を与えた」ようですね~(笑)。
水面(みなも)に微かに浮かんでいる二つの赤い影に気が付かれましたか?
クリックをお願いね →