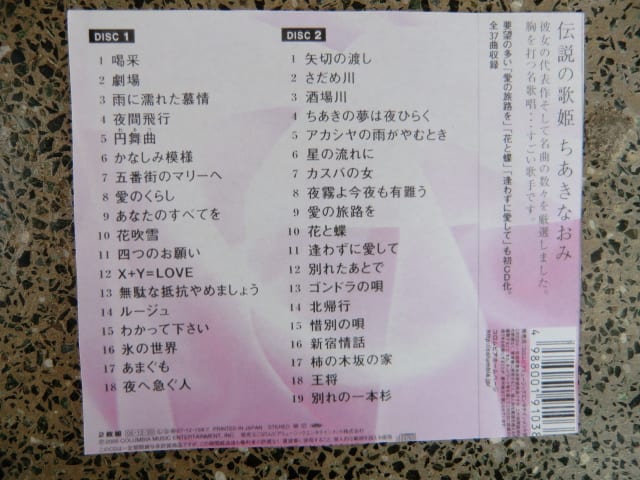亡き母の初七日があけて、ようやくブログ再開です。今後ともよろしく~。
さて、この10日間はすっかり落ち込んでしまって音楽を聴く気にならず、本を読む気にもならず、運動ジムにも行かず、もっぱら静かにテレビ番組の視聴ばかり。
しかし、こういうときでも「音」が気になってしまうのは、オーディオ・マニアの「業」というものだろうか。
以下、顛末を記してみよう。
これまで、テレビを観るときはいつもスピーカーにウェストミンスター(タンノイ)を使っていたが、現在新しいチャンデバを作成中のためネットワークを取り外していて使い物にならないので、やむなく我が家のメインシステムのオーディオ装置に切り替えて聴いている。
このメインシステムを改めて(SPに限って)記しておくと次のとおり。
40ヘルツ以下 スーパーウーファー
40ヘルツ~200ヘルツ ウーファーを3発
200ヘルツ~ アキシオム80を2発
もちろん周波数はおよその目途だが、こうした帯域の広い音楽の再生を目的としたメインシステムでテレビの音声を2~3時間程度ならともかく、それ以上、長時間聴いているとなんだか耳が疲れてしまった。
自分の場合「駄耳」だと自覚しているので、「いい音」か「悪い音」かの瞬時の判断は(極端な場合を除いて)出来かねるが「音」に不自然な響きを感じるときは、不思議とオーディオ装置のスイッチを入れるのが次第に億劫になるのでそれが目安となっている。
今回もその例に洩れない。
周知のとおりテレビ番組の音声はほとんどが人の声で成り立っているが、男声の周波数の範囲は倍音を含めておよそ100ヘルツ~7000ヘルツ程度で、女声の方は150ヘルツ~1万ヘルツ程度とされている。
ということは、テレビ視聴の場合、70ヘルツ~1万ヘルツをしっかり再生してくれれば十分というわけで、これはまったく口径20㎝程度のフルレンジユニットの守備範囲と同一。
つまり20~2万ヘルツの広い帯域を対象にしたメインシステムでテレビを視聴するなんて、まるで「牛刀で鶏肉を裂く」ようなもので”仰々しい”こと、この上なし、テレビの視聴ぐらいなら下手に周波数を分割していないだけフルレンジで鳴らす音の方が有利で自然のはず。
(ただし、我が家のメインシステムにも何らかの問題点があるのはたしかである。)
「よし、(フルレンジを)試してみよう」と思い立った。
6年前に購入したシャープの液晶テレビ(45インチ)には簡単に外部スピーカーの接続ができるようになっている。
手持ちの箱入りのフルレンジユニットといえば、40年ほど前に購入したフォスター(現在はフォステクス)の「BFー103S」(口径10cm)があったはずだがと、倉庫を探してみると隅の方にあったあった。
さっそく3mほどのSPコードを「BF-103S」の端子に半田づけし、テレビ内臓のアンプを利用して音出し。
もちろんボックスの裏蓋を外してその中に吸音材として羽毛(木綿袋に小分けしたもの)を、ぎゅうぎゅう詰めに押し込んだのは言うまでもない。

「おお、なんと素直で自然な音なんだろう」と思わず頬が緩んでしまった。低域も超高域も見事に出ないが中域がしっかりとしたグッドバランス。長時間聴いてもちっとも疲れないのが何よりもいい。また、テレビのリモコンスイッチひとつで画像と音声が出てくれるのも実にありがたい。まさに「シンプル・イズ・ベスト」。
さらに40年の星霜を経ても、ちっとも衰えていないフォスターのユニットの丈夫さには大いに感心した。
実はこの古いユニットにはちょっとばかり思い出がある。
当時といっても40年ほど前のことだが、愛読していたステレオ・サウンド誌(通称「ステサン」、あの頃は良かった!)でオーディオ評論家の長岡鉄男さん(故人)が小さなトリオのアンプ(TW-31)とこの「BF-103S」の組み合わせを提案され、他の評論家たちからも「素直な音」だと大好評だった。
さっそく”なけなし”のお金をはたいてこのセットを購入したのは言うまでもないがアンプの方は壊れてとっくの昔に処分したものの、SPユニットは湿気が入らないようにマメに梱包して保存していたのだが、「捨てなくてよかった!」。
余談だが長岡さんはそれから程なくして、「ステサン」の主柱的存在だった某有名評論家と仲違いしてしまい、「ステサン」の執筆から遠ざけられてしまった。
以後「ステサン」はいたずらに値段ばかり”ぶっ高い”高級品志向に特化してしまい、幅広い読者層に対する多様性が失われてしまったが、コスト・パフォーマンス志向が強かった長岡さんの功罪はいろいろあるにしても往時を知る方のうちこのことを残念に思うのは自分だけだろうか。
オーディオは決して「お金持ちが有利」の趣味になってほしくない、資金という制約があってこそ研究熱心となり「いいアイデア」が湧き、「センス」も磨かれると思うのだがこれは「独断と偏見」かな~。
さて、「テレビの音ならこれで十分」と大いに満足してこのユニットで2~3日聴くうちに、これがもし20cm口径のフルレンジならもっと気持ちよく聴けるかもしれないなどと、だんだん欲が出て来てしまった。
この辺はオーディオ・マニア特有の”貪欲さ”丸出し。
現在、箱無しの裸の状態で20㎝口径のフルレンジユニットを3種類持っている。
アルテックの「403A」が8本、リチャード・アレンの「ニューゴールデン8」が2本、ジェンセンの「P8P」が2本。
アルテックはいずれ片チャンネル4発で鳴らしてやろうとオークションでせっせと集めたもので、リチャード・アレンはブリティッシュ・サウンドに憧れていたときに購入したもの、そしてジェンセンの「P8P」は1954年製造のヴィンテージもので強力なアルニコマグネット付きなので絶対に「いい音」が出るはず。

きちんとした箱さえ作ってやればこれらのユニットをフルに活用できるのは言うまでもない。
よ~し、この際だから一丁やってみっか!
とはいっても名古屋のYさんみたいにとても凝った”つくり”のボックスは技術的にも資金的にも無理なので、バランスが取れて実際に「いい音」を出している「BF-103S」の箱の寸法をそれぞれ測って「黄金比」の1.6倍に拡大して作ってみることにした。
それでも縦55cm、横35cm、奥行き30cmのこじんまりとした箱になる。
スピーカーの箱は大きければ大きいほど豊かな音がするのは分かっているが、内部の平行面で起きる定在波の処理などが難しくなるし、それに置き場所だって困る。
「オーディオは大掛かりで複雑になればなるほど悩みもお金も増えていく」というのは自分の経験上ではやはり真理である。
問題は箱の材質だが近くのホームセンターで視察してみると丁度手頃の厚さ1.8cmの松の集成材があったので、これで作ってみることにしたが、はてさて、うまくいくものやら・・・。
以下、続く。