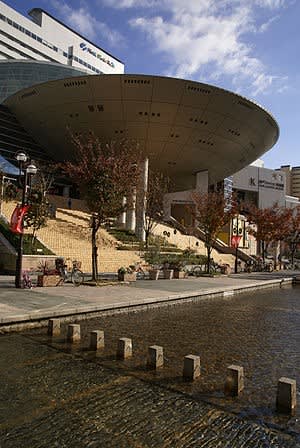「クラシック音楽がすーっとわかるピアノ音楽入門」(山本一太著、講談社刊)に、「ベートーヴェン晩年のピアノ・ソナタ」について次のような記述(95~96頁)があった。

~以下引用~
『ベートーヴェンは、1820年から22年にかけて「第30番作品109」、「第31番作品110」、「第32番作品111」のピアノ・ソナタを書き、これらがこのジャンルの最後の作品となった。
この三曲をお聴きになったことのある人なら、これが現世を突き抜けた新しい境地で鳴り響く音楽だとして理解していただけると思う。
とにかくこういう超越的な音楽の神々しさを適切に美しく語ることは、少なくとも著者には不可能なので、簡単なメモ程度の文章でご容赦ください。 ベートーヴェンの晩年の音楽の特徴として、饒舌よりは簡潔、エネルギーの放射よりは極度の内向性ということが挙げられる。
簡潔さの極致は「作品111」でご存知のようにこの作品は序奏を伴った堂々たるアレグロと感動的なアダージョの変奏曲の二つの楽章しか持っていない。ベートーヴェンは、これ以上何も付け加えることなしに、言うべきことを言い尽くしたと考えたのだろう。
こんなに性格の異なる二つの楽章を、何というか、ただぶっきらぼうに並べて、なおかつ見事なまでの統一性を達成しているというのは、控え目にいっても奇跡に類することだと思う。
もっとも、この曲を演奏会で聴くと、何といっても第二楽章の言語に絶する変奏曲が私の胸をしめつけるので、聴いた後は、第一楽章の音楽がはるかかなたの出来事であったかのような気分になることも事実だが。』
以上のように非常に抑制のきいた控え目な表現に大いに親近感を持ったのだが、「音楽の神々しさを適切に美しく語ることは不可能」という言葉に、ふと憶い出したのがずっと昔に読んだ小林秀雄氏(評論家)の文章。
「美しいものは諸君を黙らせます。美には、人を沈黙させる力があるのです。これが美の持つ根本の力であり、根本の性質です。」(「美を求める心」より)
いささか堅苦しくなったが(笑)、自分も「作品111」についてまったく著者の山本氏と同様の感想のもと、この第二楽章こそは数あるクラシック音楽の作品の中で「人を黙らせる力」にかけては一番ではなかろうかとの想いは20代の頃から今日まで一貫して変わらない。
とはいえ、ベートーヴェン自身がピアノの名手だったせいか、ハイドンやモーツァルトの作品よりも技術的には格段にむずかしくなっているそうで、標記の本では「最高音と最低音との幅がドンドン大きくなっている」「高い音と低い音を同時に鳴らす傾向が目立つ」といった具合。
言い換えるとピアニストにとっても弾きこなすのが大変な難曲というわけで、聴く側にとっては芸術家のテクニックと資質を試すのにもってこいの作品ともいえる。
以前のブログでこの「作品111」について手持ちのCD8セットについて3回に分けて聴き比べをしたことがある。
そのときのお気に入りの順番といえば次のとおり。
1 バックハウス 2 リヒテル 3 内田光子 4 アラウ 5 グールド 6 ケンプ 7 ミケランジェリ 8 ブレンデル

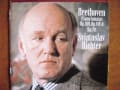

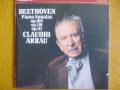

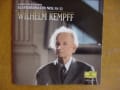


ちなみに、天才の名にふさわしいピアニストのグールドがこのベートーヴェンの至高のソナタともいえる作品で5番目というのはちょっと意外だけど、これは自分ばかりでなく世評においてもこの演奏に限ってあまり芳しくない評価が横行しているのだがその原因について先日のこと、音楽好きのオーディオ仲間が面白いことを言っていた。
『グールドはすべての作品を演奏するにあたって、いったん全体をバラバラに分解して自分なりに咀嚼し、そして見事に再構築して自分の色に染め上げて演奏する。モーツァルトのピアノソナタはその典型だと思う。
だが、この簡潔にして完全無欠の構成を持った「作品111」についてはどうにも分解のしようがなくて結局、彼独自の色彩を出せなかったのではないでしょうか。』
グールドの演奏に常に彼独自の句読点を持った個性的な文章を感じるのは自分だけではないと思うが、この「作品111」の演奏にはそれが感じられないので、この指摘はかなり的(まと)を射たものではないかと思える。
天才ともいえる演奏家がどんなにチャレンジしても分解することすら許さない、いわば「付け入る隙(すき)をまったく与えない」完璧な作品を創っていたベートーヴェンの晩年はやっぱり楽聖としか言いようがない。
クリックをお願いね →